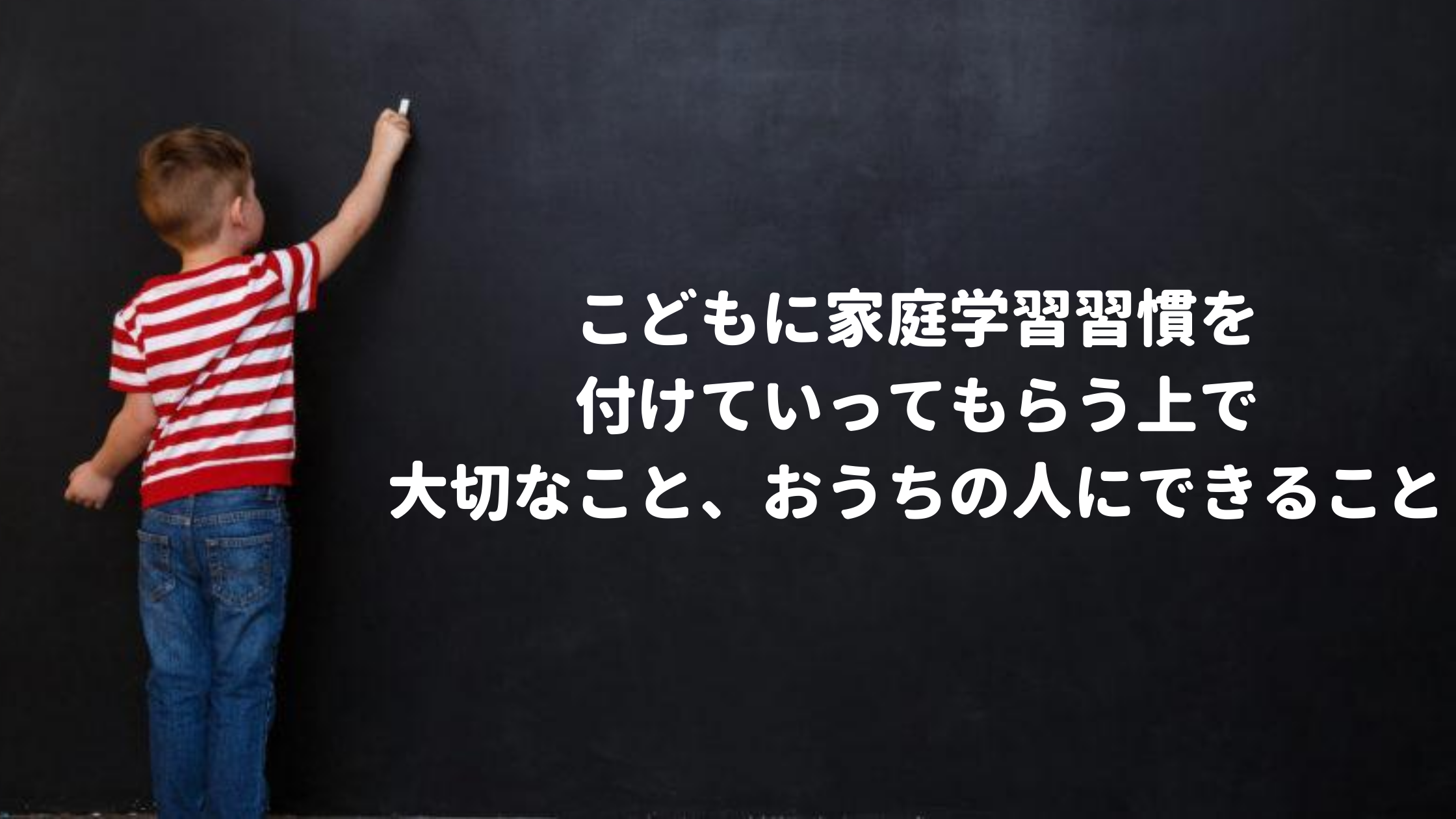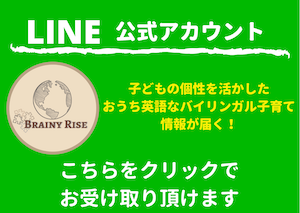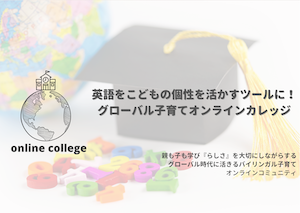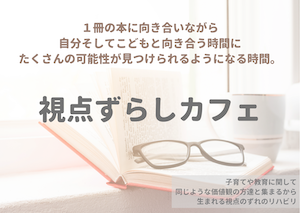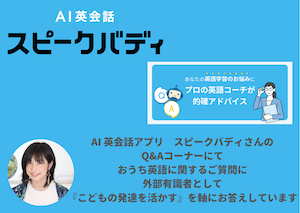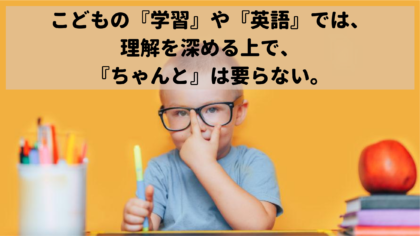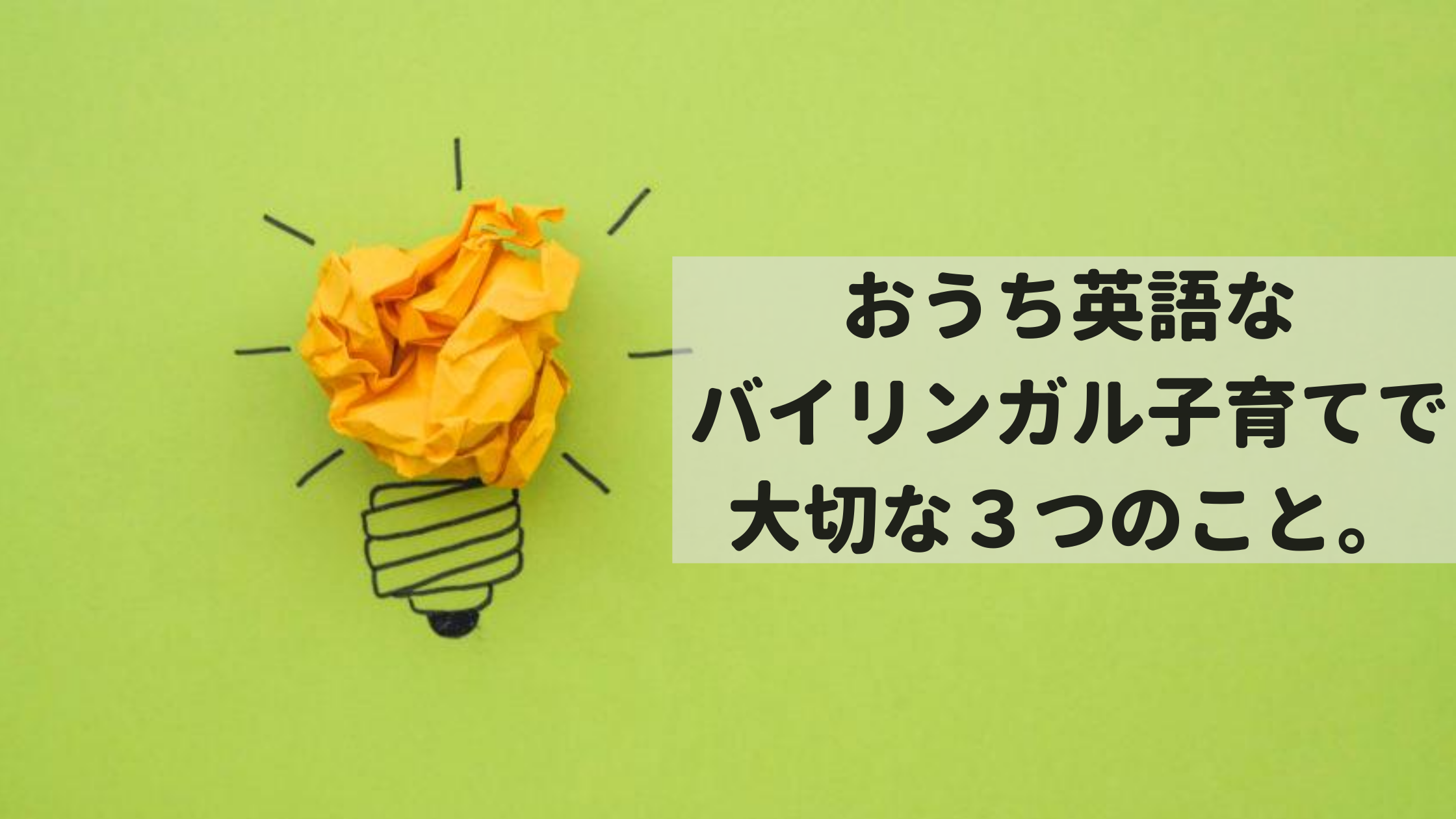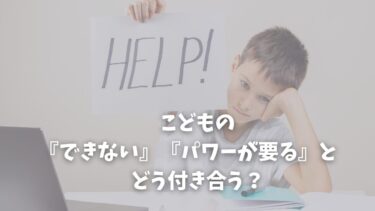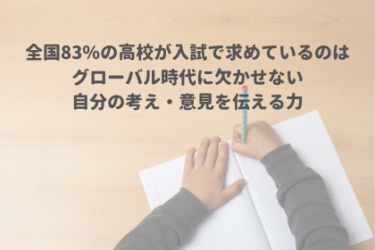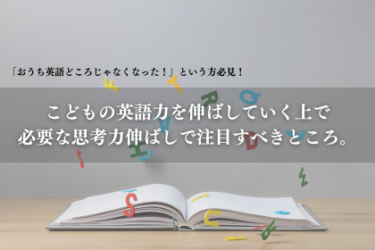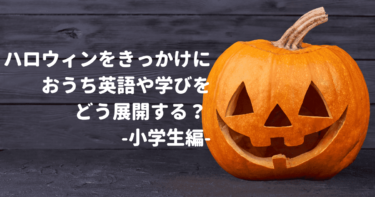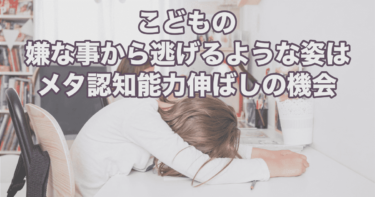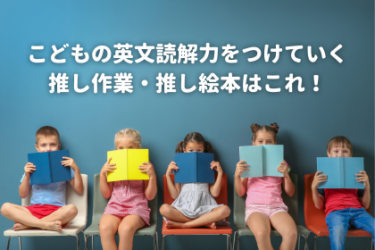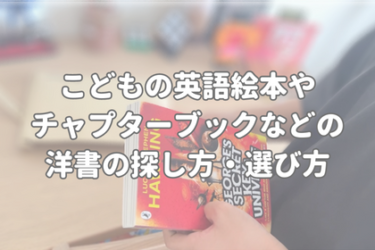子育て中のおうちの方であれば、多くの方が思われるであろう、
こどもに学習習慣が付くと良いなぁ…
という思い。
先日もお問い合わせにて、『こどもの学習習慣の付け方』についてのご相談がありましたので、今回その点についてブログ記事を書いてみたいと思います^^

目次
こどもは『学習力』を持っているから、
学習習慣を自分で付けられる。
以前からこちらのブログ記事でもお伝えさせて頂いていますが、これからの時代に求められる『非認知能力』って、言い換えると『こどもらしさ』だったりします。
その理由となるものを、以前こちらの記事にて書いていますね^^
もちろん、「経験」と「成長」によって得られる部分もありますが、
こどもの様子である、『好奇心』に満ち溢れ、調べたがりの試したがりの『探究心』が強く、「どうしてかな?」と思ったら直ぐに行動に起こす『自発性』は、非認知能力の根っこにあたる部分
です。

ですので、
こどもは元々『学び好き』だからこそ、「学ぶ力」って付けさせるのではなく伸ばしていくものだからこそ、学習習慣も付けさせるのではなく伸ばしていく事で得られるもの
なのです。

そもそも『学習習慣』って、何だろう?
先ず、我が子の「学習習慣力」を伸ばしていく上で、『そもそも学習習慣とは何だろう?』というところから考えていく必要があるのかなぁ…と感じています。
多くのおうちの方が『勉強/学習 習慣』に持たれているイメージって、
・頑張らないといけないもの
・何か形あるものをこなさせながら、付けていくもの
・成績のことを視野に入れながら触れていくもの
・とにかくルール化して付けていくもの
・机に向かって取り組むもの
・何か形あるものをこなさせながら、付けていくもの
・成績のことを視野に入れながら触れていくもの
・とにかくルール化して付けていくもの
・机に向かって取り組むもの
といったイメージだったりすると思います。

でもですね、『与えなくてもこどもは常に学びたがり屋さん』だから、大丈夫なのです^^
こどもは総じて『動きたがり屋』さん
「学習習慣を身に着ける=少ない時間でも机に向かっての学習する力をつける」
このような方程式を立てられるおうちの方は多いと思います。
これ、半分当たっていて、半分NOな感じです^^
こどもって、常に学びたがり屋さんではあるのですが、
こどもの『学びたい』というエネルギーは大きく、動き回って遊びながら学ぶ力を育て、そして学習していく
生き物。

故に、『自ら机に向かう習慣』って、なかなか付かなくてよく、『動き回って学習していくうちにつけていける』ものなのです。
動きたがりのこどもが、自ら学習習慣を付けていくには?
家庭学習で、自ら机に向かって学びをしない大きな理由は、単純に
楽しさを感じられないから
が理由。
本当に『楽しい』と思えれば、勝手に机に向かって学びをし始めるものです。
また、「お勉強自体は好きだけれど、机に向かっての家庭での学習習慣がない」という場合も同じです^^
「机に向かっての学習よりも楽しいものがそこにあるから」ということ。

・褒められる経験(認められる経験)の積み重ね
・「できた!」「わかった!」という成功体験の積み重ね
・「できた!」「わかった!」という成功体験の積み重ね
が、『知的好奇心を満たすって楽しい!』となり、机に向かうようになっていくのです。
この意識が芽生え易いのは、『好き』『興味関心』にじっくり向き合った時。
なぜならば、
学びの軸が『おうちの人』ではなく、『自分自身』にあるから
ですね!

その体験が、「自信」になるだけでなく、「もっと深めたい!」となっていき、それがどんどん形を変え、「机に向かって学ぶ学習習慣」に繋がっていくのです。
ですので逆に、「勉強しなさい!」「これに取り組みなさい!」と言われても、その学びの軸は「おうちの人」だから、「学びを楽しむ」って難しかったりする訳です。
そうなると、長続きしなかったり年齢と共に取り組まなくなったり…が出てき易いのは想像につき易いですよね。

その学ぶ力の根っこはやはり、こどもの『興味関心や好奇心』な訳です。
私自身、娘に「学習習慣をつけさせよう」と何かを頑張っていたりはしません。
もう、いつも下校後は遊んでいます。

故に「毎日」の学習習慣はないですが、勝手に
・知りたいことがあれば学ぶために机に向かう
・できるようになりたいものがあれば、机に向かって学びに入る
・できるようになりたいものがあれば、机に向かって学びに入る
という姿はあります。

また、もちろん…ですが、「机に向かっている時間だけが学びではない」ので、常に学び姿勢があるのがこどもというのはお忘れなく…。
先にも書きましたが我が家の場合、もちろん「毎日」でもないですし、「成績が一際良い」とか全くないです。
ないですが、『学びを楽しむ力』を今からしっかり付けて楽しめている姿には頼もしさしか感じない今日この頃です。