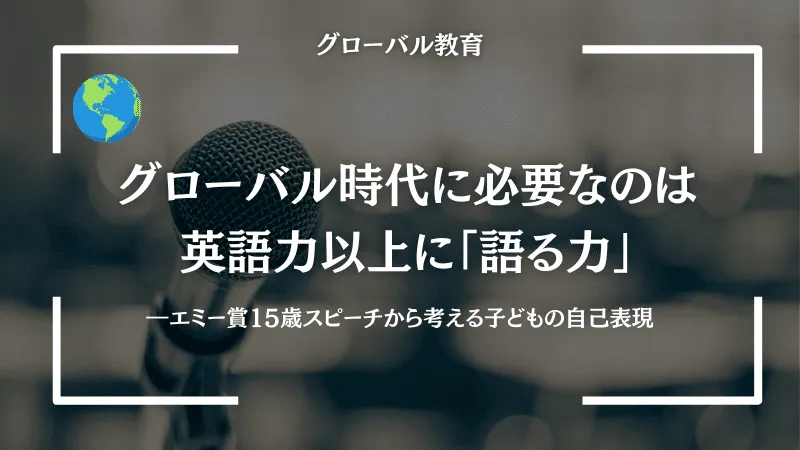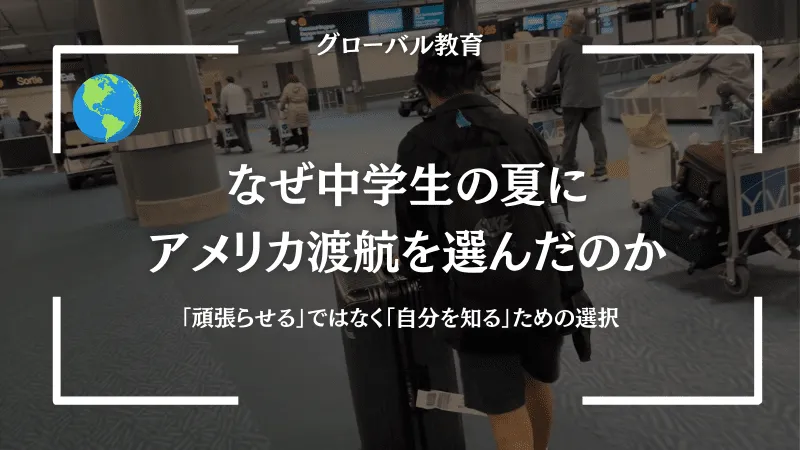こどもの発達と個性を活かすおうち英語でグローバル子育て、コーチコンサルタントの林智代乃です。
おうち英語に取り組んでいたり、海外教育に関心をもっていると、一度は耳にするのが「IB(国際バカロレア)」という選択肢。

探究的な学びや、世界を見据えたカリキュラムに魅力的に感じる方も多いのではないかと思います^^
実際、私が運営しているオンラインサロンでも、月1のセミナーで「IBについて取り上げてほしい」とリクエストをいただいたこともある程!
それだけ、関心の高いテーマなんだなと感じています^^
さて、そんなIB。
確かにとても魅力的なカリキュラムなのですが、それと同時に『誰もが楽しめるカリキュラムとは言い難い』ものではあると感じていたりします。
例えば、我が家の娘の場合。
このカリキュラムの良さを、十分に活かせるタイプではないのかもしれないな…と思っていたりします。
IB(国際バカロレア)って、どんな教育?
先ずは、IB(国際バカロレア)がどんな教育なのか…というところを改めて^^
『IB(国際バカロレア)』とは、スイス発祥の国際的な教育プログラム。
今では世界中で導入が進んでいるカリキュラムの1つなんですよね。
日本でも、ここ数年でIB認定校が増え、選択肢の1つとして注目されるようになってきていたりします。

IBの学びの特徴──“問いを立てて、調べて、考えて、伝える”
IB(国際バカロレア)は、探究学習を軸としたスタイルが特徴で
・それについて調べ
・考え
・自分の意見として表現する
というプロセスを大切しているカリキュラムなんですよね。
プレゼンテーションやエッセイ、ディスカッションも多く、単なる『知識の記憶』ではなく、『知識をどう使うか』『どう意味づけるか』という思考力を育んでいく設計になっているもの。
そして、多文化理解やグローバルな視点、社会貢献といった要素も含まれているんですよね。
正に、「これからの社会で生きる力」を育てようとしている教育だと感じます^^

IBは魅力的。でも、誰にでも“合う”わけではない?
このように、IBにはたくさんの魅力があるんですよね。
実際に、「こういった学びスタイルならば、こども自ら育っていけるかも!」といった感じに、ググッと興味持たれる方・持たれた方も多いと思いますし、私自身も初見の印象はそうだったんですよね。
ただ、我が子の思考タイプを見ていくと、
…と感じ、実はすぐにIBは選択肢の1つから消えていたりしました。

我が子がIB(国際バカロレア)と合わないと感じた理由
我が家の娘は、『結果』よりも『プロセス派』なタイプ。
ひとつの答えに向かって一直線に走っていくよりも、思考をあちこち広げながら、色々と試してみたり、考えてみたりするような時間を楽しむタイプの子なんですよね。
だからこそ、これまでにも「IBに向いてそうですね!」と言っていただくことが、実際にあったり。
確かに、パッと見はそうなのですが、思考の流れをじっくり見ていくと、娘の『探究』って、『IBで求められるような探究とは少しズレがある』んですよね。
『探究好き』なのに、IBだと逆にしんどそうと感じた理由
『探究活動が好き』=『IBのようなスタイルはピッタリ』といったイメージがあると思います。
実際、IB(国際バカロレア)は「探究型の学び」を軸にしたカリキュラムであることから、好奇心旺盛で思考の深い子には向いている、というイメージがありますよね。
でも実は、
ということを、娘を見ていて感じることが多かったりするのです。
…というのも
なんですよね。

この『決められたテーマの中で』というところが、娘のようなタイプにとっては、実はちょっとしんどいポイントだったりするのです。
『問いに答える』よりも『問いに出会う』タイプの子
娘を見ていると、
なんですよね。
例えば先日、娘が大好きなボーイバンド「One Direction」のライブDVDを観ながら、こんなことを言い出したんですね。
「あ!どうして1Dって、あんなにふざけてても許されるんだろう?むしろ好かれてるよね?…なんか、研究してみたくなった!」と。
その後、ライブDVDを見て、そして今まで見てきた動画を頭の中で再生し比較させながら、気付いたことをまずどんどんメモをしていく…というちょっとした『研究モード』に入っていったんですよね。笑

ちなみにこの探究の末、たどり着いたのが、「儒教の教えを守ることがポイント」らしいです。笑
(辿り着く先の独特感…^^:)
…と、こんな感じに娘の中では『ふと浮かんだ問い』がそのまま『探究の入り口』になっていくことが、本当に日常的によくあるんですよね。
しかも、同時進行で別の『ふと浮かんだ問い』への探究も行っていたり^^;
問いが生まれる瞬間に敏感で、それをスルーできないタイプなんですよね。
IBも確かに『探究型』の学びを大切にしています。
ただ、
なんですよね。
要は、『学習者が問いをもとに深めていく』というスタイルを大切にしているカリキュラム。
娘の場合、その
なんですよね。
故に、『探究が好き』という点では共通していても、IBのような『枠のある探究』は、娘にとったら窮屈になってしまうのだろうな…と感じていたりするのです。
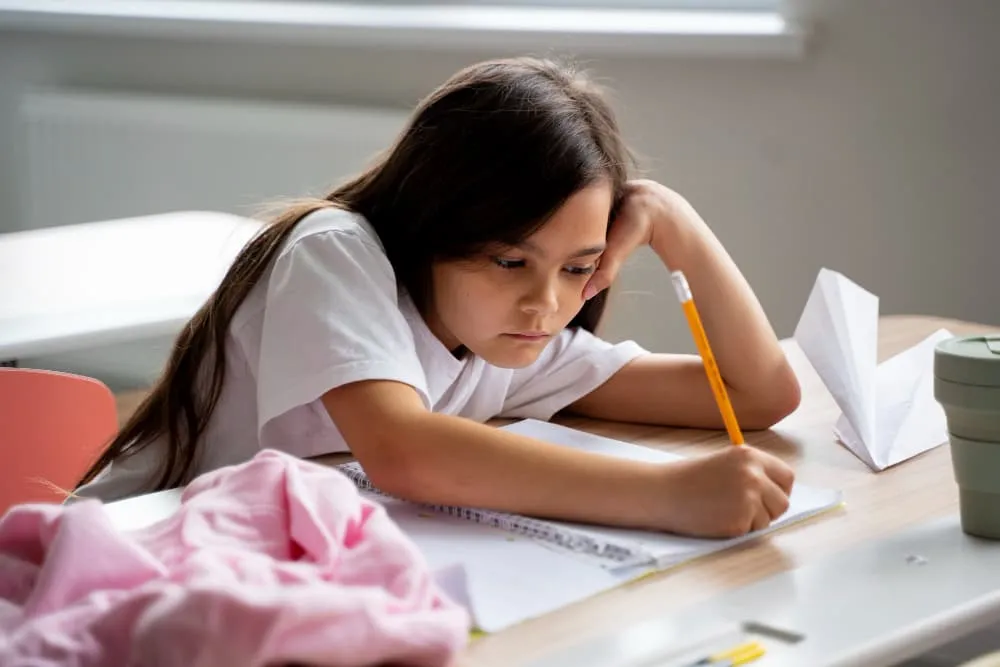
『自由に広げる思考タイプ』と『枠のある探究スタイル』のズレ
そしてもう1つ、「うちの子には難しいな…」と感じるのが、『ずっとひとつのテーマを深め続ける』という学び方。
娘は、とにかく『気になったら深掘りしたい』というタイプ。
しかも、その『気になる』は、
・ひとつを貫くよりも、関連づけながら思考を飛ばしていくのが得意
な感じ。
本人にとっては、どこに飛んだとしても、全てが『繋がっている』ものだったりするんですけどね!
ただこれが、IBのように『1つのテーマに絞って、定められた形式で論じる』というスタイルと相性がいいかと言えば…
正直難しいな…と感じる訳です。
選ぶは『良い教育』より『合う教育』
こういった『こどもの様子』を捉え、考えていくと
と改めて感じさせられます。

『合う・合わない』は教育の『良し悪し』とは別軸。
大切なのは、世の中的に「良い」と言われる教育をとにかく取り入れることではなく、目の前の我が子にとって「心地よい」教育スタイルかどうかを見ていくことなんですよね。
親のフィルターを外してみる
グローバルな視点・探究的な学び・表現力や論理性を育てるカリキュラム…。
やはり魅力的な要素が詰まっていますよね。
ただやはり、娘の思考スタイル(探究スタイル)に触れれば触れるほど
…と感じるんですよね。
もっと言えば、『世の中的に評価されやすい場』にわざわざ『頑張って合わせにく』必要はあるのか。
そして、それって、本当に『伸びていける環境』なのだろうか…というところなんですよね。
IBという教育が悪いということではなく、
訳です。
どんなに『良い』とされる環境でも、その子にとって心地よいものでなければ、その子の良さは表に出てこないんですよね。
それよりも、『その子が無理せず思考できる』『遠慮なく自分を出せる』、そんな心地よい場所を見つけることが何よりも大事だと私は考えていたりする訳です^^
「じゃあ、うちの子の場合、どんな思考スタイルなのだろう?」
「うちの子にとっての心地よさって?」
そんな風に感じられた時、その問いごと、誰かと一緒にゆっくり見つめてみるのも一つの方法だったりします^^