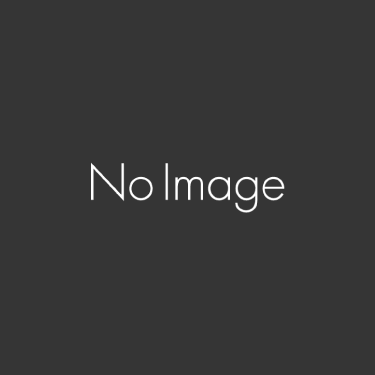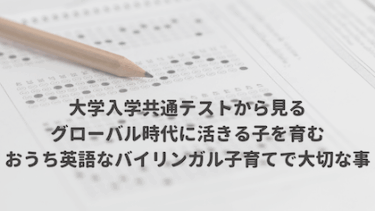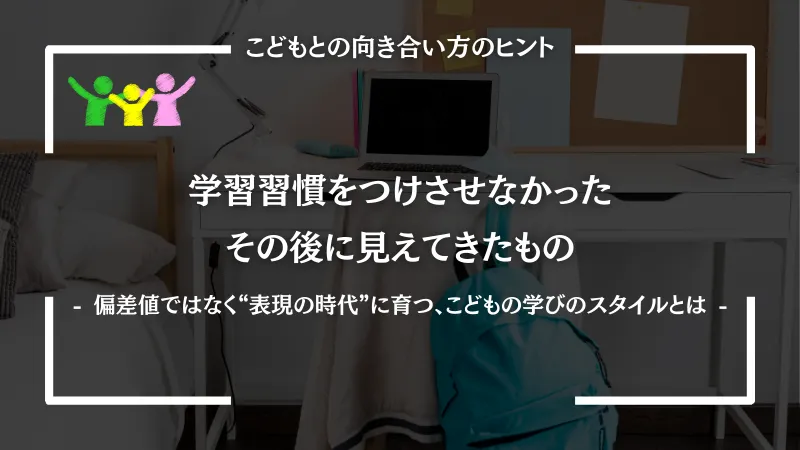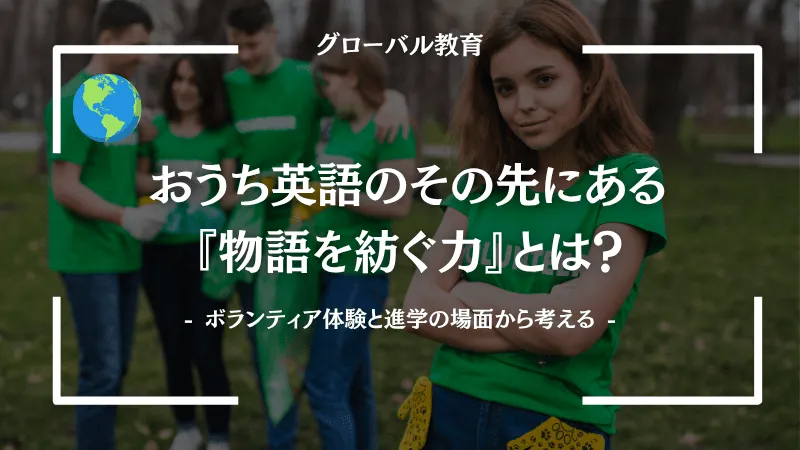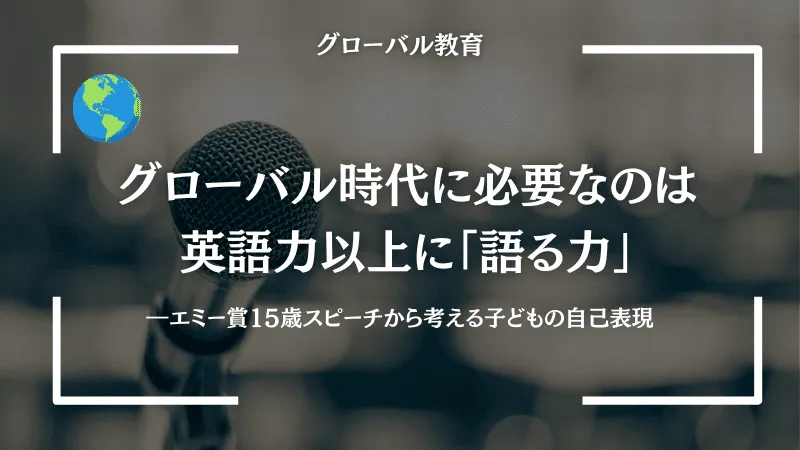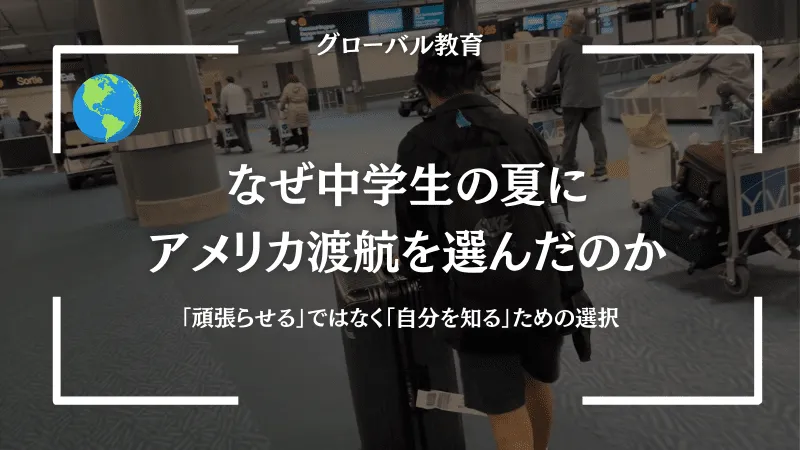インスタグラムでは、割と
・自宅での活動
(「取り組み」とまで言えるかな?…って感じなので。)
・こどもの興味とリンクさせて触れた本やワーク
についてこちらのHPブログよりも載せていたりします。
https://www.instagram.com/chiyono_hayashi/
まぁ、インスタグラムの様子を通して娘をみていると、こちらでも書いている以上に、ある意味『自由な』感じの様子が受けて取れるかなぁ…と思います^^;
特に【学校との付き合い方】に関しては。
最近はそんな娘の様子をきっかけにこちらのHPに来て下さる方も多く、HP内の検索ワードに
・学校 行きたくない
といった検索が増えているので、今回はその辺りについて書いてみようと思います。
『学校』との付き合い方は独特かも
タイトルに「かも」と書きましたが…
一般的に言ったら結構「独特」かも知れません。
学校には行ったり行かなかったり。
行くことがあっても、2時間目から…など「遅れての登校」だったりします。
(お友達や先生に迷惑が掛からないように配慮しながら…)

確かに『登校』に「〜しない」という意味の『不』という文字をつけ、『登校しない』ですものね。
そう考えた時、我が家は不登校。
そしてかなりポジティブな不登校です^^
娘が不登校的になる1番の理由は『できない』
我が家の娘は遅刻をして学校に行ったり…と不登校的な過ごし方をしていますが、決して学校が嫌だったりではないんです。
寧ろ、『学校という場所は大好き』な人。
インスタグラムでもお付き合下さっている方はご存知かも知れませんが、校長先生・教頭先生はじめ今年度の担任の先生にはとっても恵まれている娘。
まるっと娘の様子を受け止めてくださり、こどもたち各々に『認める』言葉をかけてくださる今の担任の先生の事は本当に大好き。
(私も感謝でいっぱいです。)
そしてその担任の先生がしてくれる授業は豆知識的な雑談を挟みながら…の授業で、娘は楽しいそうです^^

(最近はコロナ感染者数が増えた事を受けて、自粛してますけどね。)
また、学校を休んだ日でも放課後になれば公園に行き、お友だちと遊ぶ姿もあったりするので、お友だち関係で大きく躓いている様子は無い感じですね。
それでも学校に遅刻していったりお休みをしたりと不登校的に過ごしているのは、本人と改めて話してもやはり
・たくさんノートに文字を書く事が大変だから
(彼女基準での「多い・大変」)
という理由から。

1年生では登場回数が少なかった消しゴムも、今年は担任の先生からの良き影響で綺麗に書く事を意識し書き直す姿もあったり。
それでもやっぱり心の発達的に
「自分のできる/できない」を知り始め
周りのお友だちが幼児期の時よりも見え始め
周りと自分を見比べ始めるようになっていき
その過程で『自分』というキャラクターを作り始める時期
なので【自分のできないと向き合う時期】故に『書けない』という壁にぶつかるのは仕方のない事。

その向き合う過程に我が家は『学校には自分のペースで参加する』を選んでいる感じです。
発達凸凹(発達障害)さんでもそうでなくても
『できる』へのアンテナ張りを大切に
我が家の娘は、『書く』事に対しては本当にパワーがいるタイプ。
できる事とできない(パワーが要る)ものとの差が大きくある所謂『発達凸凹』さん。
故に『書く』への取り組みに躓くのですが
次第です。

そう考えた時、『今の我が子の状態を丸っと受け止める事で、その子の個性が輝く』のだからこそ頑張るのではなく『出来ている事』にしっかり着目する事が大切。
そして何よりも大事なのは、そうしていく中で
が大切なんですよね。

なんですよね。
自分に合った方法を見つける為の『頑張らない』
【代替え案】を知る為に、『自分の出来るを知り、そこに自信を持てるようになっていく事が大事』と先に書きました。
その為に大切なのは、
自分の【好き】や【心地よさ】をとことん追いかけられる時間
を過ごす事。
特に先々の事を考えていった時、小学校低学年くらいはこの時間を過ごす事がとても大事になっていきます。

・自分はこういった形のアプローチからなら楽しめる
などが段々と確立されていき、『うまくやっていける方法をすり合わせていける』ようになるんですよね。
この『すり合わせ方法』を見つけていく事を小学校高学年くらいの時期からし始め、中学校に入ってからの学業に対応できるように少しずつしていく。
その為にも今は、「できない」を頑張るのではなく『出来る』にアプローチをしていく事が大切として過ごしています。
不登校や「学校 行きたくない」は逃げではない
そうなると「なぜ『好き』や『心地よさ』を知る為に学校を休むのか。それは逃げではないのか?」といった疑問も出てくるかも知れません。
結論から言えば、
ので、嫌なものから逃げる癖などはそこで付くものではないです。

例えば我が家では、和やかな雰囲気で
・『学校』というところは世界中にあり、
どの国も平均的に7歳くらいになったら通う形になっているけれど、
それはどうしてなのだろうという話をしたり
⇨人の成長を考えて行った時に必要とされている場所なのだろうと話たり
・これからの時代、
「学校」という場所の形態は変わってくるかもしれないけれど、
それはなぜだろうという話をしたり
⇨画一的な学びではなく、
「『好き』や『得意』を伸ばす時代なのかもね!」という話に繋げたり
・世の中には学校には行きたくてもいけない子もいるという事を話したり
しています。

という事を考えてもらうようにしています。
色々な情報と選択肢の中から主体的に考え選びとってもらい、今どう過ごしたいのかを考えてもらっています。

(深刻的な感じで話すのではなくラフな感じで話てます。)
そして『好き』と『興味』を楽しんでもらう時間を過ごしてもらっています。
立ち止まるから自分が分かり自信もついてきた
上記のような考え方と付き合い方で過ごしている我が家。
学校を休んだ時の過ごし方はこどもの興味関心からで、
海外のオンラインがあればそれに参加したり
・パソコンで何かを作ったりして過ごしていたり
・絵を描いて過ごしていたり
…と特別学校の事や学校のカリキュラムを意識した時間を過ごしたりはしていません^^;
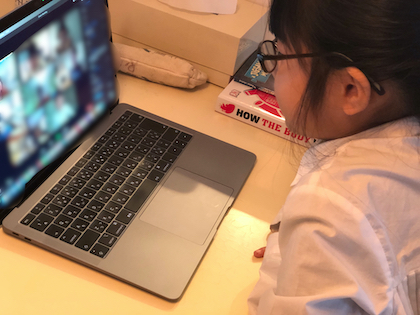
・自分に向いているアプローチ
・好きな事から広がる学び
・今までの点と点が繋がり深まる学び
などが生まれていっているのはとっても感じますし、こちもサポートがよりし易くなっています。
例えば、「自分は何か自分でアイディアを出して過ごす時間が好き!」という気付きとそこに対する自信を得たので、図工や(アイディアを出しまくる)生活の時間には積極的に参加しに学校に行ったり^^
そんな感じに彼女の中でバランスを取りながら学校に行き、学校という場所を活用しながら過ごしている我が家。
ポジティブな成長ある場所移動の1つとしての不登校です^^
※オンラインカレッジでは、月1セミナーはじめ交流会ではそういったお話ももりもりしています>>>