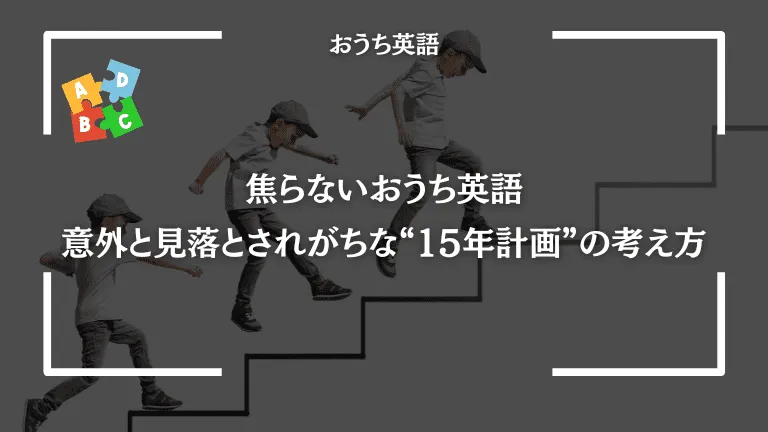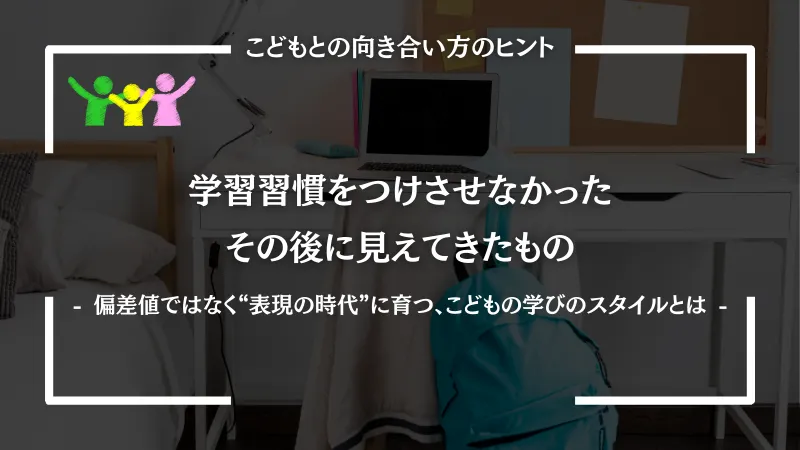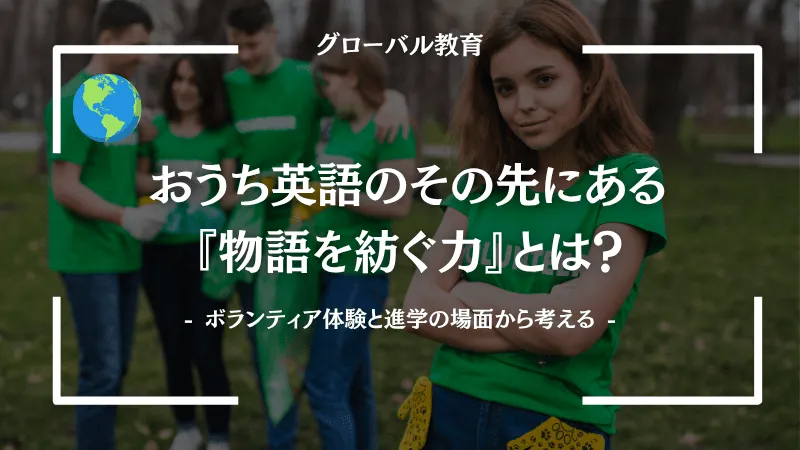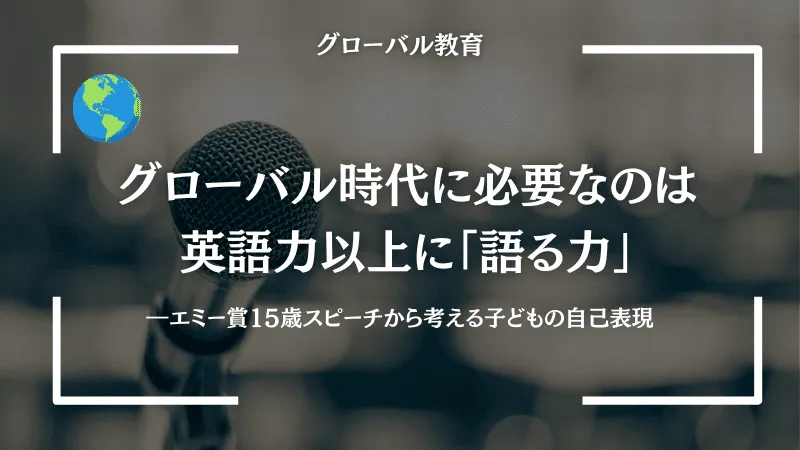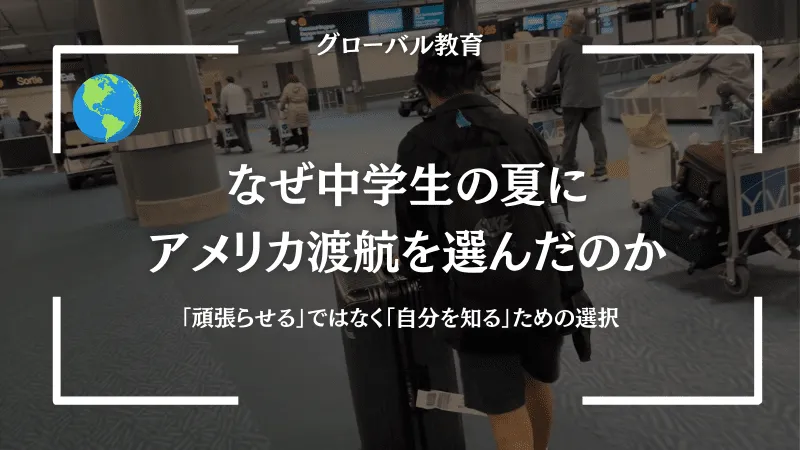最近、お問い合わせはじめコンサル生さんやカレッジ生さんには、乳幼児をお持ちの方もまた増えてきています。
そこで共通して多くの方に頂くご質問やご相談内容にあるのが、
に関するもの。
…という事で、バイリンガル子育てスタート地点で気になる事について改めて書いていってみようと思います^^

おうち英語なバイリンガル子育ての鍵は
『耳作り』
バイリンガル子育てでは『耳づくりさえしていれば良い』といっても過言でない程に、『耳を育てる』ということは大切です。
多くの方は、「耳を作る=聞けるようにする為」と思われがちですが、
のです。

こどもへの英語のかけ流しの役目はこれ!
英語のかけ流しをする目的は、
・英語の持つ文法的リズムを刻んでいくため
・聴き慣れた語を作っていくため
です。
決して、『流れてきた音源を覚えるためのものではない』のです^^

英語のかけ流しを通して各々の『リズム』を刻む理由
英語のかけ流しを通して、『音のリズム』『文法リズム』を刻んでいくことが、先ずは第一の目的。
各々に関しては、
英語のもつ音の変化や抑揚などを感覚的に刻んでいってもらうことを意味し
・『文法リズム』を刻むとは、
英語の持つ文の作り(文法ルール)を感覚的に刻んでいってもらう事を意味
しています。

これは、学校英語を通して『英語の文のリズム』が刻まれているからこそ、語順を間違えないでいられるのです^^
また、こんな経験はありませんか?
試験の時に出てきた並び替え問題を「この音の響きだと変化な…?」と、音の響きで並び替え問題を解かれたご経験。

このように『違った語順だと違和感を感じるような感覚を育てていく』事で文法パターンを掴んでいく事を狙いにしているのです。
英語のかけ流しを通して「聴き慣れた語」を作る
英語のかけ流しをする目的のもう1つは、『聴き慣れた語を作る』という事。
8歳になろうとする娘は今でも、日々「いつの間にそんな難しい言葉を覚えたの?」といった事が日本語でもよくよーくあります。
これ、日々親や先生などの大人の会話であったり、ニュースなどで聞いているうちに、段々と自分のものにしていっているんですよね。

覚えようとして覚えて知るというよりは、
のです。
それ(既知情報)を英語でも英語のかけ流しを通して作り上げていく感じです^^
英語のかけ流しを通して、『読める単語』を増やしていく
英語のかけ流しを通して聴き慣れた言葉が増えていく事で受ける恩恵は、『いつの間にか読める単語が増えている』という事。
本当に面白いほどに
のです。

『耳』は『目』よりも記憶の質が高いので、かけ流しでのインプットは思いの外溜まっており、そして記憶の質が高いからこそ直ぐに「思い出して」「リンク」させる事ができるのです。
我が家が文字読みに苦労を全くしてこなかったのは、『かけ流し』のお陰と言っても過言ではありません^^
「聴き慣れているもの」があるかないかでは、読めるようになる単語が増えていくペースが全然違う事を実体験からも感じています。
本当にラクだったので、かけながしをしてきて本当によかったと感じてならないです。

例えば、『民』という文字を習っていないのに、『国民のみなさんへ』という文字を見かけたら「こくみんのみなさんへ」と書いてある事に気付けたり…という事がありますよね。
よく耳にしているから、何という文字なのか予想立てできるんですよね。
英語のかけ流しにより英単語が読めるようになるって、正にそれと一緒なのです^^

『入れた記憶を呼び起こし読み進める」という作業であり、
これ自体が『アウトプット力』を上げてくれる作業でもある
のです^^

我が家も、もちろんまだまだ現役ですよ♪
1日、英語のかけ流しはどれくらいしている?
『英語耳』づくりは、かけ流しによって育てている我が家ですが、英語のかけ流しをしていく上で娘が赤ちゃん期から今までずっと心掛けているのは、
というもの。
『言語はリズム学習』と言えるほどに、リズムあるものに触れる事で言語習得部分が刺激を受け、言語習得を促してくれるからですね!

さて、『1日』にかけ流している時間数についてよく尋ねられる事がありますが、
形です。

毎日続ける事で、脳が『自分に必要な情報だ』と認識するからですね。
ですので、ずっと1日BGMとしてかけ流している日もあれば、20分しかかけ流さなかった時もあります。
それは今でも同じです^^
今でも
形をとっています^^

Podcastで聴いている番組は、下記のURL先のものです^^
良かったらご参考までに…!