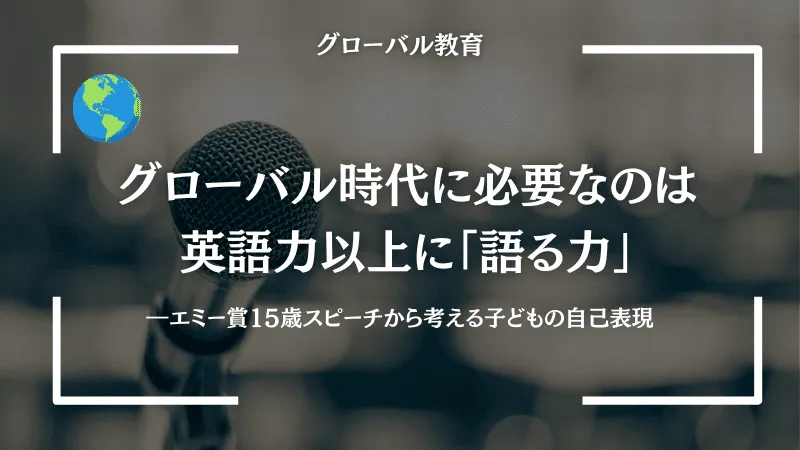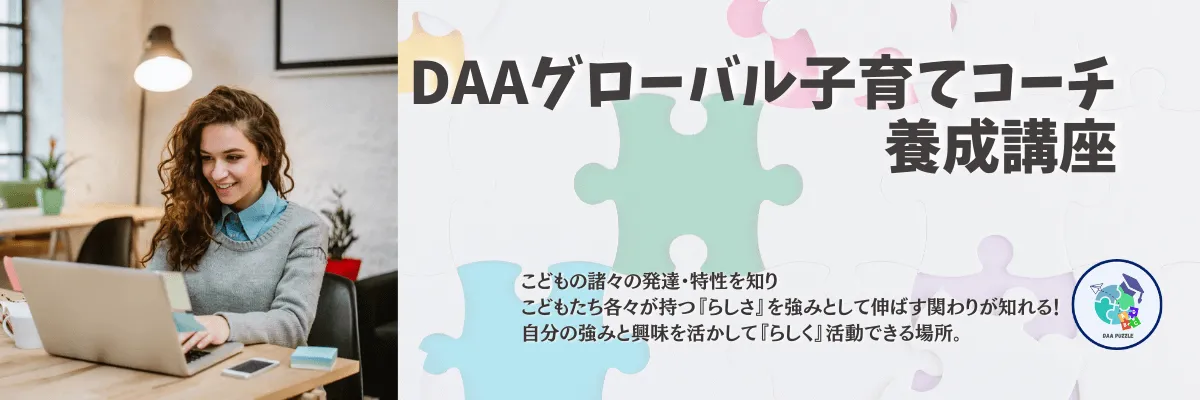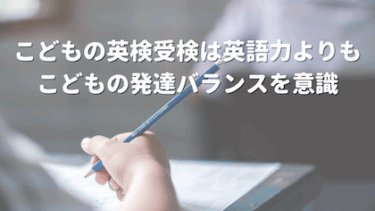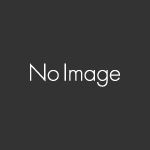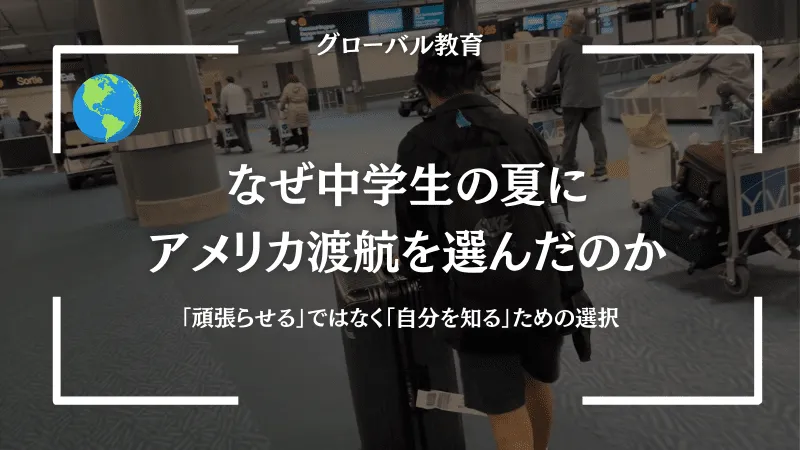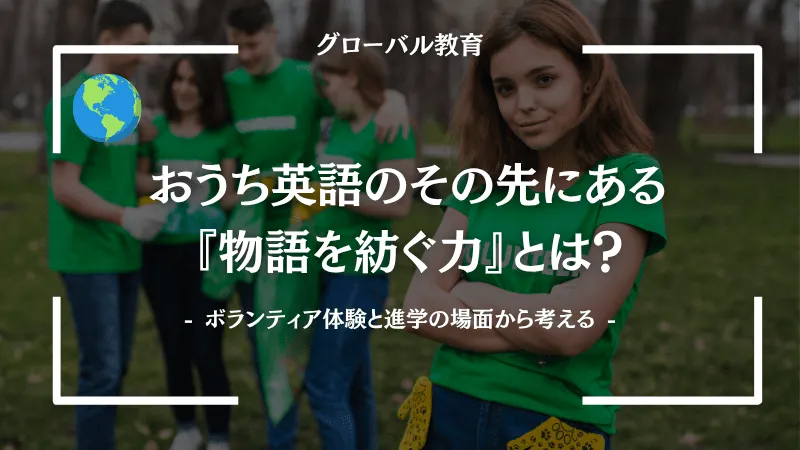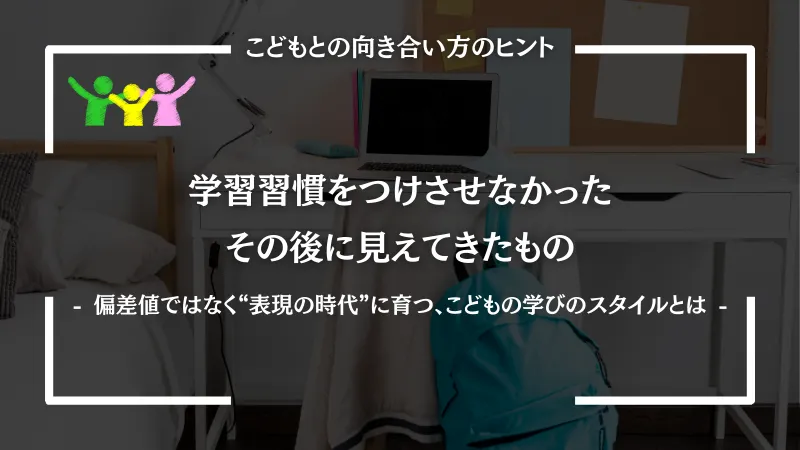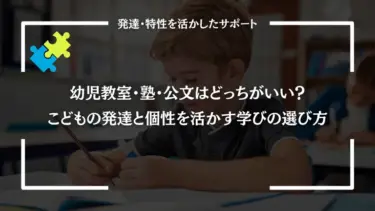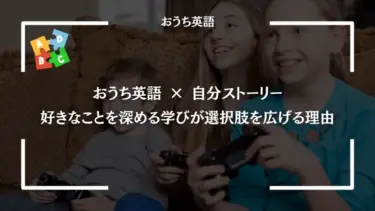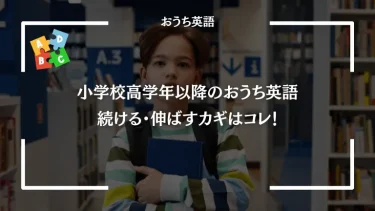こどもの発達と個性を活かすおうち英語でグローバル子育て、コーチコンサルタントの林智代乃です。
先日、アメリカで第76回エミー賞の発表がありましたね!
今回、史上最年少で俳優部門の授賞を果たしたのは、Netflixドラマ『Adolescence』に出演している15歳のオーウェン・クーパー(Owen Cooper)くん。
彼の演技は本当に圧巻の演技で、この賞の受賞はとっても納得もの!
ただ今回私がシェアしたいのは、「演技」そのものではなく、彼が壇上で語った受賞スピーチです^^
エミー賞15歳のスピーチが教えてくれる「語る力」
我が家では、娘が小さな時からスピーチを一緒に見ていたりします。
特にこどものスピーチではいつも、『角度が日本の子達とは違う』と感じる事が多いからですね。
今回の彼のスピーチもそう!
短いスピーチですが、その中でも凄さが詰まっているんですよね。
これを聞いた時私は、「同じ15歳でも、日本の子はこんな風に語れる?」と今回も思わされたんですよね。
(語れるお子さんもいらっしゃると思いますが!)
ちなみに彼は
でも今夜の栄誉は、自分の心に耳を傾けそして集中し、自分の快適な場所から一歩踏み出せば、人生はどんな事でも成し遂げられるという事の証明に証明になると思う。
僕は3年前、何者でもなかった。
(けど)僕は今ここにいる。
(だから)自分の心に耳を澄ませそして集中し、自分の快適な場所から少し踏み出してみて。
ちょっと恥ずかしい思いをしたからって、なんてことはない。
(一歩踏み出せば)なんだって起こりうるんだ!(後略)
…とスピーチしてくれているんですよね。
15歳の少年が。
日本の子どもが『語る力』を発揮しにくい理由
元々私は映画や洋楽が好きで、俳優さんやアーティストのインタビューを割とよく見る方で、その度に「欧米の人/子 たちの語る内容、すごいなー」って感心させられています。
…と同時に、「日本の子達には(自分のこども時代含めて!)、こんな発言は出てこない!」っていつも思わされるんですよね。
例えば日本の子達にスピーチやインタビューをすると多くの場合、
・「楽しかったです!これからも頑張ります!」…だったり
・「友達や家族に感謝しています。」…だったり
・「まだまだなところがあるので、努力していきたいと思います!」…だったり
…というパターンが多いと思うんですよね。

これはこれでよく言えていると言えるし、確かに感謝や謙遜は日本文化の良い部分でもあります。
ただ、折角心の中には、豊かな感覚や学びがあるのに
ところがあるんですよね。
問いを言葉にする習慣が『言語化』を育てる
まず、何が違うのか。
ここですが、
というところにあると思うのです。
欧米の教育では、小さな頃から『自分の意見を語る機会』が豊富なことは有名ですよね。
例えば、
・ディベートやプレゼンテーション
・エッセイやリフレクション
などこうした機会を通じて、『私はどう思うか』『なぜそう思うか』を語る練習が日常的に行われているんですよね。

最初から上手かったり、できたりする訳ではなく、そういった機会の積み重ねをしてきているからこそ出来ている。
実際、過去にオーストラリアの現地幼稚園で実習をした際も、そうやって『出来ない』から『できるようになっていく』瞬間を目の当たりにしたことがあります。
一方で、日本では、『感想文』や『発表』の場はあるものの、
だな…と感じるところがあります。
間違いを恐れる文化の中で、子どもたちは「自分の考え」を表に出すよりも「正解を答える」方が安全だと学んでしまいやすいところがあるんですよね。
英検を受ける子どもたちにこそ大切な『語る力』
特におうち英語の場合、気に掛けていきたいのは『英検』。
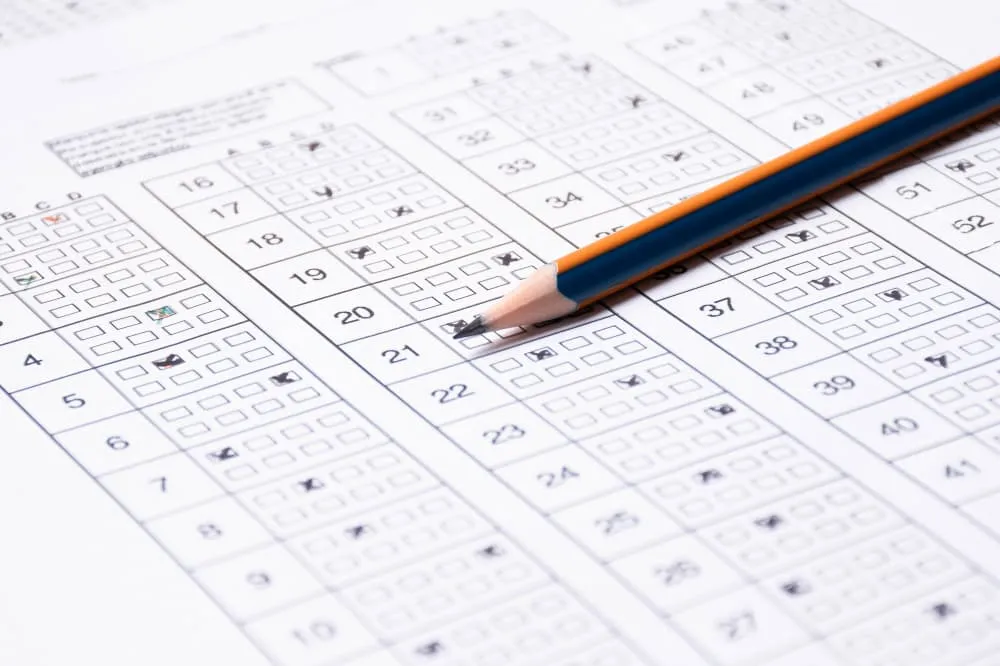
今、低年齢受験が多くなっていますが、そんな英検のライティングでも同じ事が言えるな…と個人的には思っています。
英検のライティングって、型を学んで臨むパターンが多いかな…と思うんです。
型を知っていった場合、一時的に点は取れるかもしれません。
ですが、『自分の考えをどう言葉にするのか』という積み重ねを普段から積み重ねていかなければ、中身はどうしてもついてきづらいもの。
自分の内側から言葉を紡ぎ出す経験を積む事。
これが、グローバル教育として必要な事だと思うからこそ、低年齢の英検受験は本当に気に掛けていきたいものだと考えています。
因みに我が家の娘も、本人の希望あって英検にチャレンジしましたが、ライティングの練習はあえて一切せずでした。
…というのも、まだまだ『積み重ねなければならないステップ』が娘にはあるからです。
グローバル時代に本当に必要な力|英語力の先にあるもの
グローバル時代に大切な事…といえば、『英語』と上がってくる事が多いと思います。
ですが『英語』って、そのものが最終ゴールではなく、因子の1つでしかないんですよね。
今年も先日、Appleイベント(新製品の発表)があり、そこでAirPodsにライブ翻訳(同時通訳)昨日が搭載される事が発表されました。
もう既に、「英語を聞き取れない/話せない」を機械(AI)が補ってくれる時代が来ているんですよね。
「だから、英語ができても仕方ない」などといった、そういう話ではもちろんないです。
でも、この流れが示しているのは
ということなんですよね。
じゃあ、『その先』とは何なのか。
それこそが、今回のオーウェンが示したような『自分の経験を社会や他人にどう意味づけられるか』なんですよね。
我が家での実践|スピーチ動画から始まる小さな問い

・「同じ立場だったら、何を話してみたい?」…であったり
こうした、『自己表現』の芽をどう育むかは、講座やサロンで深掘りしています。
【🗂️関連記事】
こどもの発達と個性を活かすからできる!グローバル力も育つバイリンガル子育て、林智代乃です。今、どんどん低年齢化が進んでいる 英検 受検。 我が家の娘は英検の級を持っておらず、受検の様子もない事もあってか[…]
こんにちは、こどもの個性を活かしグローバル力を育てるバイリンガル子育てコンサルタント、林智代乃です。我が子の英語力を考えた時、『話す』だけでなく『書く』の力も育てていきたいものですよね。ただ、この『書く力』を伸ばす取り組み。ここで最も大[…]