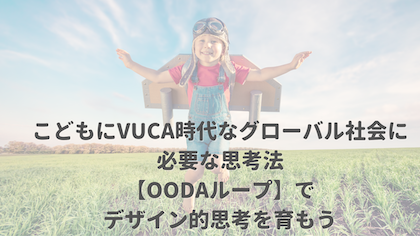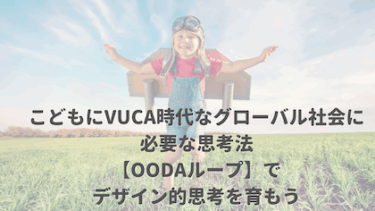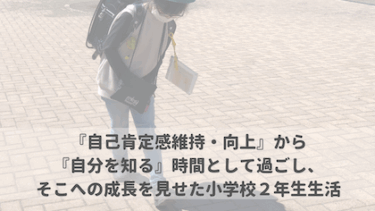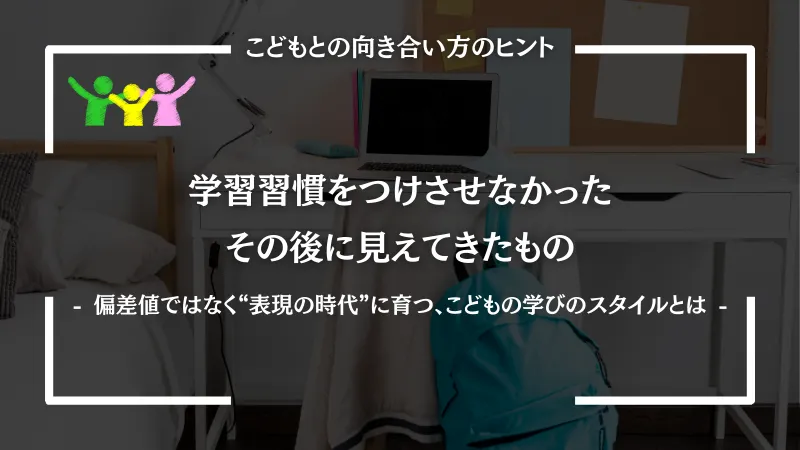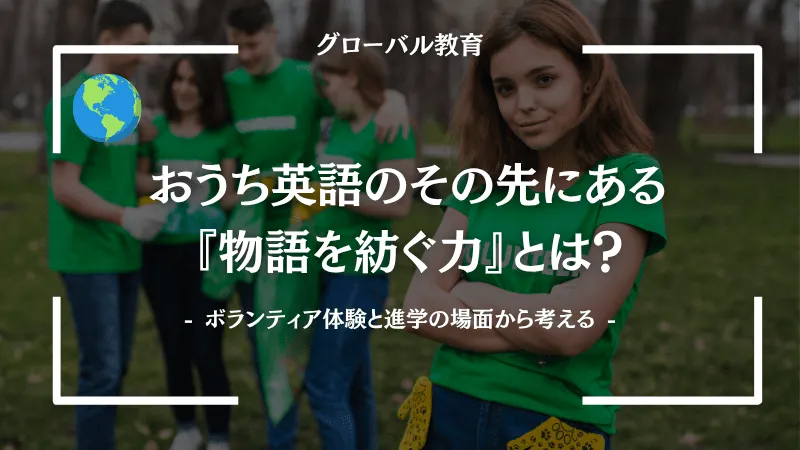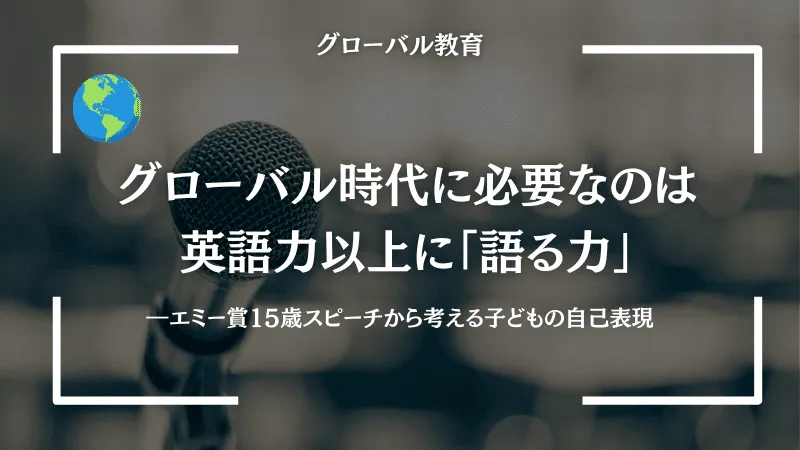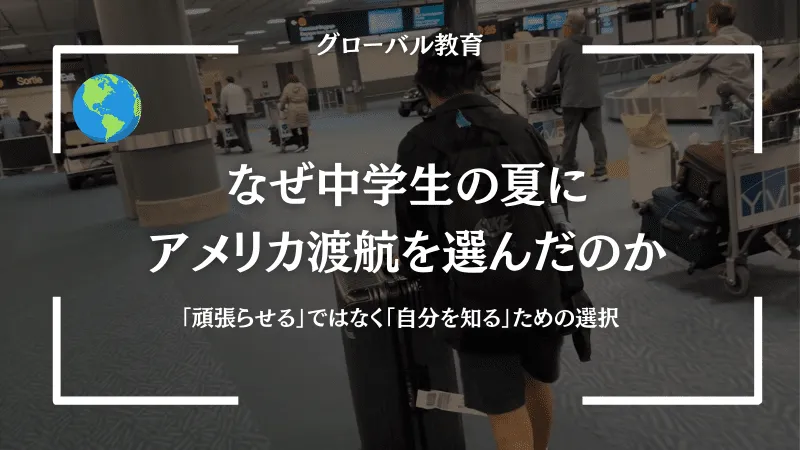新年度!
我が子がどんなお友だちとそしてどんな先生と1年を過ごし、どんな風に成長をしていく1年になるのかなぁ…と本当にワクワクな時期。
私も我が子がその成長をしていく過程でどんな風に英語や学習と関わり『自分らしさ』を表現していくツールとして伸ばしていくのかなぁ…という『未知さ』にもたまらなくワクワクしています^^

きっと『新年度』という事もあり、お子さんとこれからの1年に対する目標を立てられているご家庭も多いと思います。
この『これからの1年に向けての話』をする際に、少しだけ焦点を当てるところをズラすと、お子さんがよりワクワクしながら、そしてお子さん『らしい』形で伸ばしていってくれるものになりますよ♪
『我が子らしく』そして『ワクワクしながら』伸ばしていく際の焦点の当て先は『ゴール』ではなく『ビジョン』ににしていく事にあるんです^^

『目標』よりも『ビジョン』で描く!
年の初めや年度始めに、これから迎える1年に向けての『目標』を立てられる事があると思います。
『目標』というと、
・▲▲を毎日する!
などといった形で掲げていったりするものですよね。

ただ『目標』には、
というところがあるんですよね。
そうなると目標を立てる時に、
・「自分には無理だろうから、この目標はやめておこう…」
などの思いが付随してしまう事もあったり。
そのため、慎重なお子さんであったり挑戦する事に臆病になりがちなお子さんは、目標を立てる事自体がプレッシャーにもなってしまう事があるんですよね。

『ビジョン』を描いて向かうとメリットがたくさん!
『目標』から視点を『ビジョン』にずらすだけで『達成』でみるのではなくなり、『ワクワク』で付き合っていけるようになります。
この『ビジョンを描く』とは、
という点で物事を想像する事。
ゴールの一歩向こう側をイメージする感じですね!
例えば、新年度の今であれば、
といった形で描いていくんですね。

・『出来た/出来ない』よりも自己肯定感が育み易い
・「自分のあり方」を考えられるから自分軸がより育ち易い
・描いたビジョンにはどう到達していこうかと考えるので、
試行錯誤力が育ち易い
・ビジョンだからこそ、ゴールまでの道のりを都度作れる
・ゴールまでの道のりとなるものを色々と発想・創造しやすい
・ビジョンに向かって走る中で、
問題意識を持って向かう力がついてくる
・過程に掲げた目標を超える中で
問題解決能力もついてくる
・たくさんの道のりを作られるからこそ視野が広くなりやすい
・『結果』に着目し過ぎないからこそ
その過程における『経験から学ぶ』ということが出来る
などのメリットがたくさんなんですよね^^
以前、『目標は具体的よりも曖昧な方がよい』という記事を書いた事がありますが、そこに繋がる感じです^^
要はビジョンを掲げるからこそ、各々のポイントにゴールが生まれてくるという感じです。
『いかにデザインしていくのか』が求められる
これからの時代
これからの時代は『個性を活かしていく時代』と本当によく言われていますよね。
英語もそして知識はじめとする学習も『いかに自分を表現していくツールとしていくのか』が問われていきます。
『自分らしさ』を求められる時代だからこそ、
↓
自分自身で正解という形にデザインしていく
という事が求められていく時代になっていく訳です^^
そう考えた時、『こんな風になっていたいなぁ…』とぼんやりとビジョンを描きそこに向かっていく姿はまさに、『自分自身で描いたビジョンに向かってデザインしていく』という事になるんですよね。

ここを「上手に弾けるように頑張る!」や「間違えないで弾く!」などの『目標』で設定すると緊張が起きやすいもの。
…というのも「上手に出来なかったら…」「間違えちゃったら…」と『できる/できない』の目標がゴールになってしまうから。
ただここを、『弾き終わった後、どうなっていたいか?』という【ビジョン】で描くと、「できる/できない」ではなくそこまでをどう『デザイン』しようかとするので、発表会への臨み方にも変化が出てきたりするんですよね!
VUCA時代に必要不可欠な【OODAループ】という思考法
こちらのブログでも何度も取り上げさせて頂いている、これからの時代を象徴とする言葉、【VUCA時代】。
VUCA時代については、こちらの記事に書いていますね^^
VUCA時代はまさに『答えのないものに向かっていく力』が求められる時代。
そして最近であれば、
・地球温暖化に伴う気候変動や異常気象や災害
など、『今まで通り』という考えが通用しなくなっているのをひしひしと感じる出来事がありますよね。

をつけていく事。
故に今までは『計画(Plan)』をし、そこからの『実行(Do)』そして行動を『評価(Check)』し『改善(Action)』していくという【PDCAサイクル】の考え方がよくうたわれていましたが、今は、
→Observe
【状況理解】し
→Orient
【決め】て
→Decide
【動く】
→Act
という思考法が注目されています。
各々の頭文字を取って【OODA(ウーダ)ループ】と言われているものです。
この思考法もまさに「思い描いたものに向かって、今の状況を把握し(観察し)、状況を理解しどうしていこうか決め行動に起こしていく」というビジョン思考なんですよね。

OODAループはまさに子育てそのもの
『ビジョンを描く』という話から少し逸れますが、【OODAループ】ってまさに子育てそのものを表していると感じます。
子育てって、なんとなく「こうなってくれたらいいな!」と描いたビジョンに向かって関わり、そして『どうなるか分からないもの(計画通りにはいかないもの)』ですものね!
以前、取材をして頂いた際に、『おうちの人はじめ、こどもに関わる人たちに【こども】を知ってもうら事を目標にしている』という事を述べた事があります。
目の前のこどもの様子を『観察』し、そこからどんな状況なのか『状況理解・仮説』をし、こんなアプローチをしてみようと『意思決定』をし『行動に起こす』。
このようなループ思考でこどもと関わると起きてくる事は何なのかといえば、それは
なんですよね^^
こどもがビジョンを掲げて走り、自分で描くビジョンまでデザインしていく為にも、おうちの人はOODAループの思考法で関わる。
こどもがOODAループの思考法で向き合っていく上でもおうちの人自身がそのOODAループの思考法を大事にする事が大切だという事ですね!

・広げ
・リンクさせ
・達成感からの自己肯定感を感じてもらいながら
・次なる目標を掴み取る子たちのサポートを
させて頂いています^^
そしてお子さんたち自身にもOODAループの思考で考えていってもらう事を大切にしています。
だからこそ幼児さんから小学生さんまでサポートをさせて頂いていますが、どのお子さんも主体的に取り組み、パワフルでそして各々の個性や強みを伸ばしてくれているので、ご一緒させて頂いている時間は私が楽しいです^^
…という事で、お子さんとぜひ『1年後、どうなっていたいのか』というビジョン描きを是非されてみて下さい^^
もちろん我が家も毎年(そして年始にも)しているので、我が家の娘は来年のビジョンが描き上げています♪