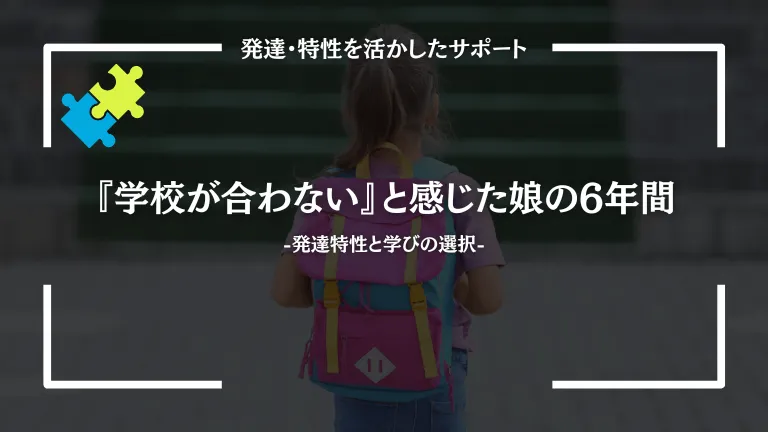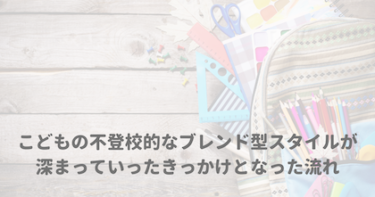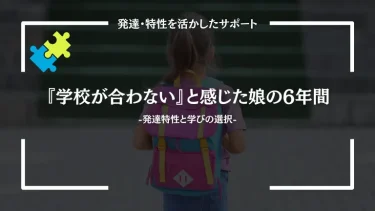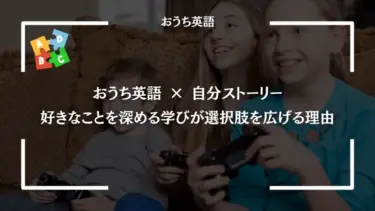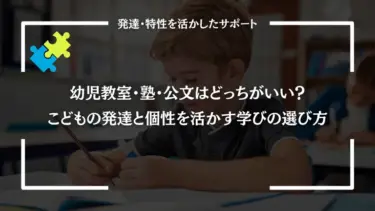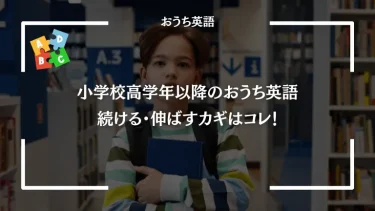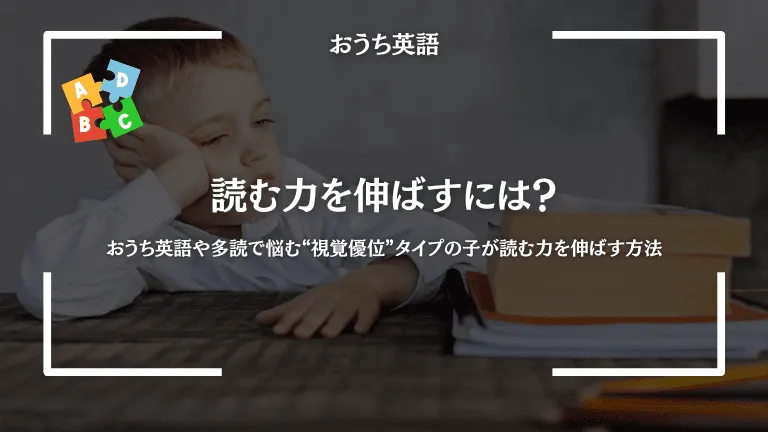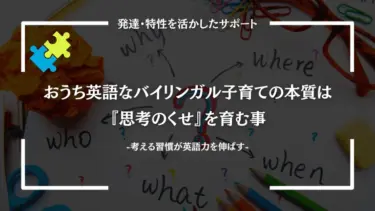こどもの発達と個性を活かすおうち英語でグローバル子育て、コーチコンサルタントの林智代乃です。
早いもので、我が家の娘もこの3月で小学校を卒業!
振り返ると、彼女の小学校生活は「よくある普通の6年間」とは少し違ったかもしれません^^
(何をもって『普通』というのか…は、置いておいて)
どんな6年間か…をざっくりと振り返ると
・宿題やドリルを終わらせる事よりも、主体的な時間を大切にした6年間
・体調や気分に合わせて、柔軟に学校生活を過ごした6年間
・一般的な登校スタイルではなかった6年間
といった時間。
こう書くと、「わがまま?」「大丈夫?」と感じる方もいるかもしれませんね^^
ですが、こういった過ごし方も別の視点から見てみると
時間だったりするんですよね。

故に、娘のこういったある種独特なスタイルで過ごした6年間に対して、焦りや不安を感じる事がなかった私です。
発達特性によって学校が合わないこともある
こどもそれぞれには、当たり前ですが『個性』があるもの。
その個性を模るものの1つにあるのが『発達特性』。
この
ものなんですよね。
過去に記事にした事が何度かありますが、我が家の娘はまさに発達特性の影響から、『学校』という場との付き合い方でいろいろな壁にぶつかっていました。
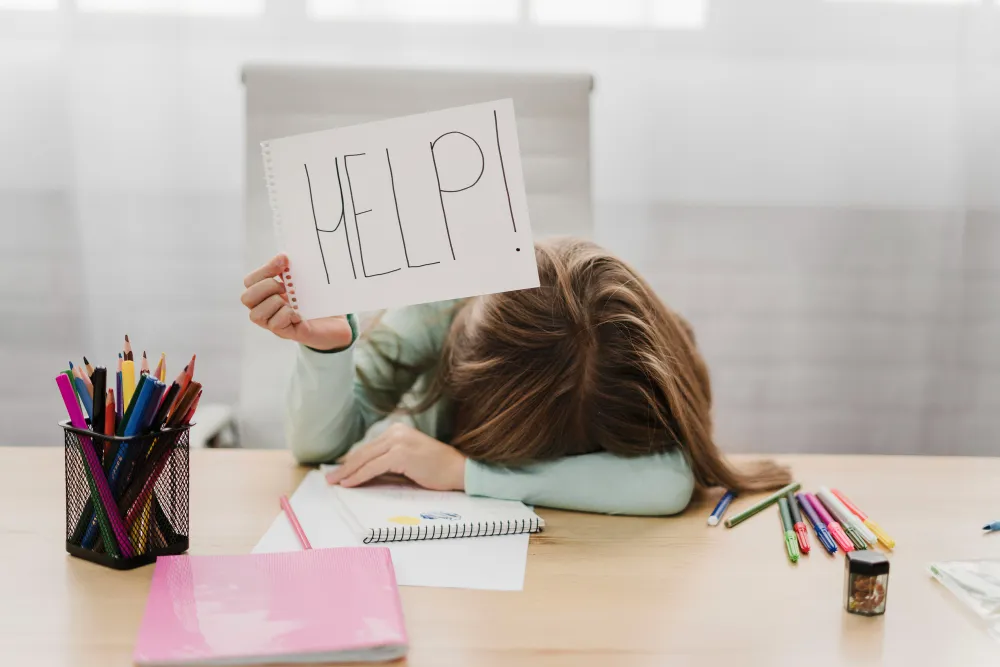
それはまさに
・人との関わり方
・環境との相性
が大きな要素だったんですよね。
それぞれ、どういった壁にぶつかったのか書いていってみようと思います。
発達特性に合った学び方タイプの違いで遠ざかった学校生活
入学してすぐの1年生の頃から、「『学び』は好きだけれど、『お勉強』は好きじゃない…」と伝えて来てくれる事があった娘。
割とすぐから、どこかフィットしない感じを感じていたんですよね。
そこから段々と言語化して伝えてきてくれたり、様子として見せてくれるものが増えていった感じです。
こどもによって『学び』のスタイルは、やっぱり大きく異なるもの。
発達の特性によって
ものなんですよね^^

実際我が子がどんな壁にぶつかっていたのか…というと…
教科ごとの学習スタイルの難しさ
いわゆる『教科毎』そして『単元毎』にバラバラと進む学習スタイルが彼女の思考プロセスと合わず、どうしても集中を向けることが難しかったというのも1つ。
娘の場合
といった思考スタイルを持つんですよね。

一方で学校は、教科を細かく分け、それぞれの単元を独立して学ぶスタイル。
娘の思考スタイルにとって、この学校のスタイルはどうしても「断片的で意味が見出しにくい」ものに感じてしまう。
それ故に、集中を向けることが難しくなっていったりしていたんですよね。
授業の進み方スタイルで立ち止まる
知的好奇心が何気に高めで、直感的に物事を把握しどんどん関連づけさせて思考を広げていくタイプの娘。
こういった子は、1つのことをきっかけに『これとあれはどう繋がるんだろう?』とどんどん連想し、考えを広げていく傾向があるんですね。
そのため、
ことも…。

これは、OE(過度激動)と呼ばれる特徴の1つ。
その中でもこの様子は特に
・想像力OE(空想や概念の広がりが大きい)
が強い子に見られる特徴だったりします。
OE(過度激動)とは?
例えば…
⬇︎
もっと掘り下げたい気持ちが強くなる。
⬇︎
でも学校の授業では『決められた範囲を決められたペースで進める』ことが基本。
⬇︎
その枠組みの中で思考を展開しづらい。
⬇︎
「考えを広げたい気持ち」と「授業の進め方に合わせなきゃ!」という意識の間で、ブレーキとアクセルを同時に踏んでいる状態に。
⬇︎
それ故に、「もっと考えたいのに、それを止めないといけない!」という状況が続くと、脳がフル回転しエネルギーを大量に使うことになる。
…という流れが生まれてしまうんですよね。
一方で、学校の授業はひとつのテーマをじっくり掘り下げるスタイル。

「この単元はここまで学んだら終わり。次は違う単元!」という形で進む。
その環境下では、なかなかと考えを広げることが難しかったりしたんですよね。
それ故、
んですよね。

正解を導きだすスタイルよりも…
また、まだどこか日本の教育スタイルとして残っているのが『正解を導き出すこと』を重視したような授業スタイル。
ここもポイントの1つだったりしていました。
『考えること』を楽しみたい、しかも『自由に考えること』を楽しみたい。
こういった思考展開タイプだからこそ…の葛藤があったりしていた訳です。
『書く』という作業にパワーが要る
入学当初に購入した1ダースの鉛筆を6年間使っていた程(買い足す必要がなかった程)、板書を取ったりする事がなかった娘。
それだけ『書く』という事をしなかった6年間。
これは
が故。

これは、頭の中で情報を立体的に整理する『視覚空間型』の特性が強い子にとっては、珍しくない事なんですよね。
また、言葉や概念を関連づけて覚えるタイプだからこそ、内容の流れは頭の中で整理できている。
そのため、改めて書く必要性を感じられていなかったのも1つではあったりします。
この『書く』に関しては、先生方からのご理解も多々あり、強制される事もなかった6年間。
(いや、厳密には1年生の時は理解してもらい辛かった面はありました)
そのため、その辺りに関しては本当にありがたく感じた6年間でした。
環境との付き合い方に立ち止まった
娘が立ち止まってしまったきっかけは『授業スタイル』だけでなく、『お友だち』という環境にもあったりしました。
言葉の影響を強く受け易かった
お友だちが何気なく口にする「バカ」はじめ「○ね!」といった言葉を耳にする度に『怖さ』を感じることが強くあった娘。
それが自分に向けられた言葉でなくても、周囲にそうした言葉が飛び交っているだけで不安な気持ちになってしまっていたんですよね。
「その言葉を受けた子は苦しい思いをしているんじゃない?」
「もしその言葉を言われた子が、本当に行動に起こしたら…?」
「その強い伝え方は、お友だちがびっくりしたりするんじゃない?」
そんな風に想像のスイッチが入ると、どんどん不安が膨らんでしまう。
それ故に、心が落ち着かなくなり学校を早退して帰ってくる事も多々ありました。

これもOE(過度激動)によるもので、過度な想像が働いてしまっていたからこそ…だったんですよね。
『違い』を知ってもらいたい
授業スタイルの違いを受け止めてくださった先生方もおり、娘も自分スタイルで過ごせる場面もありました。
ただ、どうしてもその度に周りの子たちからの言葉との付き合いに難しさを感じる事があった娘。

それは、パワーの要る『書く』に向き合っている時もあり、『違う事をする=問題/変な人』と捉えられてしまう事も少なくなかったんですよね。
まだまだ世界観が小さなこどもたち故に、違いを『知る』は出来ても『受け止める』事が難しい時期でもあるんですよね。
言ってしまえば、『仕方のないこと』。
寧ろそういった壁にぶつかったからこそ、娘なりに考える時間も持ててたので、それはそれで…と思う部分があったりする私です。
苦しくなっている本人がいるので大きな声では言えませんが、それにより娘にとっては『すり合わせ』の学びのひとつになっているな…と個人的には感じています。
この辺りについて以前記事にしたことがあります。
こどもの発達と個性を活かしバイリンガルを育てるグローバル子育て、林智代乃です。過去にもブログ記事に書いてきているのですが、我が家の娘は2年生の頃から学校に登校する日とお休みする日のブレンド型スタイルで過ごしています。娘がブレンド型の登校[…]
その子にとっての心地よさが、その子の力を引き出す
我が家の娘と同じようにこういった壁に出会い、立ち止まっている子・立ち止まった子はいると思います。
こうした『学び方の違い』や『環境との相性』、そして『言葉の受け取り方の敏感さ』などには、こども一人ひとりの感じ方があり、そこには大きな個人差・濃淡があるんですよね。
では、実際に
というところです。
こどものスタイルに合った関わりを見つける
実際、「我が子はどういったタイプに当てはまるのだろう…?」と色々と調べられるおうちの方も多いですよね。

その道の中で、
・ギフテッドタイプ
・HSC
・視覚優位
・聴覚優位
・視覚空間型
・聴覚継次型
…といった言葉に出会うこともあったと思います。
私のところにも
とご相談に来てくださる方も少なくないです。
それだけ【我が子に合った学び方】を探されているおうちの方が多いということですよね^^
目の前の我が子の様子を尊重していこうと思われての行動、本当に素敵だなぁ…と感じます。
確かに『どのタイプか?』を知ることは、大きなヒントになるものです。
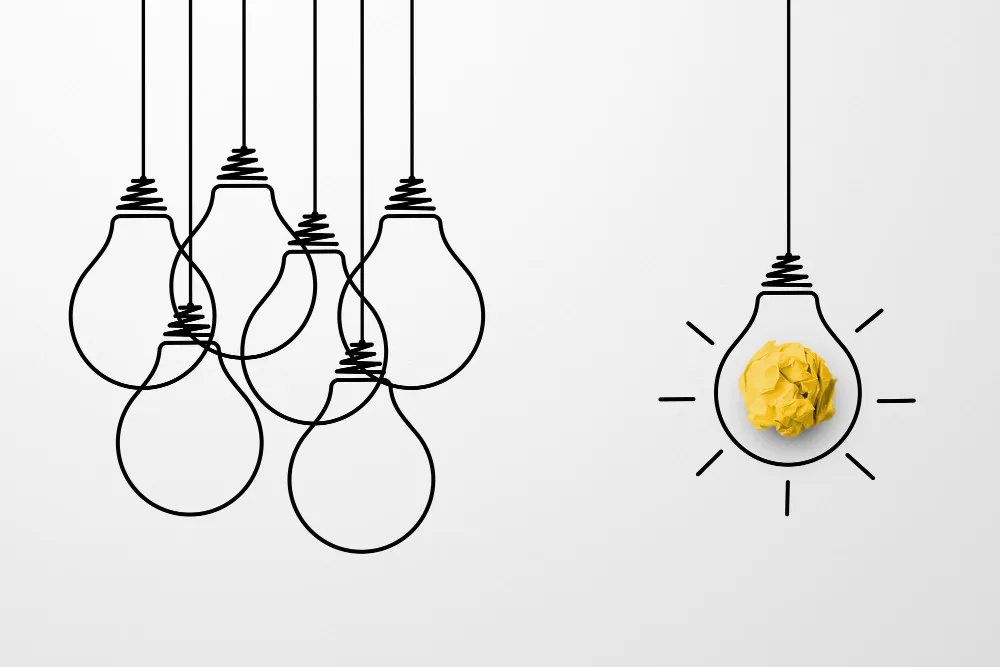
ただここは、『付き合い方』がとっても大事。
ここで本当に大切なのは、
という視点を持っていくことなんですよね^^
では、具体的にこどものスタイルに合った関わりを見つける為には、どうすれば良いのか。
この辺りは、長くなってきたので【後編】の記事として、『こどもにとって心地よいスタイル』を見つけていくための視点などについて書いていこうと思います^^