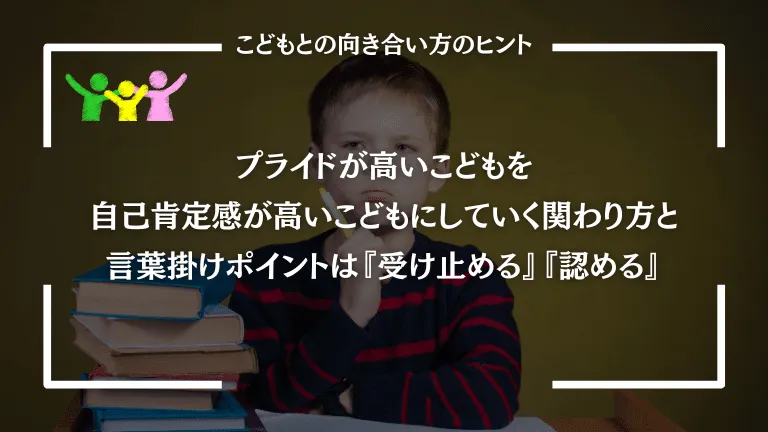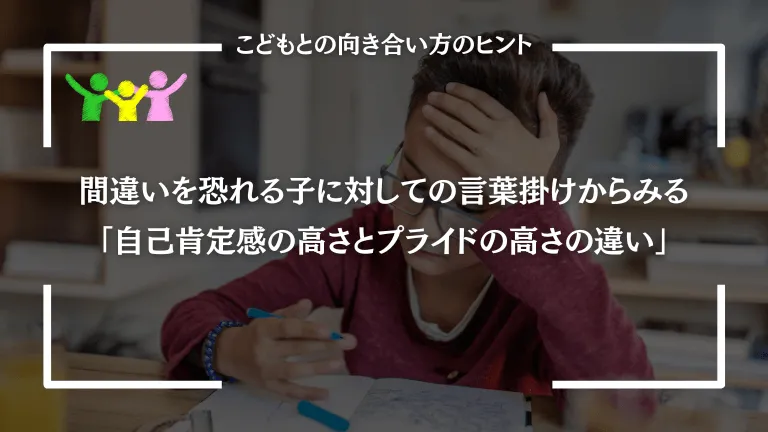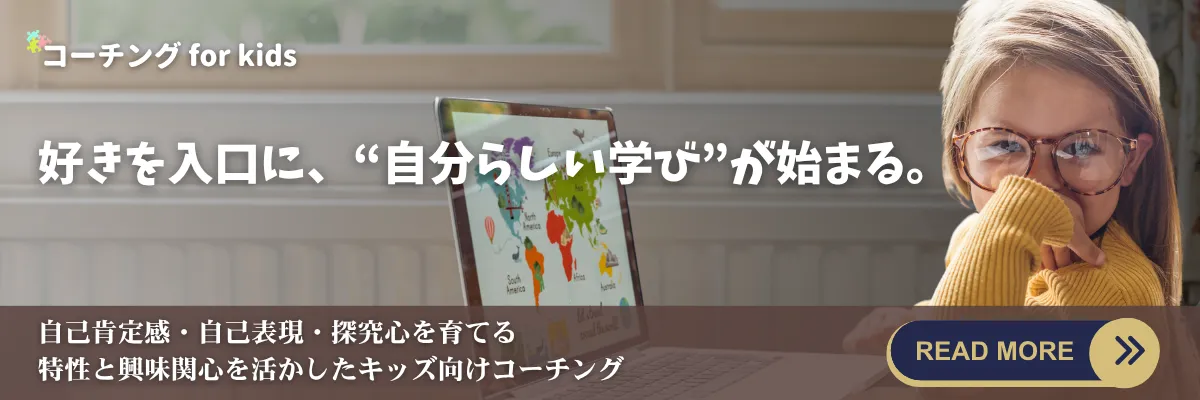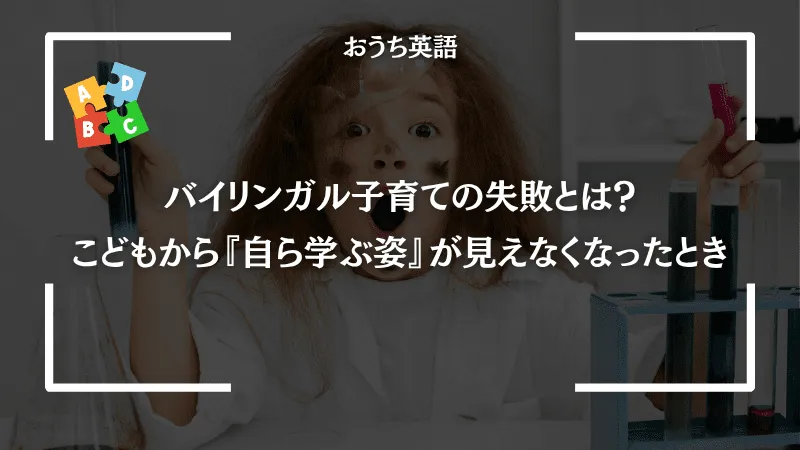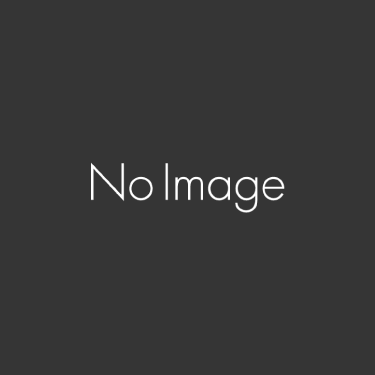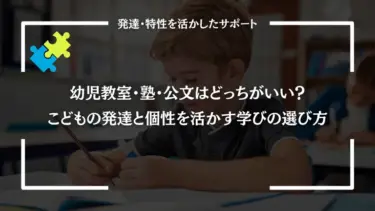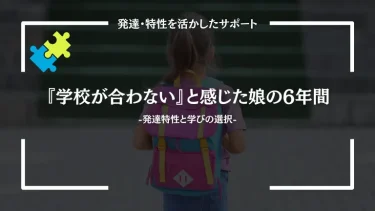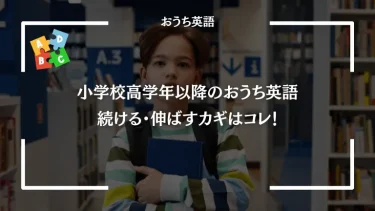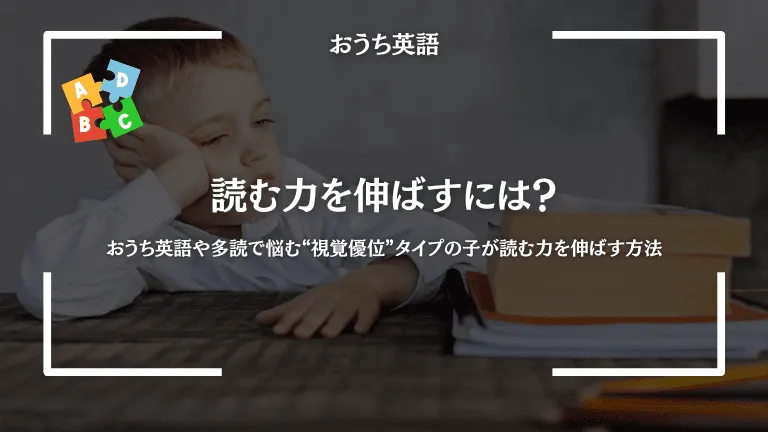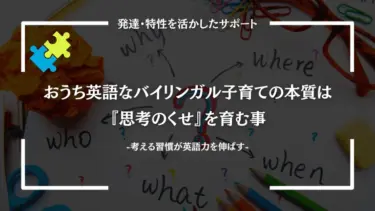こどもの発達と個性を活かすおうち英語でグローバル子育て、コーチコンサルタントの林智代乃です。
先日『自己肯定感が高い子』と『プライドが高い子』の違いから見る関わり方について書きました。
子どものプライドは、できた結果よりも「自分で選べた経験」から育ちます。発達や脳の視点からプライドと自己肯定感のつながりを…
早速お読み下さった方々から、
・我が子に照らし合わせながら、ふむふむと読ませて頂きました!
・頷きポイントがいっぱいでした!
・とても役立つ記事でした! そして「正に!」過ぎました!
といったお声などを幾つも頂きました。
メッセージを下さった方々、どうもありがとうございます^^

…と同時に、「こんな時はどう声掛けをしたら良い?」といったご質問を頂きましたので、具体例となるお話を今日は書けたらな…と思います。
ワークなどの問題が少し難しくなっただけで、こどもが挑戦しなくなる…
おうちの方からのワークなどの取り組みに関するご相談でかなり多く頂くのが、
といったお悩み。
確かに、プライドが高めな子は
・やればできるレベルの変化しかない問題
でも、「もう嫌!」と言ったり、深く考える前から予防線を張るかの如く「分からない…」と伝えてきてくれたりするんですよね。
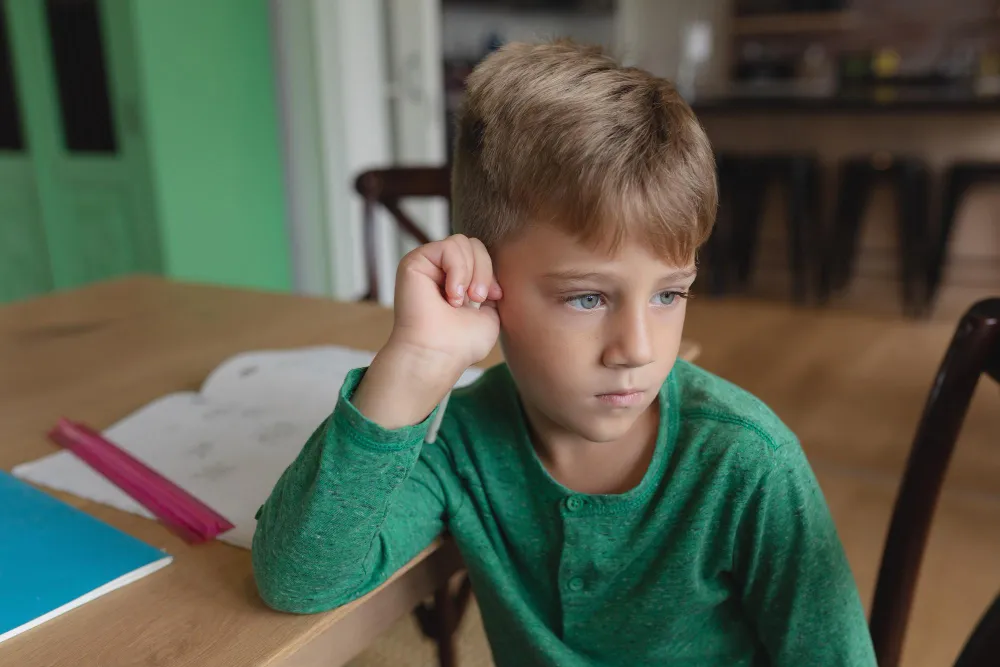
こういった姿を目の当たりにすると、『(プライドの高さ故に)逃げ癖がつき始めたのでは?』と【親】だからこそ気になりはじめてくるもの。
この姿が【逃げ癖】となるものになっていくのか、それとも【こども自身を育むもの】になるのかは、実はこちらの捉え方次第だったりするんです^^
逃げ癖に見えるような姿って、実は自分を大事にし始められている姿
こどもの「やらない!」「やだ!」といった姿を見ると、プライドの高さが逃げ癖を作っていっているのでは…と気になられると思います。
でもですね、これって一見するとそう受け取れるものですが
でもあるんですよね。
こう書くと、甘ったれた見方だと思われてしまうかもしれませんが、これって結構大事な姿。
この時の何気ない姿を尊重していく積み重ねこそが、自己肯定感の土台になっていくんですよね^^

【発達】という視点からお話をさせていただくと
でもあるんですよね。
心が落ち着く環境を確保しながら、自分なりのやり方を試し、少しずつ調整していく経験をすることで学んでいくものがあるのです。
こどもによって、物事に挑戦していく角度はさまざまで、その『挑戦をしていく角度探し』の時として捉える。
そうしていくとこどもは自分にとって心地よい方法を見つけながら、少しずつ心地よさの幅を広げていくようになっていきます。
その
のです。
実は、この時はこどもに「挑戦してもらう」よりも『切り上げる』事も大事!
いただきましたお声に
(間違えて書きたくない)
プリントをやることも嫌になる。
(間違い探しもそうでした。難易度が上がったらもうやらないとなってしまい、実際はたまたまできなかっただけで、大して難易度もあがってないのですが)
…ということがあります。
でも、実際はずっとそれが続く訳ではなく、後日もしくは数週間後には解決していることが多いので、悩むことでもないと思うのですが、どういう声かけをしてあげたら良いか?『出来ない』を認める声かけが気になります。
出来ないと言ってやらない時は「じゃあ、やめよ!」と言ったりしてしまうのですが、それもなんだかなぁ…と。
といったご相談がありました。
(引用の許可をいただいております)

『できない時は「じゃあ、やめよう!」と言ったりしている』との事。
実はそのアプローチで良いんです^^
一見すると遠回りに見えるような関わりが1番の近道
こどもとの関わりで最も大事な事は、
になっていきます。

親子間の風通しの良さは、その後の成長においてもとてもカギになりますからね!
ただ、そうすると先にも書かせていただいておりますが、「諦め癖がつくのでは?」といった思いを持たれるかと思います。
でも大丈夫!
我が子の言葉を受け止め切り上げることにより、諦め癖がつくことはないです^^
なんなら寧ろその逆で、

こどもの「諦め癖」や「辞め癖」は親の対応と言葉掛け次第で付かない
多くのおうちの方は、我が子に『挑戦心』を持って欲しいという思いを抱かれていると思います。
色々と経験をするから
・自信
・学び
・思考
などが伴ってくるものですものね!

この『挑戦心』がある子たちの殆どが『自己肯定感が高い子』であるのは、前回の記事からご理解頂けたかと思います。
そんな『自己肯定感の高い子』たちの特徴には、
・自分にOK!が出せる力
がありましたよね。
これは持って生まれた力というよりは、その視点を『周りの人との関わりを通して知っていく事』で育っていくものです。
ですので、ちょっとやれば分かりそうな問題から目を背けるような姿がお子さんにあった時、その時はその様子をおうちの方は『まるっと受け止める』のが良く、実はそれが結果「近道」な関わりとなるのです^^

頑張らせようとしないから、こどもは伸びる
「諦め癖がついたら…」や「ちゃんと取り組んで欲しい…」といったお家の方の思いで「やってみようよー!」「挑戦したら出来るかもよ?!」「●●ちゃんなら、出来そうだけれど…」の言葉掛けは、たとえどんなに優しめな口調でも
ようになっていったりします。
それはひいては「=今の私の思いは受け入れてもらえなかった」と感じてしまうものになっていくんですね。
特に『プライドが高めな子」たちには「いい子ちゃん / できる子ちゃん」でいたい傾向も強め。
だかこそ、「え?!辞めていいの???」とおうちの人からの予想外な提案は肩の力が抜けてちょうどいいんですよね^^

こどもが諦めかけたり挑戦をやめた時の言葉掛けは、例えばこんな感じ!
では、頂きました事例の場合、どんな声掛けをしたら良いのか…です。
こどもの様子を受け止めつつ、『既に出来ている部分を言語化し認める言葉掛け』をしていきたいのが先ず第一ポイント!
とは言え、目の前で諦めかけている姿をみると、認める言葉かけが見つかりにくく感じる時もありますよね!
『既に出来ている部分を言語化し認める言葉かけ』をする際のポイントは、【今目の前の瞬間の1つ前の状態】に認め・褒めポイントを探してみるんです^^
例えば
今の自分の気持ちを伝えられることは、とっても大切!
ここまでよく挑戦したね!
自分の気持ちを伝えられたこと、そしてここまで挑戦してみたその心がとっても素敵だったよ!
じゃあ、今日はここで終わりにしようね!
また今度でも良いから、『もうイヤ!』となった理由、今度こっそり教えてね!
なんて伝えながら
・認め/褒め
・こどもの思考の整理
をしていく感じですね!

「プライドが高い子」から「自己肯定感が高い子」へと変わる言葉掛けと対応。
言葉掛けの大きなポイントは『その事象の時』ではなく、『何気ない時間』にこそ意識して関わることがポイント!
そのポイントは、例えば普段のこんな関わり/会話だったりします^^
言葉の過保護となる先回りな声掛けを控える
ついつい親はこどもを思うあまり、先回りをしたような言葉掛けをしてしまう場面も少なくなかったりするもの。
例えば、おうちでの学習的な取り組みの場面で、もしこどもが鉛筆の用意をせず机に向かったとした場合
とこどもが気付いて行動を起こす前に伝えてしまったり…とかですね。
これが意外と「失敗する経験」「失敗からの気付きを褒める機会」を奪っていたりするんですよね。
また、敏感な子は、先回りをした言葉かけにより『完璧な状態を求められている』ような感じがしてしまったりするんですよね。

ですので、言葉を掛ける際は、
のです^^
私は本気で気が利かないので、ナチュラルでそうなってしまっていますが^^;
もし、言葉を掛けるのであれば、『こどもに考え気付いてもらう』ような『問いかけ』の言葉掛けにしましょう!
「だから言ったでしょ!」「ちゃんと聞いてた?」などの言葉を控えよう!
我が子へつい確認の意を込めて言ってしまいがちな、
・「〜だったから、▲▲になったんだよ。」
などといった言葉。

この言葉の裏側としてあるおうちの方の気持ちは、『失敗しない方法を伝える』だったりするんですよね。
ですが、この
んですよね。
実際は、こどもには『失敗してもいいんだよ!』『失敗してしまう自分の事もOKと受け入れてみようね!』と伝えたいのだから、
ように心掛けるのが1番ですね♪

もちろん!「完全に言ってはダメ!」ではないです^^
親子間で通じる「ギャグに似たようなノリ」でそのような言葉を使う事もあると思います。
実際、私もありますからね!
どれも「どのような意味でのメッセージなのか」それがポイントですね!
評価に依存したプライドを育まないポイント
…と長くなってしまいましたが、どの場面でも
を心掛けるようにし、我が子の「自己肯定感貯金」を積んでいってみて下さい^^
そうする事で、自己肯定感の土台がどんどん築かれていくので、自ずと挑戦心が育ち、逃げる姿勢もどんどんなくなっていきますからね!
…と同時に『遊び』などの『評価などと無関係な世界』をたっぷり味あわせてあげる事も同時に心掛けられて下さいね^^
というのも
ものです。
これは本当にグローバル力を育てるバイリンガル子育てに欠かせない時間です♪
キッズのコーチングでは、そういった部分を大切にしながら関わらせていただき、お子さんたちの強み伸ばしのサポートをさせて頂いています。
また、こどもの関わり方・こどもの目の前の姿を活かすサポートについては【オンラインサロン -Jigsy- 】でも多々シェアさせていただいています^^