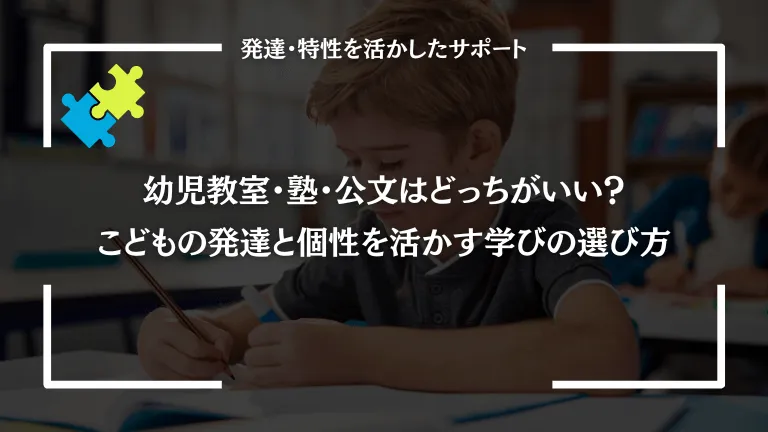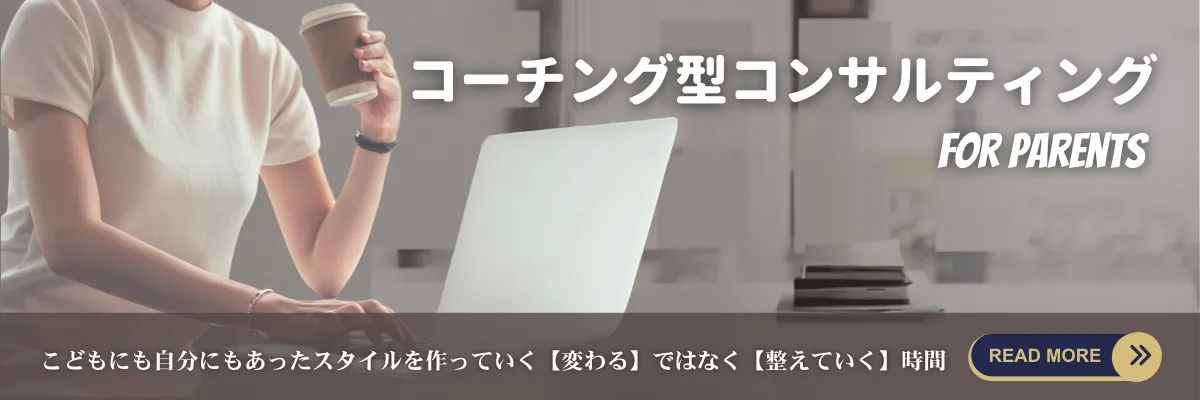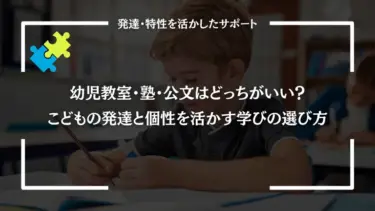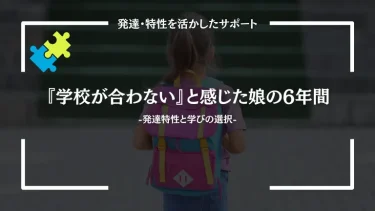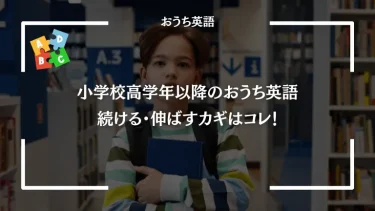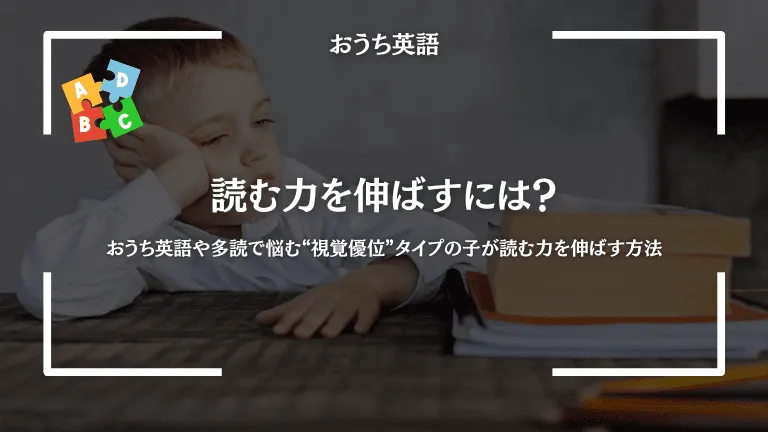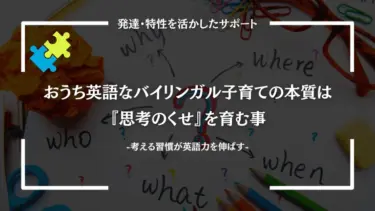こどもの発達と個性を活かすおうち英語でグローバル子育て、コーチコンサルタントの林智代乃です。
SNSやネットを開くと、「幼児教室はやっぱり必要?」「塾や公文のような反復学習なら学力が伸びる?」と考えてしまう場面って多くあると思います。
「◯◯をすると良い!」「◯◯はやめた方がいい!」などといった情報が溢れていると
結局、何をどう選べばいいんだろう?
と迷われてしまったりしますよね。

特に
…と迷われ、拮抗し合うものが出てきてしまったり。
先日も
子供の教育経験がない自分にとってつい幼児教室やプロの学習サポートに目がいくのですが、「思考力・探求心・好奇心」を育んでいくことを大切とした関わりをすれば実は不要なのか…、あるいは同学年の子と集団で学習するメリットも大きいのかなど気になります。
因みに自宅から近いという理由で娘は今、お試し感覚で公文(国語)をやっていますが、「思考力・探求心・好奇心」を養うと言う意味では逆効果なのかな…と不安もあり他の幼児教室の情報収集も進めている状況です。
この辺り、どのようにお考えだったりしますか?
…といったご相談をいただきました。
ご相談のメッセージを送って下さりありがとうございます^^

悩み揺らぐ気持ち、出てきますよね。
同じように悩まれている方って、実はとても多かったりします。
そんな時ポイントになるのは
だと考えています^^
この記事では、『幼児教室』や『塾』であったり『公文のような反復学習』を取り入れるか否かを考えてく時
・『発達段階』の視点から考える活かし方
・幼児期〜小学校時代における『心面』の成長を活かした取り入れ方
・そういった機会を活かす?それとも他の選択肢?
といったテーマをもとに書いていきたいと思います。
幼児教室や塾、公文はどんな子に合う?学び方にも合う・合わないがある?
学びの場には、幼児期の『幼児教室』、小学生以降の『塾』または『公文のような反復学習』の場など様々な選択肢がありますよね。
例えば…
→集団の中で刺激を受けながら、決まった時間枠の中で取り組む
・塾(小学生以降)
→学校のお勉強を補強したり、受験を意識した学びをする場として活用される
・公文のような反復学習
→繰り返し学習で基礎を積み上げるスタイル
といった特徴がありますよね。
このように、それぞれの学びの場には特徴があるもの。

故に、その特徴に『合う子・合いにくい子』がいたりするものなんですよね^^
幼児教室や塾・公文などに合う子/合いにくい子…って?
幼児教室や塾・公文などに合う子/合いにくい子って例えば…
○:『周りの影響を受けやすく、刺激が学びにつながる子』にとっては相性が良い場
△:『人の目を気にし過ぎてしまう子』は、集団の中で逆に萎縮してしまいパフォーマンスを発揮しづらい事も
・塾が合う子/合いにくい子
○;『ルールが明確な環境の方が集中しやすい子』にとっては相性の良い場
△:『自由度が高い方が思考が広がる子』『自分のペースで考えたい子』にはカリキュラムが固定され過ぎると窮屈に感じる事も
・公文のような反復学習が合う子/合いにくい子
○:『決まったパターンの繰り返しが安心する子』『コツコツ続けることが得意な子』にとっては相性の良い場
△:『試行錯誤しながらと考えたい子』『1つの問題をじっくり掘り下げたい子』には単調に感じる事も
といったようなところがあったりします。
だからこそ大事なことは、何が良いか悪いか・効果的か否かという角度から見るよりも、こどもの成長の中でそれらを『どう活かすツールにするのか』という視点を持ってみることだと考えています^^
『合う』『合いにくい』は、発達段階や特性が関係している
「うちの子に合った学び方って、なんだろう?」と考えた時、まず大切にしたいのは
個性・特性
の視点。
「うちの子には、どんな学びの場が合っているのかな?」と迷った時、まずは
なっていきます。

学び方を選ぶ前に、『こどもがどんな風に学んでいるのか/学ぶタイプなのか』を観察してみる事がとても大事なんですね。
そこには【観察】がとても大事になってきます。
この辺りについては、各々の時期の成長発達の角度と共にみていきたいと思います^^
幼児期(0〜6歳):土台を作る時期
この時期の発達の特徴
・「やってみたい!」の気持ちが芽生える時期。
┗自分でやってみた経験が、【探究心】や【挑戦する力】へと繋がっていく
ただし、「やってみたい!」の強さはこどもによって異なり、慎重な子は「まず見てから試す」ことが安心に繋がる事も。
・「共感してもらうこと」が心の土台になる時期。
┗「すごいね!」よりも「やってみたかったんだね!」と気持ちを受け止めてもらう経験が、【自己肯定感】や【人との関係性を築く力(協調性)】へと繋がっていく。
この時期の学びを『より活かす』ために
・『どんな遊びや活動に夢中になっているのか』を観察する
→何に熱中しているかを見ることで、「どんな学び方が合っているのか」が見えてくる。
音をよく聞いている子 → 聴覚からの学びが得意?
→「どの活動の時に目が輝く?」…とこどもが楽しく学べる環境見つけの機会として活かす
例)何かを発表する時にワクワクしている? → 人前での表現活動が得意タイプ?
→『スラスラできるものが楽しい?』それとも『じっくり考える方が好き?』などのその子に合った取り入れ方をしる機会として活かす。
例)最後までやりたがる? → 達成感を感じるタイプ?それとも完璧主義タイプ?

小学校低学年(6〜9歳):思考を広げる時期
この時期の発達の特徴
・『正解を出すこと』に価値を感じ易い時期。
┗『答えを導き出す経験』が、【論理的思考力】や【問題解決力】に繋がる
・『認めてもらう』ことがやる気に繋がる時期。
┗『頑張ったプロセスを評価される経験』が、【自己調整力】や【学び続ける力】に繋がる。
この時期の学びを『より活かす』ために
・どんな時に楽しそうか…を観察する
→目の前の子が『学びのどの部分に楽しさを感じているのか?』を見つけていく。
・塾を『どんな学び方をしているのか』を見つけていく観察の機会として活かす
例)難し問題を解く時、楽しそう? → 論理的に考えることが好きなタイプかも?
・公文のような反復学習の場は、『どこで止まるのか』を見つける機会として活かす
例)途中で飽きるのはなぜ? → もしかしたら、学習スタイルが合っていないかも?!
簡単すぎて退屈そう? → もう少しチャレンジングな問題を足してみる?!

小学校高学年(10〜12歳):論理的思考が育つ時期
この時期の発達の特徴
・「自分の考えを持ちたい!」という気持ちが育つ時期。
┗「自分の意見を伝える経験」が【プレゼンテーション力】や【主体性】に繋がる
・『評価との付き合い方』を学ぶ時期。
┗評価との付き合い方は低学年から始まってはいるものの、高学年になると『他者の目を意識する事が増え、自己の評価が揺らぐ時期』に。それにより自尊感情が低くなり易い時期でもあるので、より『結果ではなくプロセスに価値がある』事を意識的に伝えていきたい時期。これが【自己調整力】や【目標設定力】にも繋がっていく
この時期の学びを『より活かす』ために
・どんな時に納得した表情を見せる?
→考えた末に閃いた時?先生に質問した時?目の前の子の『理解の深まりを感じる瞬間』を見極めると学びサポートがしやすくなる
・塾を「どんな学習スタイルが合っているか?」を見つける機会として活かす
→授業を聞くだけより、グループワークが好き?/自分で調べる事が楽しい?(←探求型の学習があっている?でもそうとも限らないから、まだまだ要観察!)
・公文のような反復学習の機会を『どんな時に手が止まる?』を見つける機会として活かしてみる
例)すぐ終わらせたがる? → 単調な作業になってしまっているかも?
どんな時にミスが増える? →集中力が続かなくなるポイントが見えてくるかも!
途中で考え込んでいる? → もっと深く理解したい気持ちがあるかも?!

幼児教室は必要?公文のような反復学習は逆効果?…と迷う事は自然なこと^^
学びの場を選ぶ時に大切なのは、「どの方法が正解か?」ではなく、「子どもにとってどう活かせるか?」を考えること。
先ずは、「今のこどもがどんな学び方をしているか?」を観察してみてください^^
・どんな時に楽しそう?
・どんな場面で手が止まる?
・どんなふうに考えている?
『学びの場』は、合う・合わないがあるものの、活かし方次第でプラスになるものです。
→ 「なぜ?」を考える機会を増やし、自由に試行錯誤できる環境を整えることが大切。
・もし「基礎力をしっかり固めたいなら…」
→ 公文のような反復学習が、型にはまることが安心できる子には向いていることも。
・もし「集団の中で刺激を受けながら学ばせたいなら…」
→ 幼児教室や塾の環境が、その子の成長にプラスに働くことも。
大切なのは、「この学び方を選ぶと、どんな力が育つのか?」を意識しながら、その子に合った学びを見つけていくこと。
学びの選択肢は、ツールとしてどう活かすかが大切です。
例えば、『おうち英語』に取り組んでいるおうちならば、「英語環境はどう活かすか?」も学びの選択にも関わってきますよね。
それぞれの子どもの発達段階や個性を見極めながら、その子にとって『学びの楽しさ』を感じられる環境を整えていくことが、結果的に自走力に繋がっていきますからね!
私もキッズのコーチングでその辺りを大切にしながら関わらせていただいています^^
もしお子さんの『ここ!』が「これで良いのかな?」などとなられた場合は、こちらでそのサポートをさせていただいています^^