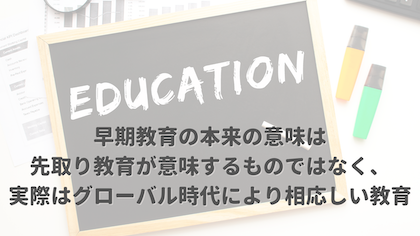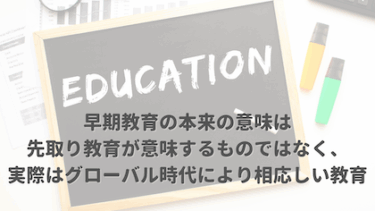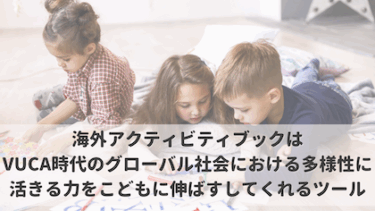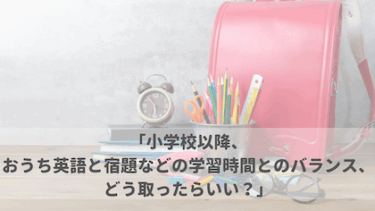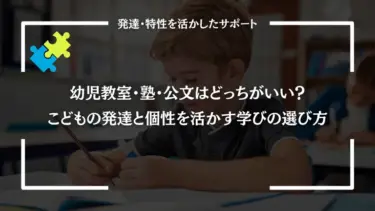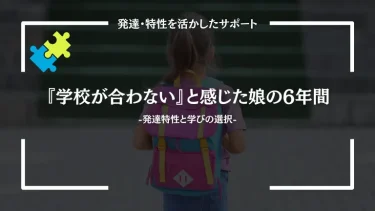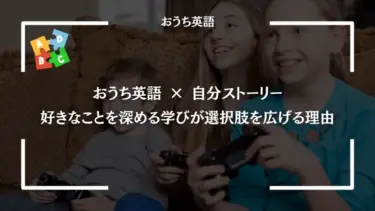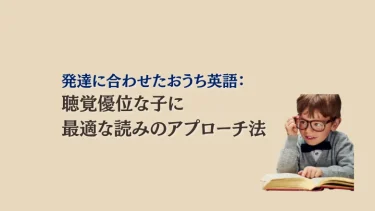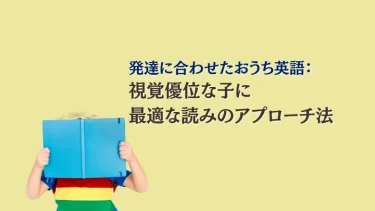こどもの発達と個性を活かすからできる!グローバル力も育つバイリンガル子育て、林智代乃です。
先日、
例えば、〇〇式などのプリント学習など。
就学前に先取りで学習することです。
といったご質問を頂きました。

…という事で、今回は
について私の考えを書いてみようと思います。
※私の思う【早期教育】については、動画を通してもお伝えしておりますので、「動画から見ちゃった方が早い!」という方はこちらからご覧頂けます>>>
【早期教育】の本当の意味を理解する
【早期教育】について考えていく際に大事な事は、その良し悪しではなく、
にあると考えています。
今、「早期教育って、どんなイメージですか?」と投げかけたとしたら、きっと多くの方が『早期教育=先取り教育』と考えられ、そのイメージを答えられるのではないかと思います。

実際、「早期教育の成功例」として挙げられるものは、幼児期で漢字が書けたり、かけ算・割り算の計算ができたりしている様子だったりすると思うんです。
ですが実際、【早期教育】が本来持つ意味は、それとは少し違うもの。
【早期教育】が本来持つ意味は、
(こども自身が持つ、自分自身で成長しようとする力を引き出していく)
というところにあります。
この『こどもの中にあるもの』というのは、
・想像力
・創造力
などといったもの。

上記にあるこれらのこどもの中にある力を引き出し伸ばしていく事を本来の早期教育は意味しているのです。
実際、『教育』を意味する英語の「education」の語源は『引き出す』を意味する「educe」からきているものですから、
なのです。

いわゆる早期教育(先取り教育)が
頭の良い子を作るわけではない
いわゆる早期教育としての成功例では、『どんどん先へ先へ進める子は頭が良い/賢い』とされるような傾向にあると思います。
ですがこれ、ちょっと違うんですね。
確かに先へ先へいける賢さを持ったお子さんはいますが、ただここで大事な事は、
という事。
これに関しては2013年にニューヨーク大学が行ったおよそ8件の論文を解析したメタ分析で言われています。
例えば、たくさんのマルが描かれた紙を2人のこどもに渡すとします。
1人の子はいわゆる先取り教育という早期教育を受けていない子、そしてもう1人はいわゆる先取り教育という早期教育で学び進めていっている子。
各々に紙に描かれているマルの数を当ててもらうとします。

先取り教育的な早期教育を受けてきていない子は、
↓
1つずつ数えると数え間違いが起きることに気付く
↓
数えたものにはバツ印などのチェックを付け、数え間違いがないようにしてみる
↓
それでも混乱してくるなと思った時、数えやすいように区切ったりマルで囲んだりしながら
囲んだマルの数を数える
↓
10のかたまりが何個なのか足し算して求める
などのステップを踏んでいったりします。
一方、先取り教育的な早期教育を受けて来た子は、
↓
10の塊がいくつなのか数えて、かけ算して答えを出す
といったステップを踏んだりするでしょう。

こう見ていった時、素早く答えに辿り着く後者の『先取り教育的な早期教育をしてきた子』の方が賢く見えるかもしれません。
ですが、実際に賢い子に近づいていくのは、
なんですよね。
先に進めるという事は難しいものに向き合っているという事でもありますが、先へ進むからこそ簡単な解法を知る事でもあるので、色々と思考する時間が短くもなりやすいのです。

実際、小学校受験・中学校受験そして大学受験で求められるのは、
という『思考する力』を図られているような場面が多いですよね。
ここで求められている事は、「正しく答えられる」よりは実際、「どれだけ工夫して解けるのか」という思考部分ですよね。
この『思考時間』が、いわゆる『賢い子』を作っていく時間となるのです。
早期教育として大事な事は
『課題は自分で作り自分で展開していくという事』
先取り教育と言われる早期教育での多くは『学習的なアプローチ』をしていくものだと思います。
この『学習的なアプローチ』で共通するものは、
という事。

学習的なアプローチに向かっていく際、こどもたちは
『限られた範囲での思考』
なんですよね。
ですが、【早期教育】の本来の意味を踏まえていった時、こどもたちに過ごして欲しい時間は
何通りものゴールに向かって自分で展開していく
という事。
要はこどもに『課題発見する力』『問いを立てる力』を育んでいく事の方が、大事という事なですよね。
ここの部分に関しては正直、『学習的なアプローチ』になりがちな先取り教育を意味する早期教育をメインしたした関わりの子育てでは得難い時間だったりします。
本当の意味での【早期教育】は、
こどもがどんどん展開していく事で成り立つ
このように、『課題は自分で作り、何通りものスタートから何通りものゴールに向かって自分で展開していく事』が早期教育で大切な事。
故に、こどもたちにとって大切な時間は、
・『好き』『興味』から
広がっていく時間です。

故に、我が子に対してもそしてキッズコーチングでご一緒させて頂いているお子さんたちとの関わりの時間でも大切にしている事は、
興味関心や好きを通して遊びながら物事を展開させていき
そこでの会話を通してこどもからの『もっと!』や『こうなりたい!』などの目標を引き出し
こども自らが色々と学び等を展開していく形
です。
もちろん、おうちの方へのサポートの際にも、その関わり方についてサポートをさせて頂いています。
因みに先に挙げさせて頂きましたニューヨーク大学のメタ分析では『人と関わる時間が最も人を賢くする』と発表しており、こどもと会話をしながら展開していくって実際賢さにも効果があるのです^^
…という事で、我が子そして関わらせて頂いているお子さんたちには『早期教育』を提供していますが、私の提供している早期教育は本来の『早期教育』が意味する『こどもから引き出す』ものという感じです。

先取り教育ではなく先取っちゃった教育は
早期教育
このようにこどもの好きや興味関心や遊びから引き出し展開していく時間は、どんどん学びが深まっていく時間でもあります。
そうすると段々とそこから広がった学びが、気づいたら先取り教育かのように、今の年齢を超えた学びになっている事もあったりすると思います。
例えば、我が子。
今小学2年生ですが、下記のワークブックが割と好きです。
グレード5のワークブックですが、「この学びをしよう!」「これをどんどん解いていこう!」としてこのワークを与え触れているのではなく、下記のブログ記事で書いた遊びから広がって辿り着いたもの。
興味や遊びから広がっていった先に辿り着いた学び故、このグレード5のワークブックは該当箇所しか取り組んでおらず穴あきだらけです^^
ただ本当に『遊び』や『興味関心』に付き合っていったら、展開された先がたまたまそこだったので『気づいたら先取っちゃっていた教育』だったという感じですね。
こんな感じに『先取り教育』と『気づいたら先取っちゃってた教育』は違うもので、後者は『自ら課題を見つけ展開していった先に辿り着いた学び』なのです。
このように
こども各々に展開の仕方があり
その時間を通してその子の持っている力を育んでいく本来の意味での『早期教育』の時間は、
まさにこれからの【個性】を活かしていくグローバル時代にはとても大切な時間
なんですよね。
…という事で、『早期教育』についての私の考えは、【早期教育】の本来の意味を考え付き合っていく事が大切という感じです^^