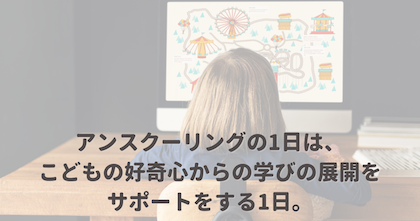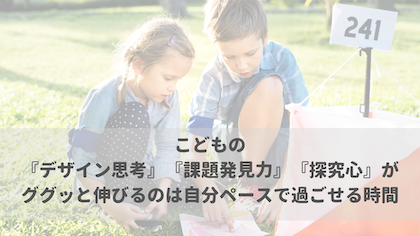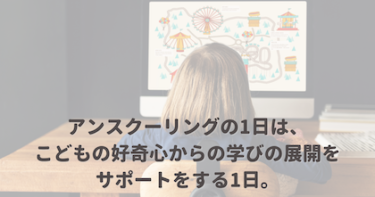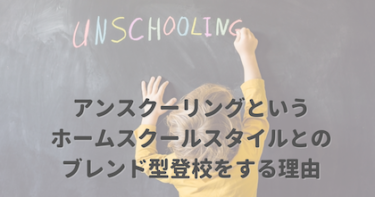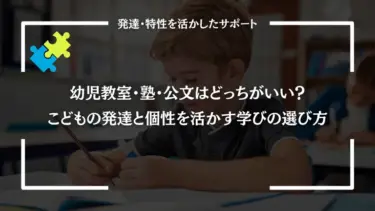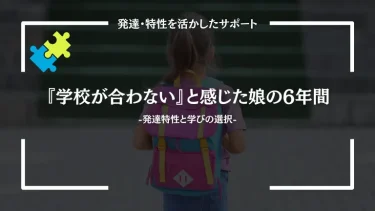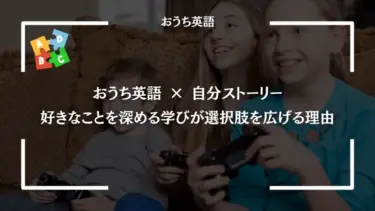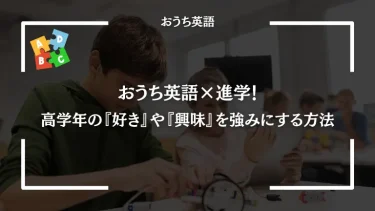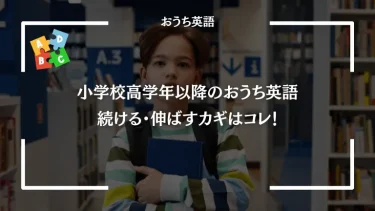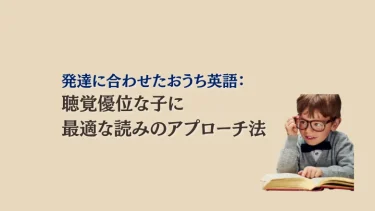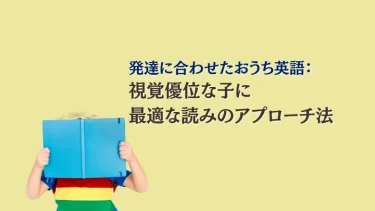こどもの発達と個性を活かしバイリンガルを育てるグローバル子育て、林智代乃です。
先日、我が家の娘の学校との付き合い方である【アンスクーリングというスクーリングスタイルとのブレンド型登校】について書きました。
こどもの発達と個性を活かしバイリンガルを育てるグローバル子育て、林智代乃です。 以前、当の本人たちは『不登校』という概念…
なかなか聞かないスタイルという事もあってか、多くの方に興味を示して頂いた記事となりました。
今回は、そこでよく頂く
どう関わったら良いのか分からなくて。
などと言ったお声。
今回はその辺りに触れてみたいと思います^^
アンスクーリングスタイルだからこどもが日々をデザイン
上記でシェアをさせて頂きましたブログ記事でも触れていますが、我が家のスタイルは『こどもが日々をデザインするアンスクーリングスタイル』。
アンスクーリングとは『教育をしない』ということではなく、大人が決まった学びを提供したりするのではなく、こども自身が興味関心から自発的に学びを展開していくスタイルで、おうちの人がするとすればそこへのサポートというスタイルです。
故に
です。
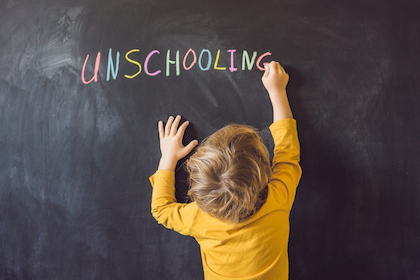
「これをしなくちゃいけない」「今日はこれをしよう!」などがないスタイルがアンスクーリング。
『いつ・何を・どれだけ学ぶのか』は学びの主人公であるこども以外の人が作るものではないという考えがアンスクーリングなので、正直、その日その日どんな1日になっていくのかは親も時にこどもも分からないという日々です。
…と日々のシナリオはこども自身が決めデザインしていくのですが、いつもいつも所謂『学び』的なものに繋がっている訳でもありません。
『遊び通した!』という日もあれば、『何もしなかった!』という日も全然あります^^
アンスクーリング中
親がしている事といえば、ただこどもへの『質問』だけ
『アンスクーリングをしている』という話になると「私には、こどもの興味関心から展開していく事は難しい…」と伝えて頂く事があります。
確かに『こどもの興味関心から学びを展開していく』と聞くと、おうちの人は大層な役割を担う事になりそうな響きですよね^^;
ですが、アンスクーリングでは実際『展開をしていく』のは『こども』。
私がしている事はこどもが示した興味関心に『もっと!』が生まれるような質問や言葉を掛けるという事をしている感じです。

質問と言っても、
・「もっとこうしたい!とか何か『もっと!』となるものはある?」と、こどもの中の『もっと』となるものを探る
・こどもが聞かせてくれる考えや取り組んでいるもの等に対して、『どうしたらいいかな?』『どうしようか?』とこどもが考え始めるような質問を投げかける
といった感じ。
因みに上記のスタイルはキッズのコーチングでも取り入れているスタイル。
ご一緒させて頂いている方は「あのいつもの感じね!」とイメージ付きやすいかも知れませんね^^
例えばこの前だったら、ビニール袋を飛ばし空中での持続時間を長くさせようと遊んでいたので、
娘;「もっと下から風がブワーっと吹き続けてれば長くなるんだよねー。」
私;「下から風がブワーっとね。じゃあ、下から風がブワーっと吹き続けるようにしてみたら?」
娘;「だからやっているんだけど、落ちてきちゃうんだよー。」
私;「やってるけど落ちてきちゃうんだ?じゃあ『もっと』ブワーっと吹き続けさせられるものないかねぇー。」
娘;「あるよ!扇風機!扇風機使っていい?」
私;「いいよ!」
…しばらく放っておいて…
私;「どう?」
娘;「扇風機の位置もいい感じにしたんだけれど、ずっと受けてられないんだよねー。」
私;「じゃあ、どうしたら『もっと』風を受けられそう?逆に何が『もっと』の邪魔になってる感じ?」
娘;「あ!それもいいけれど、飛ばすよりもファンとか風の動きが気になり始めてきた!」
私;「あ、そっちにいくのね(苦笑) いいんじゃない?『もっと!』知りたいってなったところはどんなところ?」
…という感じに会話が広がっていったりとそんな感じです。

『学びは気付き』
『こどもがシナリオを書いて初めて探究活動』
その後は、興味が移ったファンの動きの方に『もっと!』を向けていた娘。
取り組んでいる事は幼児さん的な感じもありますが、『今の年齢だから』こその思考の展開であったり深さもあったりして、それはそれで良いな…と感じています。
何よりも『思考する時間が過ごせている』というところでもう花丸です。笑
先にも書いている部分になりますが、
『思考』するから『気付き』が生まれ、その時間こそが『学び』の時間になる。
それは知識を覚えるように得るよりも大切な時間。
探究心は好奇心からの『もっと!』で生まれるものだからこそ、こどもの『もっと!』を刺激するような質問や言葉を掛けるだけでいい
そう考えています。
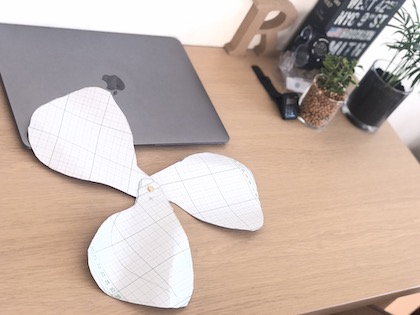
これは学校に行っていない『アンスクーリング』の時間に限らず、普段のこどもとのどんな時間においても言える事。
以前、下記のブログ記事でも書いた事がありますが、今よく見聞きする『探究活動』の実際はそういうところにあります。
こどもの発達と個性を活かしバイリンガルを育てるグローバル子育て、林智代乃です。 夏休みこそ ・自分で決め ・自分でデザイ…
その為、よくある『探究活動』とされるイベントものの多くは『実際はそれ自体が探究活動なのではなく、それが探究活動の入り口となる存在』なんですよね。
なぜならば
から。
これはよく『ミュージカル映画』を例に私は出してしまうのですが、例えばその『ミュージカル映画』で見ていくとすると…

同じミュージカル映画を見ても
・劇中の踊りに興味を持ち、そこに『もっと!』を抱く子
・劇中に出てくる演者に興味を持ち、そこに『もっと!』を抱く子
・劇のシナリオ構成に興味を持ち、そこに『もっと!』を抱く子
・劇中の演出の仕方に興味を持ち、そこに『もっと!』を抱く子
と様々いるはずです。
でも多くの大人は『ミュージカル映画=歌か踊り』と見立ててシナリオを立てていってしまうようなところがある訳です。
そうなると、演者やシナリオ構成そして演出に興味を持った子は、そこで提示されるものを楽しみつつも自分の中の『もっと!』は満たせていない事になるんですよね。
だからこそ『こどもに質問をする』って大事なのです。
ワーキングマザーのアンスクーリングのリアル。
とはいえ!
私も日中はお仕事をしているので、常につきっきりでしっかりサポートが出来ている訳ではないです。

『アンスクーリング』は『放置する』を意味するものではないですが、やや放置気味になる事はあります。
ありますが、小さな時から彼女の興味関心から展開させていく『アンスクーリング』に似たスタイルで関わってきている事もあり、それだったらそれで『自分で学びを展開させる』事をしていたりします。
何よりも『もっと!』を刺激するような質問の回を重ねていく事で、こどもの中で『もっと!』の思考が自然と育まれていくので、最初はつきっきり感があったとしても段々と距離感とって関われるようになっていくはずです。
もちろん、お手伝いが必要な場面とかは出てきますけれどね。
ま、我が家においてはただゴロゴロしている日も全然ありますが。笑
でも『ゴロゴロする』という『ぼーっとする時間』という時間は1番『閃き力』を育てていってくれる時間なので、『次のフェーズにいく為に必要な休息』と捉えています。
(「都合がいい」と言ってしまえばそれまでですが。笑)
『教える』というスタイルから『学ぶ意欲』は育めないのか
我が家が様々あるスクーリングスタイルの中でも『アンスクーリング』(とのブレンド型登校)というスタイルを取る理由は先に書いている内容からもイメージが付くかと思いますが、
と考えているから。
実際、以前のブログ記事にも書いていますが学校を休みがちになる理由は本人の『学びたい!』という意欲と学校が前提とする学びスタイルが合わないというところからなんですよね。
とはいえ、ここに対して、
と感じられる事もあるかも知れません^^

それによって育てられるものも勿論あると思いますが、私はやっぱり
と考えていて、『気付かされる』時間よりもこどもが能動的に行動して『気付いた』時間をなるべく作っていく事が大切だと考えています。
「こどもの興味関心軸で進めるアンスクーリングで、遅れはでないの?」
『アンスクーリング』というスタイルは、こどもの興味関心から広げられるスタイルだからこそ時に学年の履修範囲を超える事もあれば、学年の履修範囲に触れず…の時も出てきます。
そうなると多くのおうちの方が気になられるのは
という部分。
娘の場合は、学校にも行く『ブレンド型登校』なので「学校に行った時に遅れが出て困る事はないの?」と気になられる事もあると思います。

今はまだ3年生という事も相まって、そこまで『遅れが出た!』という事はないですが、今後そういった部分ももしかしたら出てくるかも知れません。
ただ私は、その『遅れ』を感じる基準がただ『学校のカリキュラムラインの話なだけ』という外軸の話なだけで『その子に合ったラインとは限らない』と考えているので、仮に遅れが出たとしても仕方がないと考えています。
仮に学校の学びに遅れが出た時、そこで大切な事は学校の学びに付いていけるか否かよりも
な部分だと思っています。

言い換えると、
だなぁ…と。
『アンスクーリング』はこの『学びに対する意欲』を育む時間だからこそ、もしこどもが学校に行った際に『遅れが出たから学びたくない!』と思ったとしたら、その時は『アンスクーリングになっていたのか?』と自問自答する時なのかも知れません。
もちろん、一瞬は「えー!知らない事やってる!みんな知っているのに嫌だなぁ…」とは思うかも知れませんが、その後どう行動に起こすのか…なところなんですよね。
…と、『アンスクーリングではどんな風に過ごしているのか』の部分を書いていくつもりが得意のちょっと(…どころじゃない)脱線になってしまった感がありますが、私が捉えている『アンスクーリング』とそこでの日々の向き合い方について書いてみました。