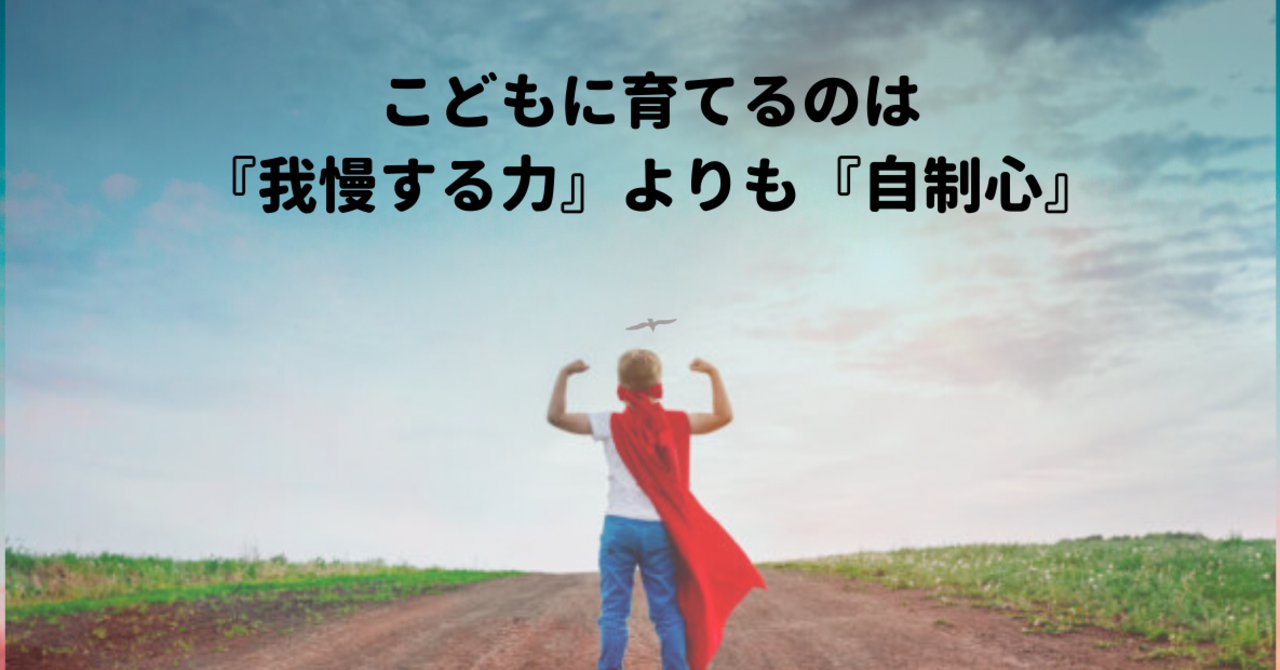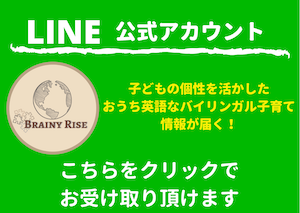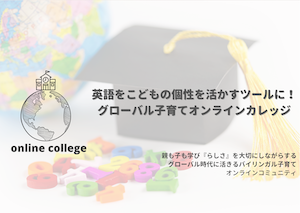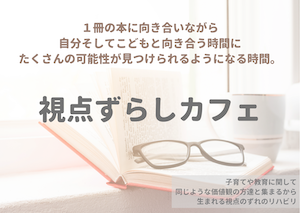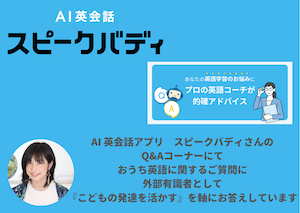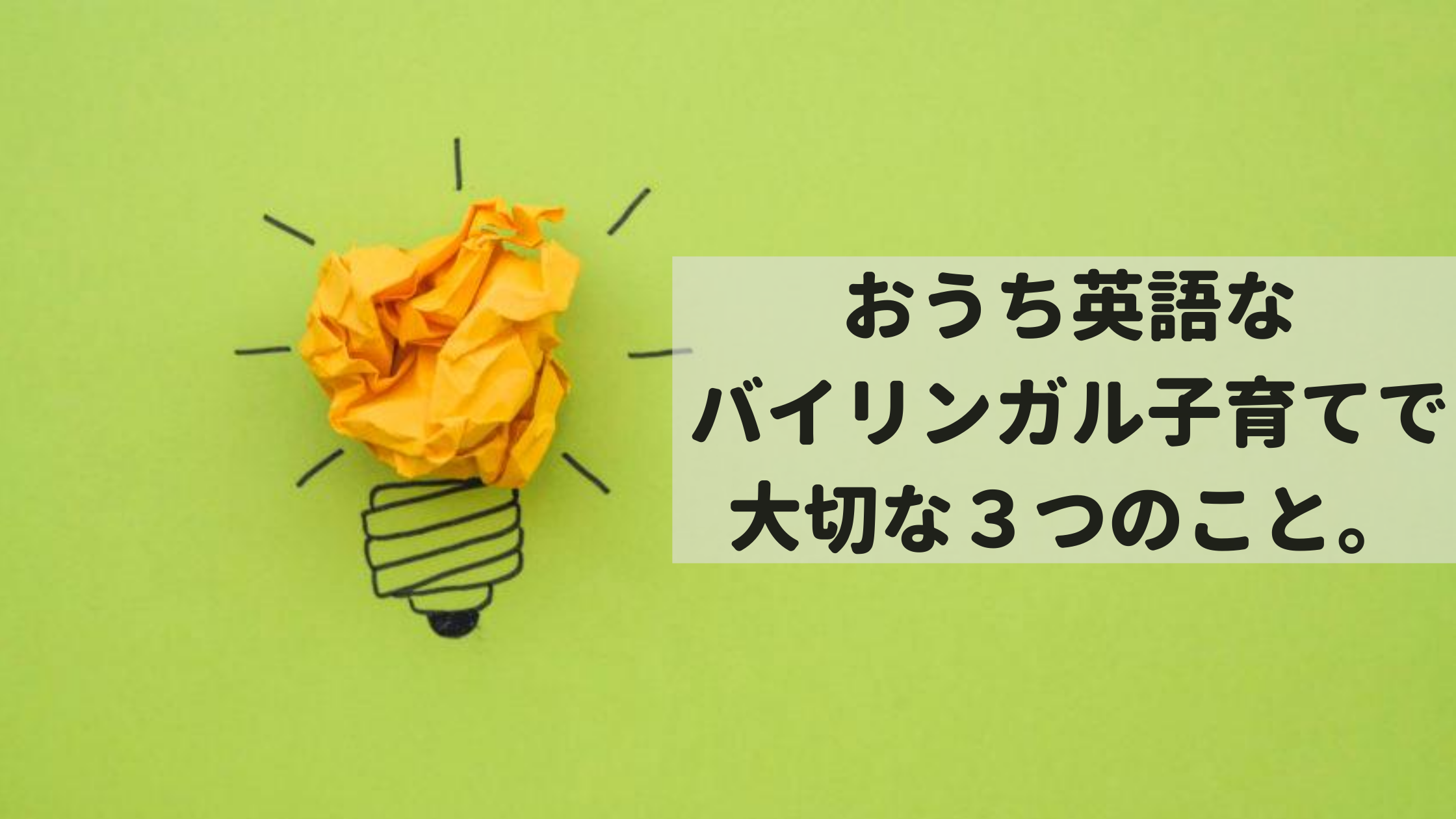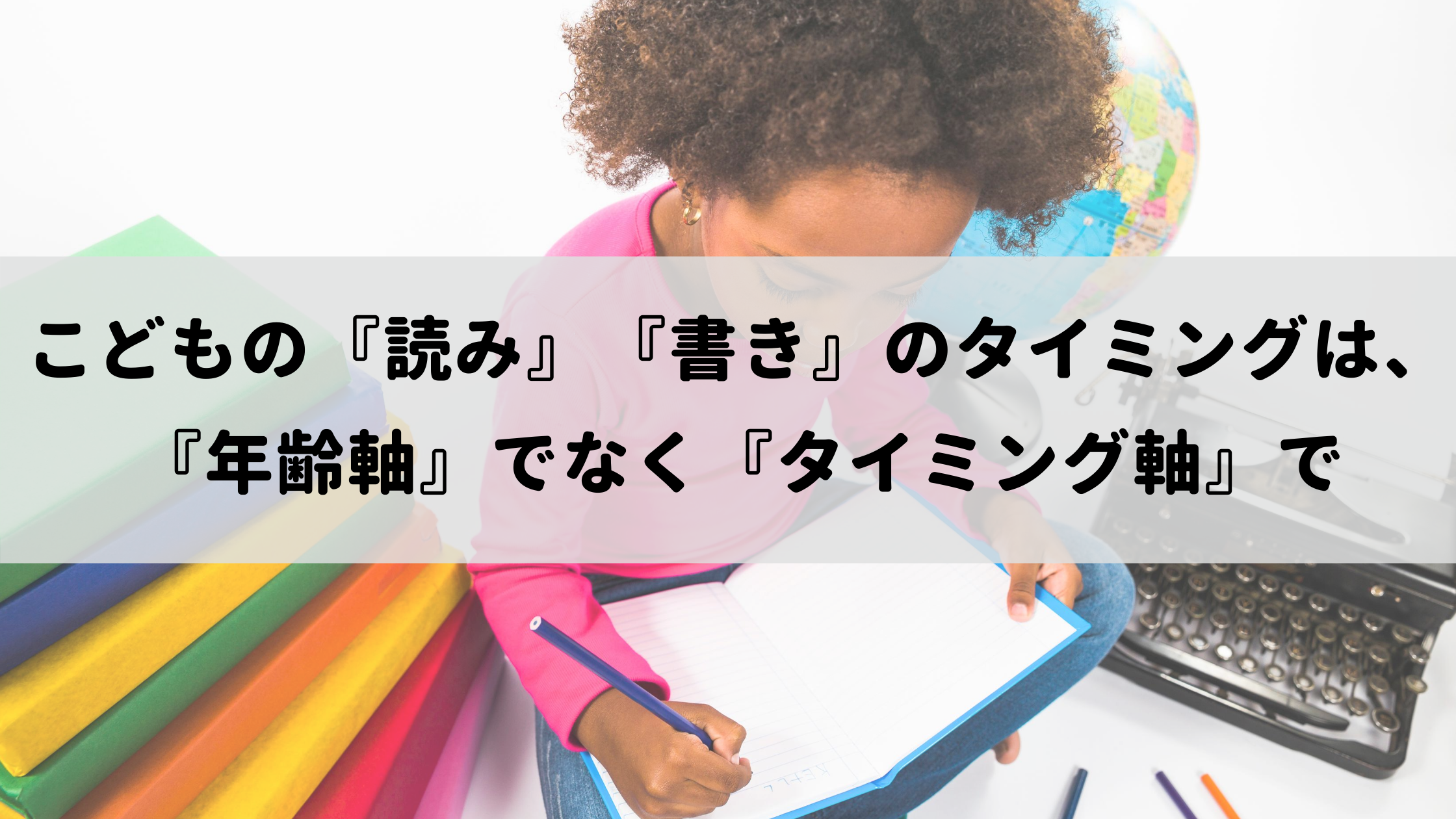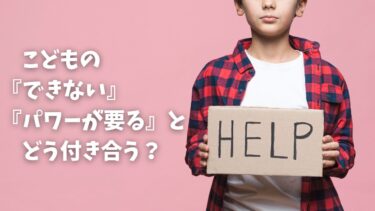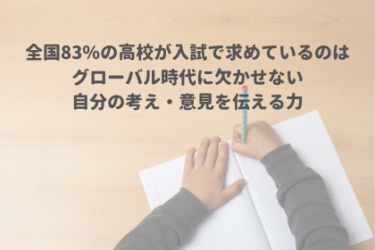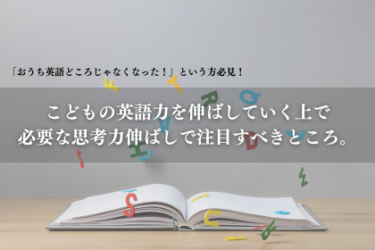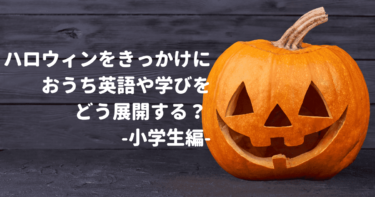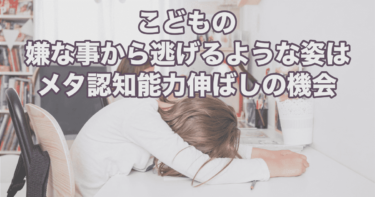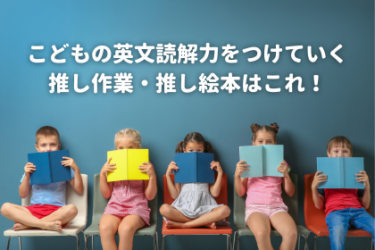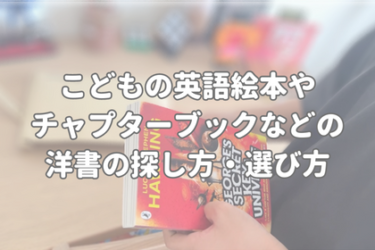先日、
忍耐、我慢を伝える、教えるタイミングや伝え方についてアドバイスをお聞きしたいです。
堪え忍ぶことに美徳を感じるのは日本人ならではかもしれませんが、確かに我慢が必要なときもあると思うのです。
今はイヤイヤが出たときに、なるべくポジティブな声かけを心がけているのですが、そうするとなかなか我慢を伝えるタイミングがないことに最近気付き、悩んでいます。
堪え忍ぶことに美徳を感じるのは日本人ならではかもしれませんが、確かに我慢が必要なときもあると思うのです。
今はイヤイヤが出たときに、なるべくポジティブな声かけを心がけているのですが、そうするとなかなか我慢を伝えるタイミングがないことに最近気付き、悩んでいます。
といったご相談を頂きました。

…という事で、今日は『我慢』について書いてみたいと思います。
『英語』ができる事だけがグローバル力を持ったバイリンガルではなく、グローバル時代に活きる人間力を持ったバイリンガルがこれからの時代に求められる『バイリンガル像』ですからね。
こういった人間力伸ばしに関することはとっても大事です^^
目次
こどもに本当に付けていって欲しいのは、
『我慢』なのか。
こどもに育てていきたい力って、『我慢する力』ではなく『自制心』と考えています。
『我慢』と『自制』。
この2つは似ているようで、実は違う意味。
この部分を改めて見てみると、『我が子に育てたい力』と『その関わり方』がみえてくるように思います^^

【我慢】
→耐え忍ぶこと。こらえること。辛抱。(広辞苑)
【自制】
→自分の感情や欲望を抑えること (広辞苑)
→耐え忍ぶこと。こらえること。辛抱。(広辞苑)
【自制】
→自分の感情や欲望を抑えること (広辞苑)
と記されていますね。

【我慢】
→「辛さ」が前提にある。
「本当はこうしたい!」という自分の言動を押さえ込んでいる状態。
現状で停滞しているようなイメージ。
辛さ前提なので、その先にあるゴールを見れていない。
(ゴールは『我慢を乗り越える』という部分だけ)
故にその行動に対して意味を見いだせていない状態
【自制】
→自分の感情等をコントロールする先には、相手など自分以外の人等が向こう側にいる。
故に先を見越して行動した上に成り立つもの。
自分の向こう側にある対象に対しての『理解』から生まれるもの。
『良い結果』を得ることを考えて、自然と言動をコントロールしている。
→「辛さ」が前提にある。
「本当はこうしたい!」という自分の言動を押さえ込んでいる状態。
現状で停滞しているようなイメージ。
辛さ前提なので、その先にあるゴールを見れていない。
(ゴールは『我慢を乗り越える』という部分だけ)
故にその行動に対して意味を見いだせていない状態
【自制】
→自分の感情等をコントロールする先には、相手など自分以外の人等が向こう側にいる。
故に先を見越して行動した上に成り立つもの。
自分の向こう側にある対象に対しての『理解』から生まれるもの。
『良い結果』を得ることを考えて、自然と言動をコントロールしている。
といった意味に捉えています。
『我慢』と『自制』の違いから見えてくるもの
グローバル時代に活きるバイリンガル子育てとして私はこどもに、「どうしたら良いのか」などの『自分で(主体的に)考え、判断し、責任を持って行動する』主体性を持って育っていって欲しいと思っています。
この『主体性』を育む通過点として求められるものは、「我慢」と「自制」の意味の違いから『自制』だと感じています。

これにより『ストップの言動や感情』がこどもから生まれてくるようになったり…と育っていくものがあるのです。
そこで大切なのは、上記ブログ記事にも書いていますが、『会話』なんですよね。
会話をする事で、自分の考えや思いを伝え、そして相手等の気持ちも聞き理解をしていく。
この『会話』というプロセスを踏みながら「我慢」ではなく、納得からの「自制」を通して『ストップ』の心を育んでいって欲しいと思います。
そして、そういった時間を積んでいく事がひいては『自己対話』をする力にも繋がっていき、自制心がどんどん育まれていくという訳です。
グローバル時代に活きるバイリンガルに求められる
『リーダーシップ力』
今、『リーダーシップ教育』という教育があるほどに、これからの時代には「リーダーシップ力」が求められています。
この『リーダーシップ力』って、「俺についてこい!」みたいに引っ張っていく力ではなく、
・物事を主体的に考えられる力
・協調性
・各々の人の特長を活かす力
(みんなが各々の角度からみたらリーダーにできるような人)
・各々の人を見る力に必要な「共感力」
・コミュニケーション力
(コミュニケーションを図る事で各々を知る)
・決断力
(決断をする上で必要なのは「(自分の中での)納得」)
・協調性
・各々の人の特長を活かす力
(みんなが各々の角度からみたらリーダーにできるような人)
・各々の人を見る力に必要な「共感力」
・コミュニケーション力
(コミュニケーションを図る事で各々を知る)
・決断力
(決断をする上で必要なのは「(自分の中での)納得」)
といった力。

まさに『自制心』に繋がる部分が必要となっていくのです。
先にも書きましたが、『色々な角度からみると、みんながリーダー』となるように各々が活躍していける事が求められていきます。
これ、こちらのブログ記事でよくお伝えしています『個性を活かす』という事ですね。

そういった社会の中で活きるバイリンガルはただ英語ができる人ではなく、各々の特長を活かせる人ですからね。
そういった意味でも、バイリンガル子育てを通して育んでいきたいのは『リーダーシップ力』なのです。
そう、『各々の個性を活かす』事が大切だからこそ、「我慢」していたら個性は活かしきれない訳です。
こどもに育てるは『我慢する力』ではなく『自制心』
このような考え方から、
こどもに育てるは『我慢する力』ではなく『自制心』
と考えています。
自制心を育てていった先に「ストップをする心」が育っていくという感じです。
この「ストップ」は我慢と似ているようで違う。
そこが注目ポイントかなぁ…と。

益々加速していくグローバル時代において必要な力や育てていきたいものとの向き合い方等については、こちらのオンラインサロン『英語をこどもの個性を活かすツールに!グローバル子育てオンラインカレッジ』にて、お伝えしています>>>