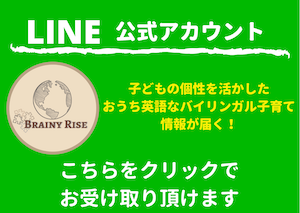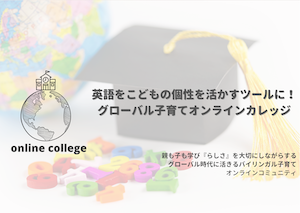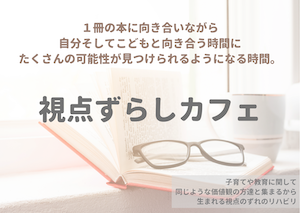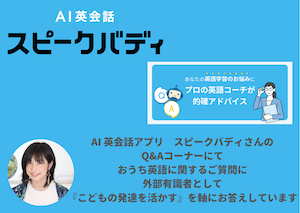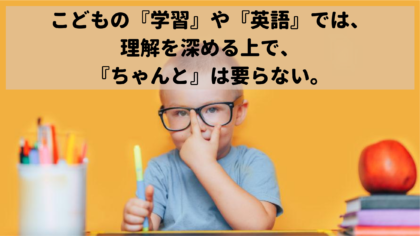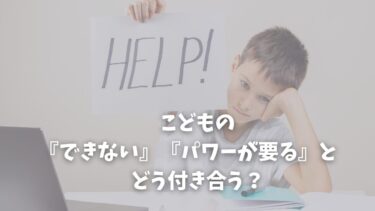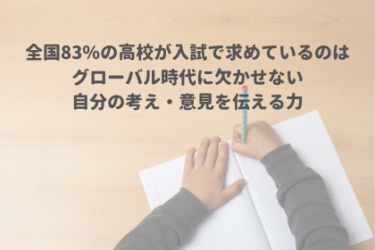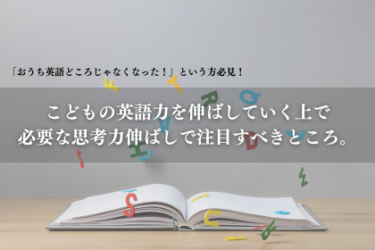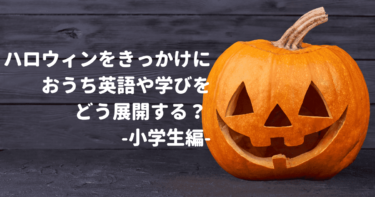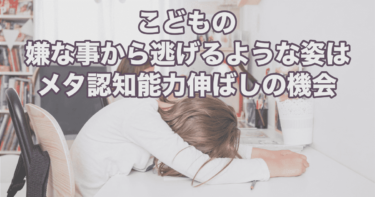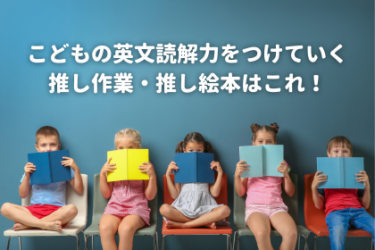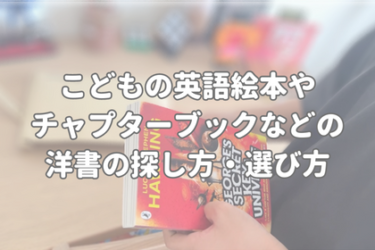英語学習ツールの1つとしても大人の方達に人気のある、
The Japan Times Alpha
さんの記事にて、先日取材して頂いた記事が掲載されています^^
6月5日発売の6月12日号での掲載です。

・なぜ今の活動をしているのか
・今の活動の根っことなる体験は何なのか
・こどもの英語習得において大切な事は何なのか
(オンライン版のロングバージョンにて掲載)
・今の活動の根っことなる体験は何なのか
・こどもの英語習得において大切な事は何なのか
(オンライン版のロングバージョンにて掲載)
について書いて下さっています。
オンライン版の記事はこちらとなります>>>

正しさを求めすぎて、
段々と英語ができなくなっていった過去
The Japan Times Alphaさんの記事にてもお伝えさせて頂いていますが、『大好きだった英語(英会話)が段々、苦手になり出来なくなっていった』という過去があります。

映画 “Back To The Future” がリアルタイムで話題になった世代なのですが、幼稚園時代にその映画のテレビ放映を見て、その世界に憧れたのが私にとっての最初のスタートでした。
…といっても、当時はもちろん日本語で観たんですけれどね!

当時としては割と珍しく、海外教材を使って文法をする事もありましたが、『お勉強』という感じでは全くなく、本当に『楽しむ』形。
その後、『授業としての英語』に中学校になってから入ったのですが、ここでもラッキーな事に、毎授業『洋楽』を歌ってからの授業で、それが楽しくて、お勉強感はそこまでもたずに楽しめていたんです。

それが段々と「苦手」になっていったのは、
・段々と文法説明に複雑さが増し、イメージで掴むのではなく
正しく訳す…などが求められる文法授業に違和感を感じ苦手意識が生まれ
・英語が評価されるものへとよりなっていった事で、正しさを追うようになった
(「間違えたくない」ももの凄く強くなっていましたね。)
正しく訳す…などが求められる文法授業に違和感を感じ苦手意識が生まれ
・英語が評価されるものへとよりなっていった事で、正しさを追うようになった
(「間違えたくない」ももの凄く強くなっていましたね。)
がきっかけでした。
本当は『イメージで掴みながら楽しみたかった』だけだったので、「評価される」ものへと段々なっていった事で「正しさ」を追うようになり、英語に対して臆病になっていったのです。

そういった経験もあったからこそ、こどもへの英語を取り入れた子育てでは、
・正誤を追い求めるような取り組みを基本的にしない
・正誤を追い求めるような取り組みをすると『答えを覚えよう』とするようになる
・答えを覚えようとすると、記憶に刻まれる情報とならなくなる
・正誤を追うと間違いを恐れるようになる
・正誤を追い求めるような取り組みをすると『答えを覚えよう』とするようになる
・答えを覚えようとすると、記憶に刻まれる情報とならなくなる
・正誤を追うと間違いを恐れるようになる
ので、そういった部分を心に留めながら関わっています。
…と同時に、『好き』や『興味』が原動力になる事も知っているので、その部分も大切にするようにしている感じです^^
『発達』を意識して関わることは勿論大切なのですが、人間って本当にシンプルなので基本は同じなのです。
語る内容の違いから思考力の大切さを痛感
私が初めて留学をしたのは、社会人3年目の時でした。
『留学』と言っても、1ヶ月のみの滞在を3年間続けてした…というド短期のものですが^^;
留学は、
・1年目は、児童英語講師の資格を取得しに
・2年目は、オーストラリア現地幼稚園にて研修をしに
・3年目は、「語学学校に通ってみたい!」で語学学校へ通いに
・2年目は、オーストラリア現地幼稚園にて研修をしに
・3年目は、「語学学校に通ってみたい!」で語学学校へ通いに
行くような形でした。

「ステイ先」「現地でできたお友達」との会話に詰まることが多かったです。
「あなたの国はどう?」「あなたはどう考える?」などなど色々と聞かれる度に、
色々な事を知らないだけでなく、物事を様々な角度から考えたことがなかったし、聞かれて答えられる思考が自分にはなかった
というのが毎回悔しく、ショックでもあったんです。

20歳前後の子が多かったのに…、自分はその子たちと政治の話などをしても、適当な相槌しかできず全く意見交換にならない…。
これ、本当にショックと恥ずかしさでいっぱいでした。

本当に海外の人たちって、
ただ自分の意見を言えるのではなく、色々な視点で物事を語る力がある
んですよね。
映画のプロモーションでのインタビュー等をみていても分かりますよね。

『英語教育』って、英語を教育するのではなく、『英語ある教育』をする事だと思っています。
「英語ある教育」だからこそ、英語をどうこどもの成長に活かしていくのか。
実体験から尚更そこを大事にしている感じの私です^^