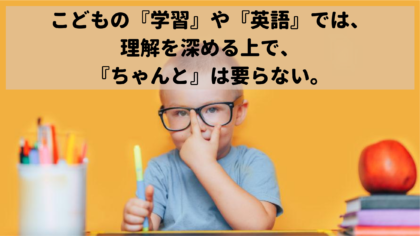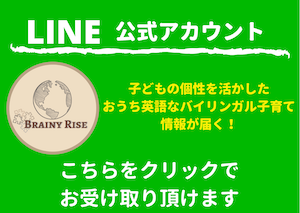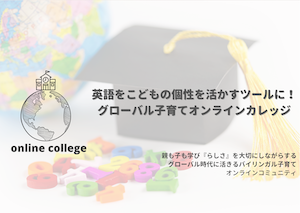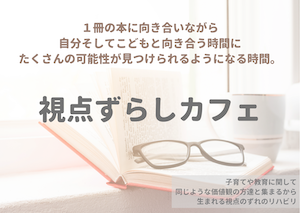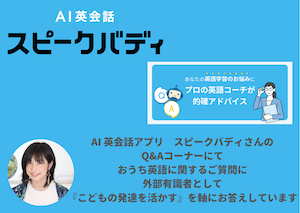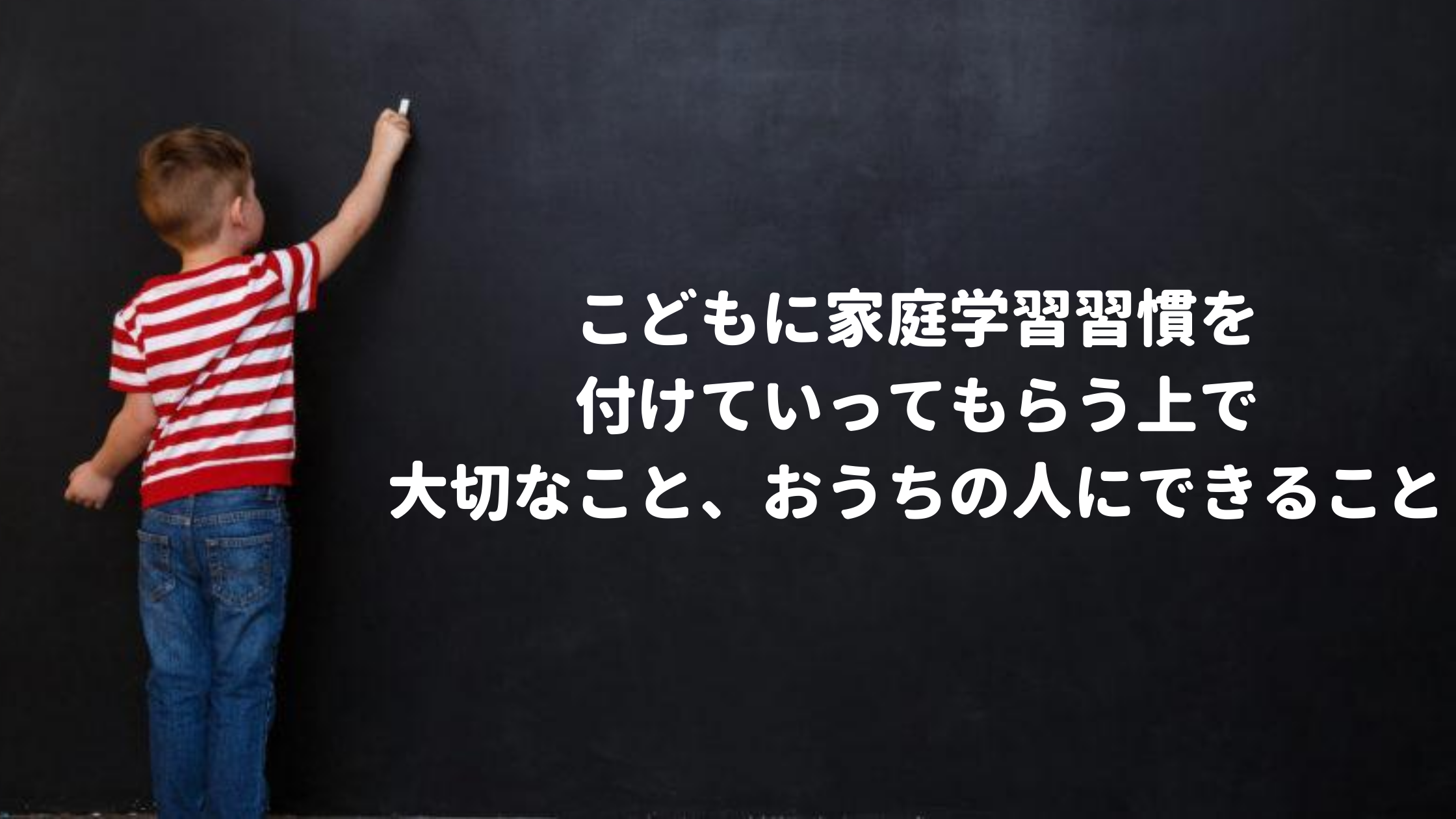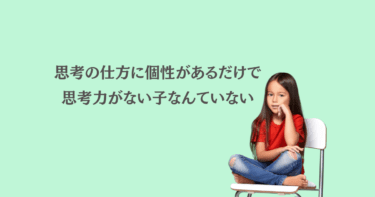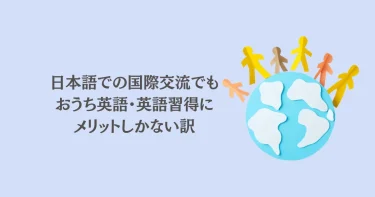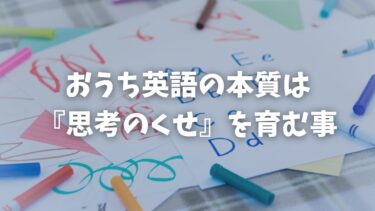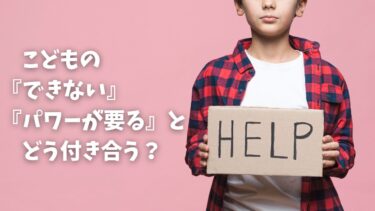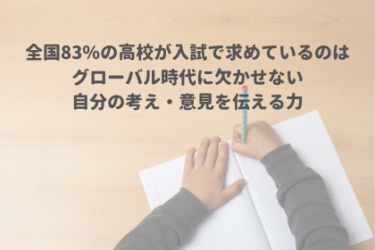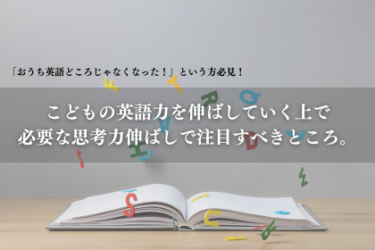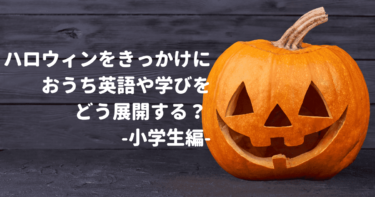物事に取り組む上で『理解』って、大事です。
大事ですが、
『理解の育て方』について知る事はもっと大事
だったりします。

目次
『理解』は都度するものではなく
後からついてくるもの。
よく、
あまり理解している様子がないのですが、これで良いのでしょうか?
どうこれから進めていったらいいのか、分からなくて…
どうこれから進めていったらいいのか、分からなくて…
といったご質問を頂きます^^
これに関してですが、
『理解』は都度求めるものではなく、色々と触れていった先に『後から付いてくるもの』が『本人の中に刻まれる理解』
となるものです。


この『理解』に関しての捉え方は『年齢』によっても少し変わっていきますので、こどもの年齢の発達に合わせた『理解』について書いていってみたいと思います^^
幼児期までは特に『理解を求めない』
これが大切!
『6歳くらいまでの幼児』は特に『理解を求める事はしない』時期です^^
というのも
『理解』を進めながら習得していく脳が7歳を迎えるあたりから育ち始めるので、その頃までの物事の習得の仕方は「なんとなくの積み重ね」を通して物事を身に付けていく
からですね。
イメージで捉え、経験等を積み重ねながら諸々の意味等を形どっていくように習得していきます。


理解を促すために1つのテーマに関して集中的に行うのではなく、色々な情報に触れていく事で溜まった情報を元に形づけていき習得していくスタイル
なのが幼児さんなのです^^
そのような習得の仕方をしていくので、特に幼児期のお子さんにとっては理解をしながら進めるってそもそも発達に合っていない訳です^^
7歳以上の子の『理解』は、
一方向からではなく多方向から
幼児期を脱する、7歳を迎える辺りからの理解に関してですが、この時期は、
『理解しながら進みたい』という脳が働き始めるので理解を求めながら進める事もポイントになってくるのですが、『いつも同じ角度からではなく、違った角度からのアプローチをする』事で理解が深まってくるようになる
時期です。


1つのテーマに関して色々な角度から触れていく事を集中的にしていきながら理解をしていき、それがしっかり刻み身に付けていく形となる
感じです。
例えば、算数の問題でも同じ角度からばかり聞いてくるような問題に触れていると、覚えるどころか脳が「飽きた」となり、受け付けなくなるのです。
よくある、『繰り返し同じような問題を解く』というのは、実はちょっと効率の悪いものであり、且つ「答え(方)を覚えよう」となり易く、『理解』とは違うものになりがちなのです。
7歳を迎えるあたりは、「理解」に関しても
こどもの『個性』『特性』で変わってくる。
因みに、7歳を迎える辺りになると、こどもの『個性』『特性』が見え始めてきます。
この時期は、こちらのブログでもよく書いています『学びの優位性』が出始めてくる時期ですね。
この優位性で理解の仕方を分けてみると、
・『視覚優位』
→全体を捉えてから理解したいタイプ(割と幼児期の理解ステップに似ている)
・『聴覚優位』
→細かく理解していきたいタイプ(7歳以降の理解ステップを好む)
→全体を捉えてから理解したいタイプ(割と幼児期の理解ステップに似ている)
・『聴覚優位』
→細かく理解していきたいタイプ(7歳以降の理解ステップを好む)
といった形になります。


各々のバランスが取りづらく、1つの優位性に偏りがちな子たちが、いわゆる『凸凹児』と表したり『発達障害』と表したりされる子たちですね。


英語も「理解していない様子」で進めてOK?
CTPなどの英語絵本教材をご利用されていらっしゃる方々から、よく
理解している様子がないのですが、次のレベルに進んでも良いのでしょうか?
といったご質問を頂く事があります。
上記までのお話で、『理解を都度しっかり求める必要はない』という事をお分かり頂けたと思いますが、英語もそうです^^
色々な絵本に触れていくから、しっかり『単語イメージ理解』がついてくるのです。
例えば、『have』という単語。
“have” には、
・持っている
・ある/いる
・食べる
・飼っている
・開催する
・経験する
…
・ある/いる
・食べる
・飼っている
・開催する
・経験する
…
などなど、たくさんの意味があります。


その単語が違った文脈で使われている英文にたくさん出会っていく事で、意味をイメージで捉えていく事が大切
なのです。
“have” の場合も意味を覚えようとするのではなく、『周りにモノや状態・状況などが存在する』といったイメージで捉えていくのがベスト。


たくさんの英文情報に触れる(インプットする)
↓
その経験を通して、その語のもつイメージを育てる
↓
その経験を通して、その語のもつイメージを育てる
をしていく事がポイント。
そこに「年齢ごとの理解の進め方」を参考にしてみるとより、効果的という訳です^^
そう、
・『理解』を気にしてばかりだと実はもったいない
・こどもの発達段階や特性によって関わり方は変わってくる
・こどもの発達段階や特性によって関わり方は変わってくる
という事です^^
『こどもを知る』って、とっても大切ですね。