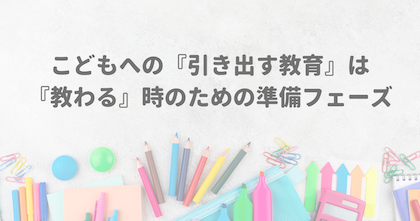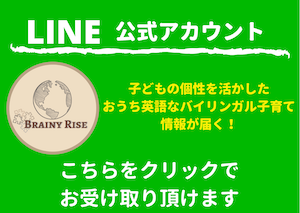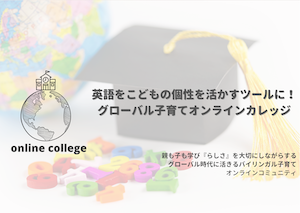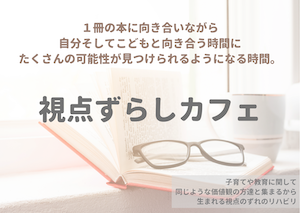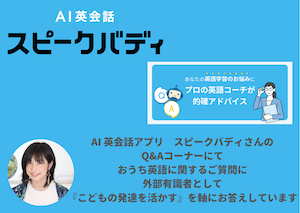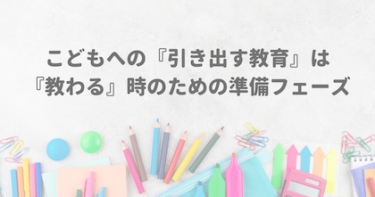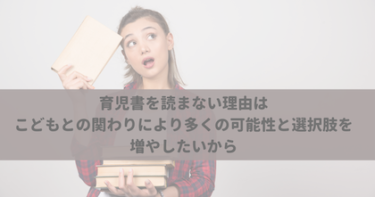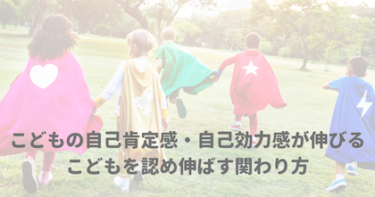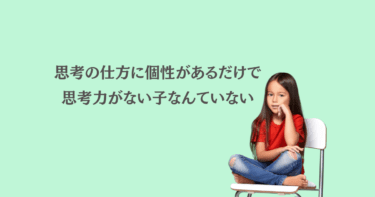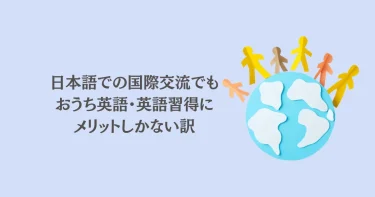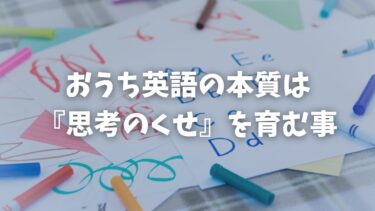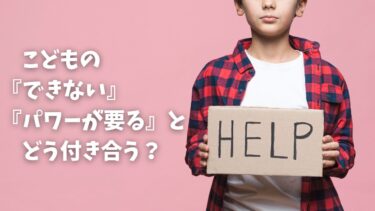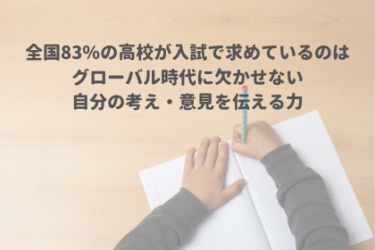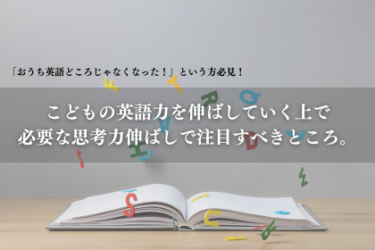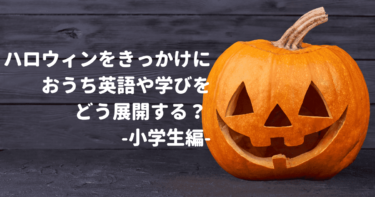こどもの発達と個性を活かしバイリンガルを育てるグローバル子育て、林智代乃です。
こちらのブログを通して、
という事をよくお伝えさせて頂いています。
『学習』的な事だけでなく『英語習得』においても『その子その子にあったアプローチ』があり、それだけでなく英語力というのは『英語以外の部分』の時間が伸ばしていってくれるもの。

その為、
なっていきます。
ただ、『与えるのではなく引き出す関わり』とお伝えさせて頂くと、
・『教える』をせずに知識の幅を増やしていく事は可能でしょうか?
といったご質問を頂く事があります。


…という事で今回はその辺りについて書いていこうと思います^^
こどもの『発達を活かす』への照準合わせ
以前、下記のブログ記事にて『【こどもの発達を活かす】には2つのパターンある』という記事を書きました。
こどもの発達と個性を活かしバイリンガルを育てるグローバル子育て、林智代乃です。 グローバル時代に活きるバイリンガルに育ん…
ここへの捉え方・理解というのは、実はとっても大事な事。
その為、この部分について敢えて改めて書いてみますと、『こどもの発達を活かす』には
・今目の前にいる『我が子の興味関心であったり得意を活かす・伸ばすように』こどもの発達を『活かしていく』関わり
の2パターンが存在します。
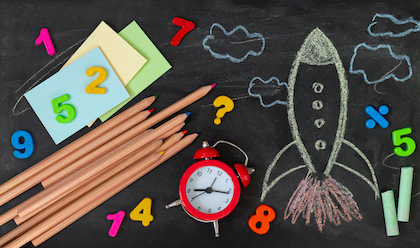
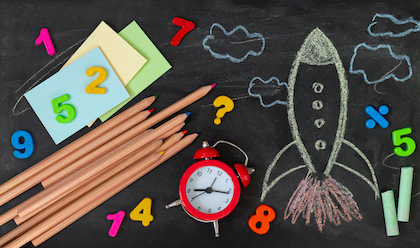
この2つのパターンには、
それは割と『詰め込み型』になりやすい
・『我が子の興味関心や得意を活かす・伸ばすように』関わる場合、
それは『その子その子に合ったサポートをしていく型』となっていく
といった大きな違いがあるんですよね。
要は、『誰の為のそれなのか』『誰が主語なのか』という部分ですね。
その部分を踏まえた上で、話を進めていきたいと思います^^
こどもたちにとって『教わる』ももちろん大事
先に結論からお伝えさせて頂きますと
となります。
ある程度の専門的な内容になれば、『教わる』という形で『学ぶ』事が必要とやはりなってくるんですよね。


ここでポイントは、教わる『時間』ではなく敢えて『時期』というワードを使わせてもらった事。
『時期』というのは、あるフェーズから移り変わってきて入った段階の事。
そう、
といえるのです。
こどもへの『引き出す』関わりが『教わる』学びを活かす時間になる
『教わる』という形が『時間』ではなく『時期』と敢えて表すのは、
となるからですね。
こどもから『引き出す』関わり時間がこどもの『教わる学び』への『準備時間』にあたる時間になるのです。


では、『こどもから引き出す関わり』とは、どんな関わりなのか。
これが先に挙げさせて頂きました『こどもの発達を活かす関わり』にリンクするものになっていきます。
『引き出す関わり』もどこに照準を合わせるのか
いわゆる『引き出す教育』と言われる『引き出す関わり』にも
・こどもの主体性を引き出し、こどもが興味関心に対して主体的に『もっと!』から生まれる探求の心をどんどん育んでいけるように引き出す関わり
と2パターンあります。
前者のパターンをしていく結果それが後者の関わりになっていく事もあったりと、前者・後者、どちらもオーバーラップする部分はあります。
ただその場合、後者のパターン出発からの前者のパターンになっていく流れが本当の意味での『引き出す教育(引き出す関わり)』だと考えています。


というのも、この前者・後者の違いが『教わる』スタイルに触れる際の教わる側のスタンスに違いを生んでいくものになっていくから。
前者のパターンから出発の場合、「目の前に感じられる困り感は誰が困り感として捉えているのか」というところがあるからですね。
もし、こども自身が『困り感』を感じてのそれだった場合、その前に必然的に後者のパターンが存在しているはずなのです。
…とやや余談を挟みましたが
ものとなるのです。
そしてこの違いは、『学びとったものを自分のものにしていけるのか否か』の違いにも繋がっていくのです。
『教わる』が受動的なものになるのか能動的なものになるのかの違い
同じ『教わる』でも、教わる側のスタンスはとっても大切です。
というのも、
からです。


『能動的な学び』になる『教わる』の姿勢は
・こどもの中から生まれる『疑問からの出発』からくるもの
…と全て『こどもの中から生まれてくるもの』ベースとなって出てくる姿です。
そしてこの『こどもの中から生まれるもの』って、
・こどもが興味関心に対して『もっと!』の探求の心をどんどん持てるように
・こどもが自己肯定感を持って物事に向かえるように
・こどもが自己効力感を抱いて物事に向かえるように
引き出していくような関わりをした先に生まれてくるものです。


要は、
という事。
また別の角度から言えば、こども自身がどれだけ『課題発見する力』・『問いを立てる力』を伸ばしていっているのかというところになっていくんですよね。
教わる姿勢が能動的でなく受動的だった場合、そこで受け取ったものは入っていかなったかり、詰め込み化になっていったりするものです。


因みに、『引き出す関わり』によって引き出されるものって、いわゆる『非認知能力』にあたるもの。
過去のブログ記事でも何度も書いてきていますが、
です。
その為、
・『教わる』に入る前の準備段階として『非認知能力を高めていく』事が大切。
と言い換える事ができるのです。
それでも気になる『教えなくて出来るの?』
そうは言っても
といった疑問が出てくると思います。


先ず
です。
いわゆる『学校のカリキュラムライン』で進む訳ではないですが、こどもたちは自分たちの力で色々と『気付く』事ができます。
例えばおやつの時間、『お皿に載った3枚のクッキーは1枚食べるとなくなる』という事を経験します。
また例えば、たくさん転がるレゴブロックの数を数える時、『1つ1つ数えるよりも10のかたまりを作ってみると早い』という事をその時、見つけ出す経験をします。
このように、あえて「●●を教えるぞ!」とならなくても、日常の体験そして興味関心からの発展を通してこどもは色々な事に『気付き』そしてそこから『学ぶ』事ができるのです。
実際、娘も図形の面積の求め方を積み木を使って導いていましたね。


この『気付き』にリンクするお話が『早期教育の本当の意味』についてのブログ記事になります。
ただ確かに、例えば算数であれば概念が理解できても式などでの表し方は教えないと分からないものです。
故にこの時は
という形で関わっていく感じです。
先に何かを提示するのではなく、今やっている事に対しての意味付け感覚。
『こどもの気付きに意味付け』の場合、
という事。
「これはこう表せるよ」と伝えるこの時は、受動的な学びではないんですよね^^
英語習得だって『引き出す』と『教わる』の関係性は同じ
この『引き出す』と『教わる』の関係に関しては、【英語習得】においても全く同じ事が言えます。
英語に対しての
事が英語力を一時的な『技術』的なスキルとしてではなく、英語をツールとして伸ばしていく『能力』としてのスキルになっていきます。
特にこれからの時代に求められる英語は『英語で何を語るのか』という自分を表現するツールですからね。
その上で欠かせないのは、こどもの興味関心をどんどん伸ばしていく『引き出す』関わりです。


また、過去のブログ記事にも書いてきていますが、
ものです。
要は、
という事^^
実際、キッズのコーチングでご一緒させて頂いているお子さんたちは、特別『英語』に特化して関わらせて頂いている訳ではなくても、その子の中から引き出した関わりだからこそ、普通に『英語が選択肢』になっている子が多いです。
『興味関心』『自己肯定感』『自己効力感』の存在は大きいですね!
…という事でこんな感じに、『教わる時期』は必要な時期で、その必要な時期の為の準備として『引き出す関わり』をしていく事が大切なのですよーというお話でした^^
教わる教育に馴染みにくいパターンって、天才的な賢さあるタイプ故の場合と『教わる』への耐性というか準備期間が必要な場合があると思うのです。
どんなに『自分で導いていきたい』だったりする子でも『教わる瞬間』ってあるんですよね。
この『教わる瞬間』までの道のりが長い子と短い子がいる…みたいな。
『引き出す』関わりの時間を過ごし、準備が整うと『教わる』への耐性がついてくるみたいな感じですね。
だからこそ『引き出す』という時間は大切にしないとな…と思うのです。