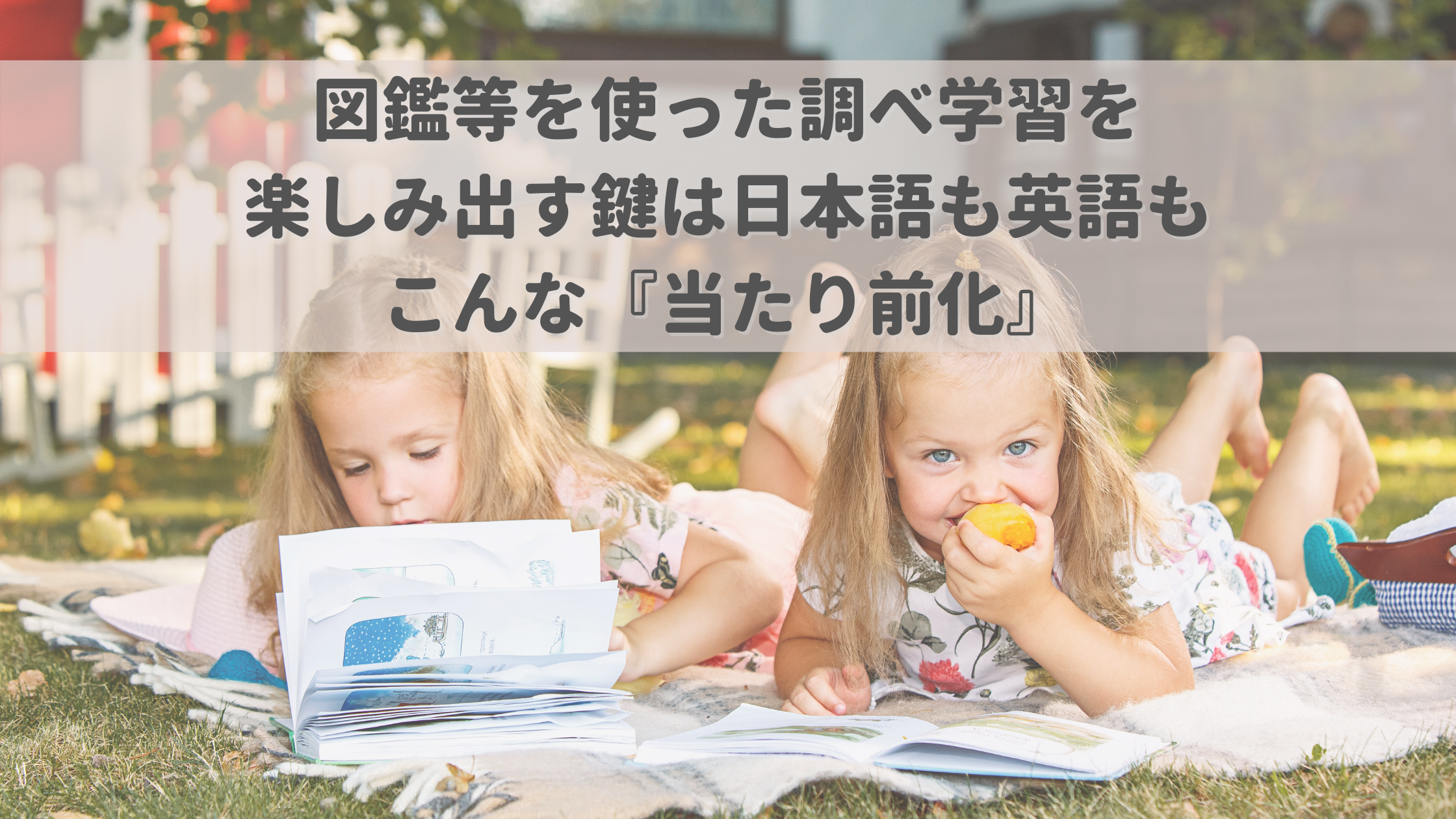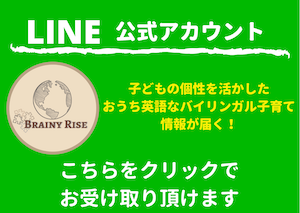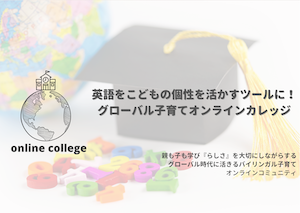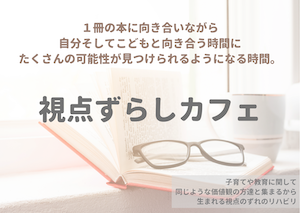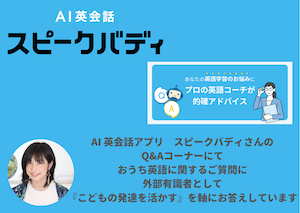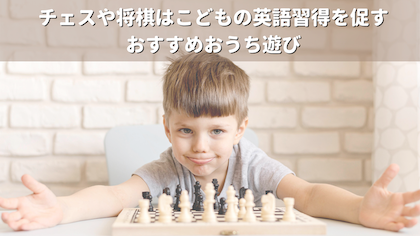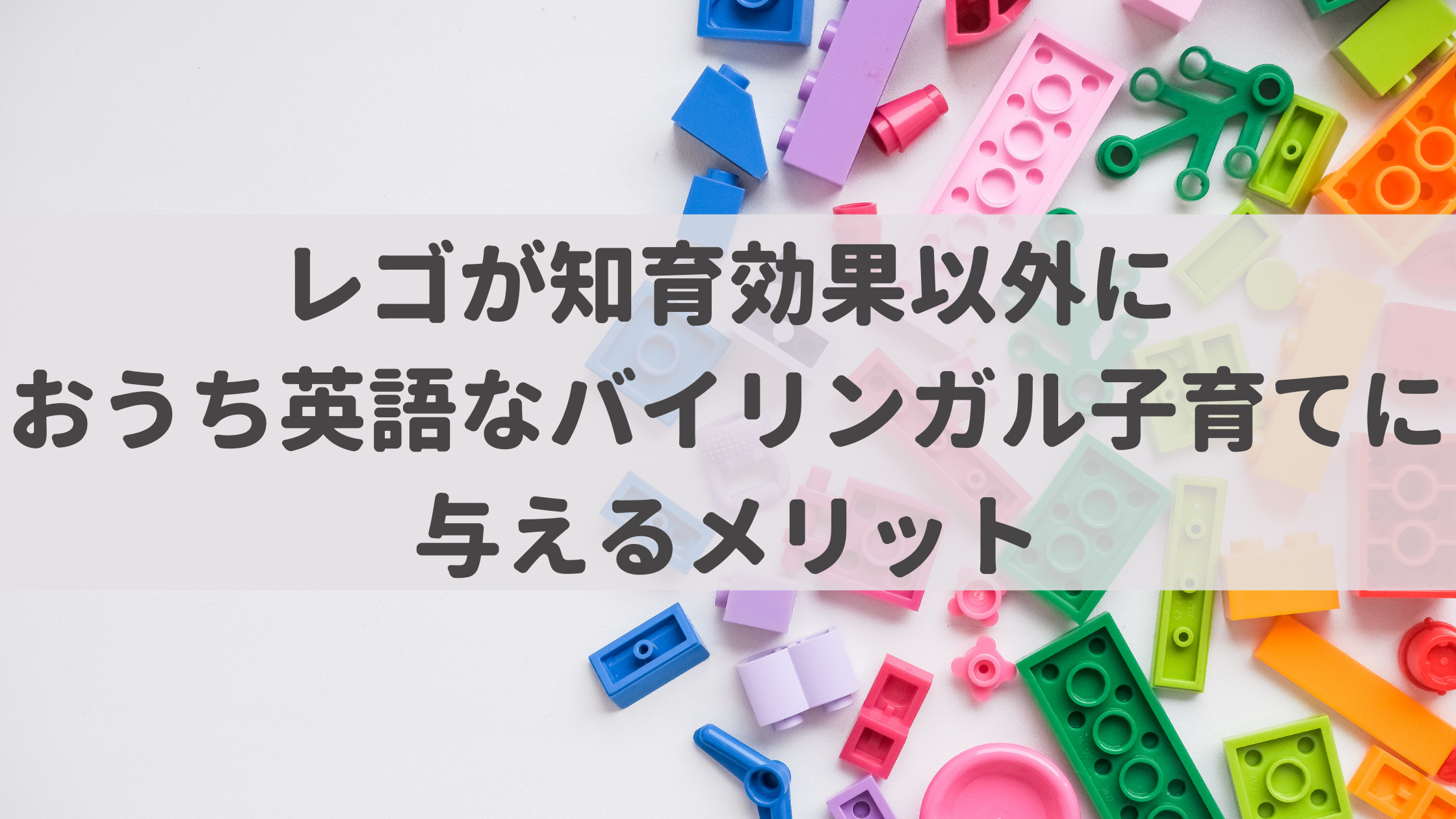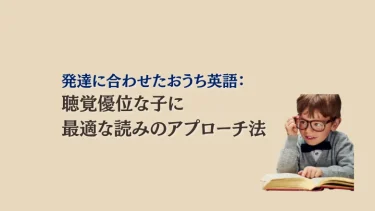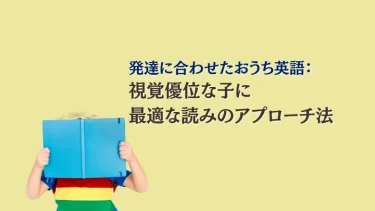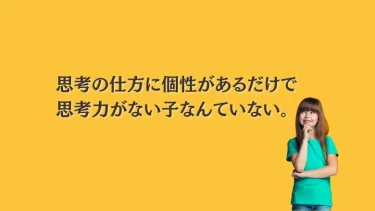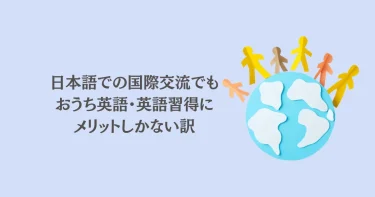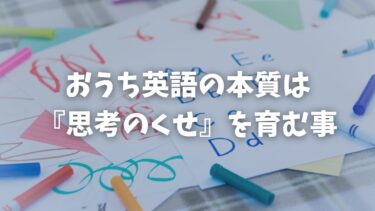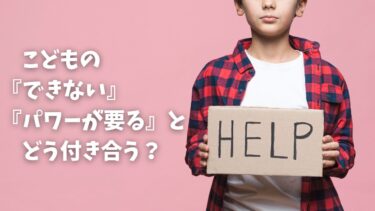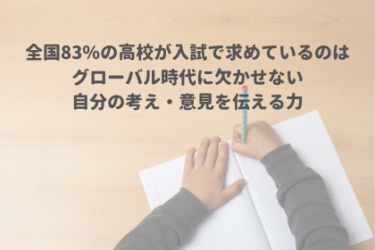こどもの『主体的』な行動力が求められるこの時代。
学習においてもその姿は必要な姿であり、
どのように主体的に学び取る力をこどもに育て、伸ばしていくサポートをしていこうか
と、おうちの方は常に考えられていると思います。

こどもが自ら調べるという姿/分からない事は調べるという習慣を持った姿
だったりすると思います。
この『自ら調べる姿』『調べる事の習慣化』というのは、教えて育んでいくのではなく、『気付くと生まれる当たり前化』によって育っていくものなのです^^
目次
「調べる」という作業こそが、
こどもの『自ら学び取りにいく力』
『調べる』という作業はとても大切な作業で、
この『調べる』という作業こそが、「自ら学び取りに行く」という力
といえます。


『自ら学び取りにいく力』だからこそ、「調べる事をさせる」のではなく「調べたくなるような導線を引いていく」事が大切
なんですよね。
「調べなさい」で調べるようになるのではなく、「知りたい!」と思う、こどもの中から湧き上がる気持ちが「調べる」事への習慣化になっていくと良いんですよね。
こどもが自発的に「調べる」ようになるまでのステップ
「調べる」時にツールの1つとなるのが、「図鑑」や「辞書」。
こちらでも『英語図鑑セット』や『英語辞書セット』を取り扱っている事もあり、
英語の図鑑や英語の辞書は、こどもが本を読んだり調べたりするようになってからが良いですかね?
といったご質問を頂く事があります。


というのも、
図鑑を絵本の延長といった存在にしていく為にも、「調べる」はもちろん「読む」が始まる前から、図鑑等を身近なとろこに置いておいてあげるのは大きなポイントとなる
からですね!
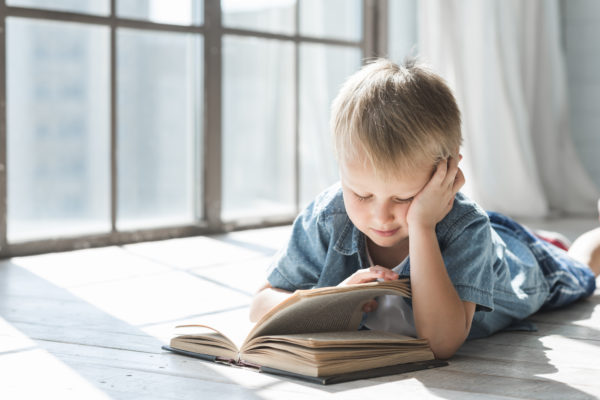
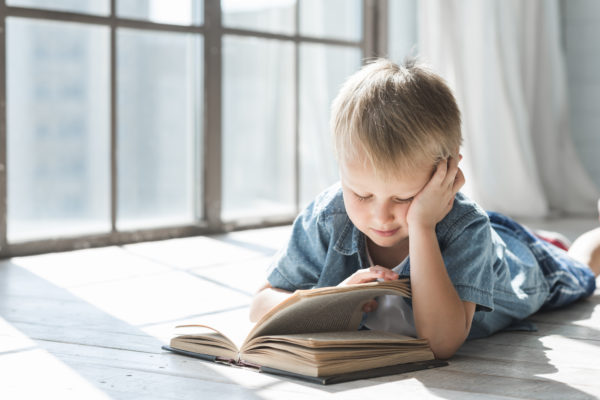
身近なものになっていくと、こどもにとって触れやすい存在になっていきますね!
そしてこどもが手に取って見る時、それがただ、『なんとなく眺める』というだけでもOKなのです。
というのも、
こども期、特に6歳を過ぎるくらいまでのこどもは、『ただ眺める』だけの時間からの吸収力はピカイチだから
ですね!


・その写真や図などが意味しているものは、何なのかを
『想像する力』が高く
・色々な図や写真などから見比べて違いに気付く
『差異に気付く力』『観察力』が高い
『想像する力』が高く
・色々な図や写真などから見比べて違いに気付く
『差異に気付く力』『観察力』が高い
からですね!
こちらからしたら一見何も吸収していなそうな時間ではあっても、その時間こそがこどもの能力を伸ばしていく時間になっていたりするの訳です。
そして、そういった時間こそが『図鑑等との距離縮め』にもなるのです。


その時に一役買うのは、おうちの方の関わりにあるのです。
「図鑑や辞書はわくわくが広がるもの」と
こどもに伝えていく
図鑑や辞書に書かれている文字の様子に圧倒されてしまった場合だけでなく、そうでないお子さんに対してもとても効果的な、そして調べ学習的なものを楽しめるか否かのポイントになってくるのがおうちの人の関わり方にあったりします^^


私たちは、大人になるまでの間の色々な経験から、「調べたら分かる」「図鑑等に触れる事で知識が深まる」という事を知っています。
ですが、こどもはその部分までまだ見えない事もあり、
そもそもで「調べる」という事の意味や「知識を広げる」ということの意味をあまり理解できていない
のです。


・情報は色々なところに載っているよ。
・この本には、こういった情報が載っているよ。
・リンクして広げる事ができるね!
・この本には、こういった情報が載っているよ。
・リンクして広げる事ができるね!
を水面下のメッセージとして出していくように関わる事も大切。
例えば、何かこどもに興味持ったり取り組んだりしている姿があったら
「あ!そういえば、その事、ここのページにも載ってたの思い出した!」
/
「ここにもその話の事が書いてあるね!」
程度にさらりといつもリンクするページをおうちの方が開きさりげなく、こどもの横に添えてみる
「ここにもその話の事が書いてあるね!」
程度にさらりといつもリンクするページをおうちの方が開きさりげなく、こどもの横に添えてみる
事をしてみたり。
または、時にこちらから「●●について知りたいのだけれど、それについて載っている本、持ってない?」なんて投げかけてみたり。


そうすると、自ずとその3つのメッセージをこどもは自然と受け取り、それを『当たり前化』していくようになります。
我が家も娘が1歳の終わり頃から、できる時にできるだけの形で小さく小さく積み重ねるをしてきています。
本当に、こちらの一人芝居ともいえるそれだけ。


・図鑑や辞書は絵本の延長線上として楽しみ
(まだまだ眺める専門!)
・何か話題にでれば、それとリンクするものを広げてきたり
・「分からない」があると、調べて書こうとする姿が出始めたり
(まだまだ眺める専門!)
・何か話題にでれば、それとリンクするものを広げてきたり
・「分からない」があると、調べて書こうとする姿が出始めたり
していますね。
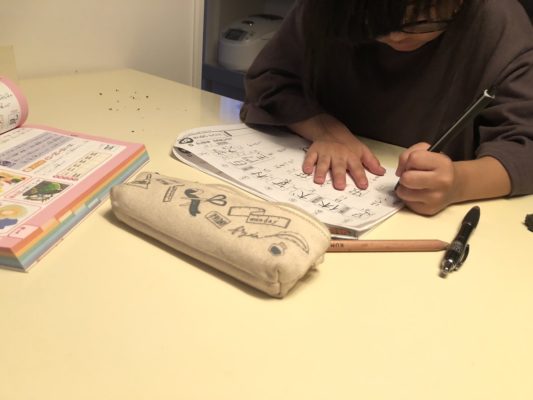
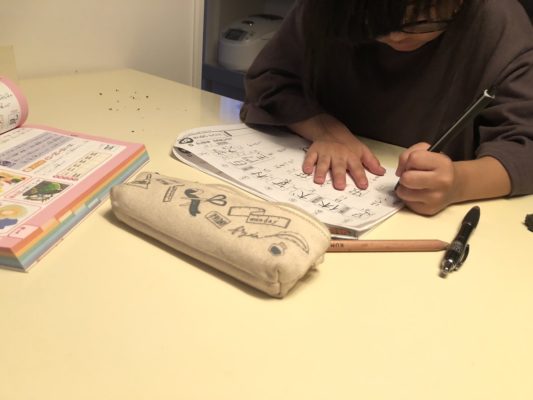
与えられたり義務付けられると嫌いになる
『調べる』という事に関して1番して欲しくないのは、「やらせる」「義務付ける」事。
本人が『調べよう』と思えていないのに始めてもただの「面倒臭いもの」になってしまうので、とにかく「調べたい」という気持ちに火を付ける事を狙う小さな積み重ねを焦らずに大切に積み重ねていってほしいです。
調べる事の質に関しても、
こども本人に調べたいという気持ちが起きてくれば自然とそこへのスキルは上がるし、
ノートにまとめる事も楽しめるようになれば自然とそこへの向上心の根が張られていき、
どんどん磨かれていく
ノートにまとめる事も楽しめるようになれば自然とそこへの向上心の根が張られていき、
どんどん磨かれていく
ものです。
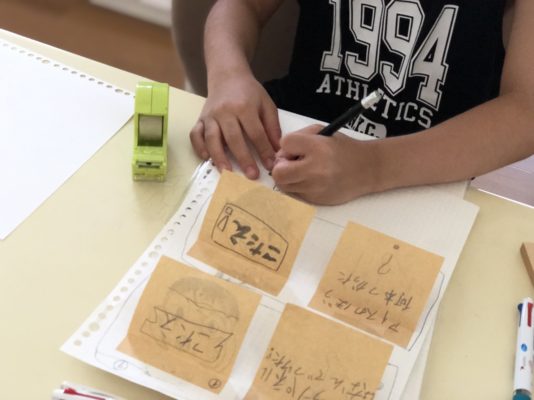
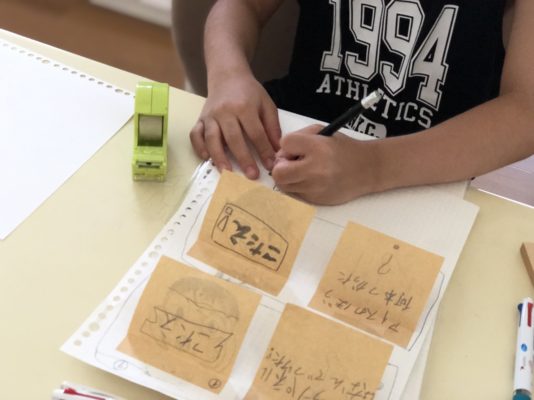
いや、実際は調べたい事を調べるのは好きで、結構とことん突き詰める型。
ですが当時は学校を通して「これを調べなさい」的な感じで与えられる機会が多く、それについては自分自身調べたくもないし興味もないからノートに書くのも面倒くさくてしんどかったんです^^;
故にやっつけ仕事になるから、クオリティーも上がらない。
…とそこから「調べ学習嫌い」が生まれてしまい、やらされなきゃやらないという経験が自分自身にもあります。
そう、自分自身にもあるからこそ、そう思ったりもするのです^^;


だからこそ、『与える』『取り組ませる』というのは逆効果になっていくのです^^
…とこのような感じで、『自分の力で調べる』という習慣化は自然とついていくものではあります。
ありますが、より「調べる」を楽しみ始められるようにする為にも
物事に対しての好奇心の高さ
は大切!
その為にも我が子には、「常にポジティブなエネルギーと共に物事に対してワクワクする力」を持っていって欲しいものですね!
ただいま、『英語図鑑セット』キャンペーン実施中!